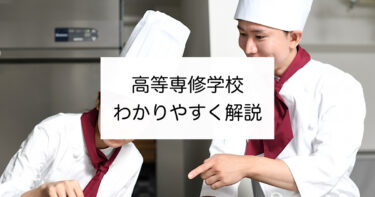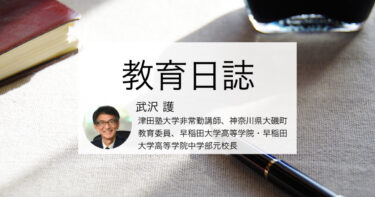こんにちは、千葉県の公立小学校で教員をしている山本裕貴です。小学校教員を目指し、必死に勉強していた大学生の頃には、アクティブ・ラーニングという言葉に注目が集まっていました。
アクティブラーニングとは、教員による一方的な講義形式の授業ではなく、生徒が能動的に考え、学習する教育法のことを指しています。アクティブ・ラーニングは、いつしか「主体的・対話的で深い学び」という言葉に変わりました。しかし、教育に大切なことは変わっていません。
私は学級づくりの中で、ずっと「対話」を大切にしてきました。対話を通して学ぶことが、子どもたちに必要な学習だと強く思っています。対話には多くの効果があります。例えば、対話をすることで「思考が整理される」「知識が定着する」「学習意欲が高まる」という学習効果が期待できます。また、対話とはコミュニケーションですので、子ども同士の人間関係を紡ぐことにも大きな効果を発揮します。これらは、私が学級担任をしていく中で実感したことです。
では、そもそも対話とは何なのでしょうか。辞書を引いてみると対話とは、「向かい合って話し合うこと」と書いてあります。まあ、たしかにその通りなのですが、これでは子どもに上手く伝わりません。
子どもたちに理解してもらうために、私は4月に子どもたちと「本学級における対話の定義」について共有します。具体的には、次のように語ります。
「君たちは、対話という言葉を知っていますか?」おそらくここでは、子どもたちは知っている!と答えるでしょう。続けて、「では、対話と会話の違いはなんでしょうか?」と聞いてみてください。これには、子どもたちも答えられないことが多いです。
「分からないときは、自分の持っている知識で推測することが大切です。対話は、対で話す。会話は会って話す。と書きますね。しかし、辞書を引いてみると、あまり違いはありません」「でもね。先生は対話というのをとても大切にしています。だから、先生は対話を次のように定義しています」
「対話とは『対等な立場で、目的を達成するために話し合うこと』です。つまり、授業の中で友達に自分の考えを伝えたり、話し合って問題を解いたりすることです。だって、休み時間に友だちと話しているのを対話とは言わないですよね。それは会話です」
「対話をすると良いことがとってもあります。先生は授業の中で、たくさん対話の場面を作ります。一生懸命に対話して、成長しましょうね」このように、具体的に説明することで子どもたちと対話の定義を共有できるでしょう。また、大切なことは子どもたちに対話の良さを実感させるために、くりかえし対話活動を実施することです。
今回は私が学級づくりの中で大切にしてる「対話」についてお話しました。次回は「対話の3つの類型」についてお話しします。ここまでお読みいただき、ありがとうございました。