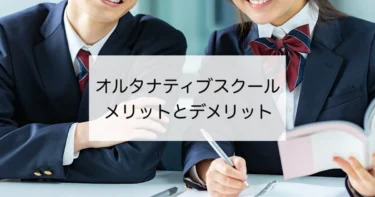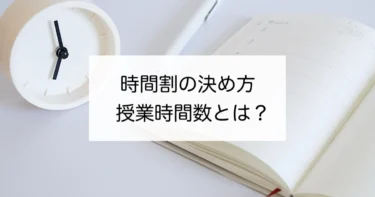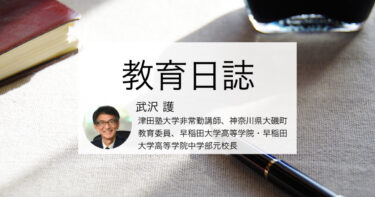こんにちは。千葉県の公立小学校で教員をしている山本裕貴です。前回は対話の3つの類型についてお話しさせていただきました。まだお読みでないからはぜひ上記のリンクからお読みください。
あなたはどのような形式で対話を行っていますか。今回は、「対話の形式」について詳しくお話ししていきます。
対話活動をするときに、よく耳にする言葉が「お隣の人と相談しましょう」というものです。これは一般的に「横の人と二人で話しましょう」という意味だと思われます。学級で考えると隣の席の友達です。私の学級でも、45分授業の中で複数回短い対話活動を行います。そのようなとき、毎回横の友達とばかり話していると、飽きてしまい授業への集中力も切れてしまう可能性があります。それを防ぐためにも、私は4月の学期初めに「対話の形式」について、子どもたちに教えています。
具体的には、次のように言います。
「先生は、授業の中でたくさん対話してもらいたいと思っています。でも、毎回同じ人とばかり話すのは、正直あきてしまいますよね。ですから、対話をしてもらう前に形式の指示をします。その形式で対話してください」
このように伝え、図を黒板に書いて説明します。
①【横のペア】横に座っている友達と対話をします。最も一般的な対話形式です。
②【縦のペア】座席の縦方向の友達と対話をします。前に座っている人が、後ろを向いて話します。
③【斜めのペア】座席の斜め方向の友達と対話をします。斜め同士で向かい合って話します。
④【3人組】近くの人と3人組を作って対話をします。あらかじめ、3人組を指定しておきます。
⑤【4人組】生活班の4人組で対話をします。短い対話のときは、机を動かさずに話し合います。長い対話のときは、机を向かい合わせにします。
⑥【立ち歩き】座席から立ち歩いて対話をします。なるべく自分の席から遠い友達と話すとよいことを伝えます。
⑦【同じ意見の人と】自分と同じ意見の人を探して対話をします。じゃんけんの「グー」「パー」を使うと分かりやすいです。例えば「〇〇に賛成の人はグー、反対の人はパーを出しましょう。それでは、同じ意見の人を見つけて対話してください」
⑧【違う意見の人と】自分と違う意見の人を探して対話します。やり方は⑦と同様です。
このように、対話の形式を示しておくことで「それでは、横のペアと話しましょう」「では、立ち歩いて意見交換しましょう」などと色々なパターンの対話活動を行うことができるようになります。子どもたちの対話がマンネリ化しないように、組み合わせて行うのが有効です。
今回は「対話の形式」についてお話しました。私は初任のころから、学級づくりの中で対話を大切にしています。子どもたちの成長に不可欠だと思うからです。そして、もう一つ大切にしているものがあります。それは音読です。次回はその「音読」について詳しくお話しします。ここまでお読みいただき、ありがとうございました。