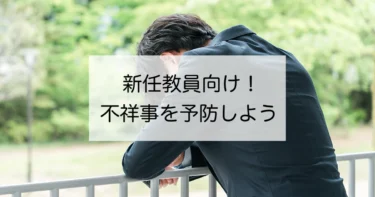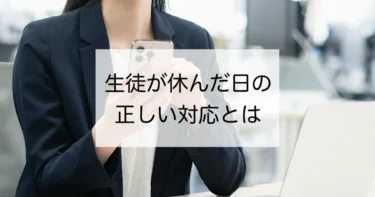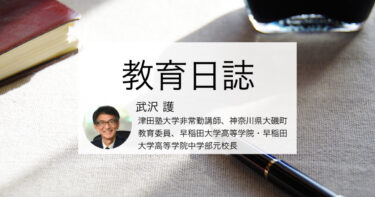こんにちは、千葉県の公立小学校で教員をしている山本裕貴です。今回は、私が学級経営や授業づくりをする上で重視している「音読」について話していきます。
どこの小学校でも音読は行われていますが、高学年になるにつれてだんだんと少なくなっていくように思います。たしかに、発達段階が進むことで音読から黙読へ移行する必要もあります。また、音読は「国語科」のみで実施されることが多いです。主には教科書に載っている教材文のみを音読するケースが見受けられます。しかし、それではもったいないと思いませんか?
私は高学年でも、どんどん音読するべきだと考えます。また国語科のみでなく、全ての学習活動において音読を取り入れるべきです。音読には、子どもを育てる多くの効果が期待されています。では、それはどのようなものなのでしょうか。
文部科学省では音読について、「音読は、黙読の対語だから、声に出して読むことは、広く音読である」と説明しています。つまり、声に出して読む全ての活動は音読だといえます。また、音読には記憶力や集中力、語彙力を高める効果があると言われています。
私は学級開きをしたあとに、いつも子どもたちに音読について説明をします。具体的には次のように語ります。
「学校では、たくさん読む活動をします。読む活動は大きく分けて、2つあります。それは何か分かりますか」このように尋ねると大体は「音読です」と子どもは答えます。
「そうです。1つは音読です。では、もう1つはなんでしょう」こちらは、すぐには答えられません。「ヒントは、音読の反対です」と伝えると数人の子は「あ!黙読です」と気付くことができます。
そもそも、この時点で「黙読」を知らない子も結構います。ですから、漢字を見て意味を教えていきます。「黙読は、黙って読むから黙読ですね。それに対して音読は、音(声)を出して読むから音読ですね。みなさんは、今までたくさん音読をしてきたと思います」このように話すと、多くの子はうなずきます。
「では、良い音読とはどのようなものですか」と尋ねます。だいたいは「大きい声で読むこと」などと子どもは答えます。そこで次のように伝えます。
「先生が考える良い音読とは、次の3つが達成されているものです。その3つとは『正しく』『はっきり』『スラスラ』です。
まず、文章は正しく読まなければいけません。正確に読めることが第一です。
つぎにはっきり読むことです。ぼそぼそと聞き取りにくい音読ではだめです。はっきり聞きやすいように読みます。
最後にスラスラです。文の区切りが変だったり、たどたどしい読み方だったりしては良い音読とは言えません。
1年間、たくさん音読することで良い音読ができるようになります。がんばりましょうね」このように伝え、あらゆる場面で音読をしていきます。
ちなみにこの3つは、文部科学省が示している「正確・明瞭・流暢」を子どもに理解しやすくしたものです。音読を続けると、本当に子どもたちは大きく成長します。これから、もっと音読を取り組んでいきましょう。
というわけで今回は音読についてお話ししました。次回は、「音読の4機能」についてお話ししたいと思います。ここまでお読みいただき、ありがとうございました。