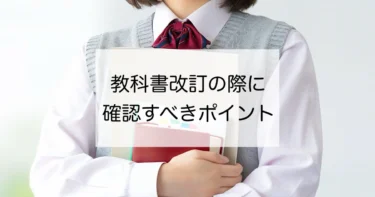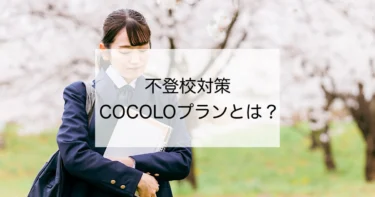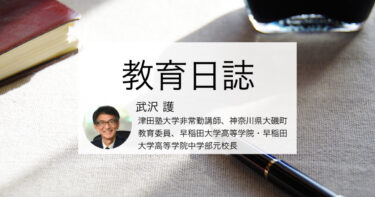こんにちは。千葉県の公立小学校で教員をしている山本裕貴です。前回は、良い音読についてお話ししました。私が考える良い音読とは「正しく」「はっきり」「スラスラ」読むことです。良い音読を重ねていくことで、子どもの個々の力が伸びていくのはもちろんのこと、学級全体の雰囲気も良くなっていきます。
今回は前回に引き続き、音読の機能についてお話ししていきます。 私は音読には大きく分けて4つの機能があると考えています。それは【①読解促進機能】【②思考表現機能】【③記憶定着機能】【④意欲向上機能】です。1つずつ詳しく解説していきますね。
【①読解促進機能】は、「声に出して読むことによって、文章が理解しやすくなる」ということを意味しています。音読と黙読では、圧倒的に音読の方が時間がかかります。しかし、黙読では読み落としてしまうような箇所も、声に出すことによって読み落とすことが少なくなります。
【②思考表現機能】は、「読み方を変えることによって、自分の考えを表現する」ということを意味しています。植草学園大学名誉教授である野口芳宏先生の有名な発問で考えてみましょう。
ごんぎつねのラストシーンです。兵中のセリフである「ごん、お前だったのか」の語尾を上げて読むか、下げて読むかというものです。上げて読むならば驚愕、下げて読むならば落胆を表現できます。みなさんならば、どちらで読みますか?
【③記憶定着機能】は、「読むことによって、内容を覚える」ということを意味しています。
先ほども述べましたが、音読は時間がかかりますが、その分記憶にも残ります。また自分の声が耳から入るため、記憶として定着しやすくなります。受験勉強をするときに、声に出して暗記する方法を思い浮かべると分かりやすいと思いますよ。
【④意欲向上機能】は、「音読すると、やる気が出る」ということを意味しています。これは、実際にやってみると、すぐにわかります。
高学年の教材文は、長いものが多いため、黙読していたり、教師が読むのを聞くだけだと、子どもは飽きてしまいます。そこで、音読を取り入れてみてください。子どもたちが活発に、意欲的に取り組む姿を見ることができます。
このように、音読には4つの機能があると私は考えています。少しでも、音読の良さを再認識してもらえたら嬉しいです。
今回は音読の4つの機能についてお話ししました。音読というのは、ただ読ませているだけだと、マンネリ化して子どもが飽きてしまいがちです。そこで次回は「音読の手法」についてお話ししたいと思います。ここまでお読みいただき、ありがとうございました。