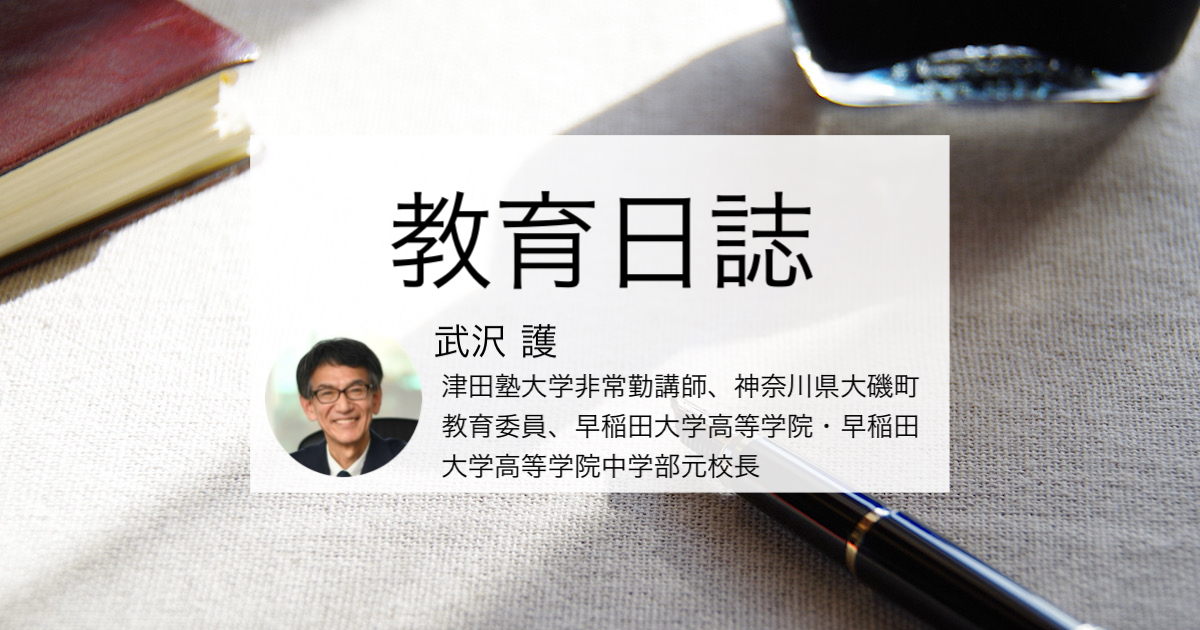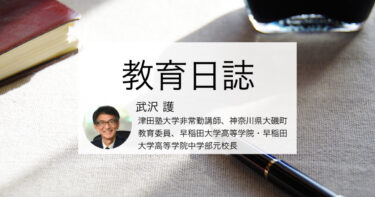2025年3月で45年間にわたる教員生活にピリオドをうちました。
現在、教員という職業が社会的に不人気な時代を迎えていますが、この職業がどのようなものか筆者の紹介も兼ねて45年間を振り返っていきます。
私は、教員養成を専門としない理工学部数学科に進学し、大学院修士まで学んだのち、教員となりました。
教員生活の45年間の前半は、公立高等学校の数学教諭、次に行政職として教育センターの指導主事(算数・数学、情報教育)、そして後半は、大学附属中高教諭に加えて、教職大学院の客員教員、さらに最後の4年間は中高の学院長(校長)として過ごしてきました。
大学教育において学問としての「専門的な教職」を学んだ経験のない私が、教員人生において出会った出来事、悩んだ様々な事柄および、考えなどを振り返りながら、極私的な意見ですが、「教職とは何か」について考えてみたいと思います。
教員という職業が「やりがいのある仕事」のひとつであることが読者に伝わればと思いながら筆を進める予定です。
まず初回は、わが国の明治以降の教員養成の歴史を振り返ってみます。
明治以降、第二次世界大戦まで(戦前)のわが国の教員養成のシステムはいわゆる「師範学校」に代表される職業目的制を中心とした学校教育制度でした。
現在でも、医師になるためには「医学部」、弁護士になるのには「法学部」を卒業しないと原則的にはその目的の職業に就くことができないように、戦前は「教員」になるためにはその目的に沿った学校を卒業・修了しなければなりませんでした。
それが、第二次世界大戦後(戦後)の教育改革のひとつとして「開放制」すなわちさまざまな大学において設置される教職課程の所定の単位を取得することで教員になれる新たな制度が確立したわけです。
いわゆる「教員養成大学」や「教員養成学部」を卒業しない学生でも教員資格をとることができるようになりました。
さらに、この教員養成に関わる戦後の大きな改革のもうひとつが2008年に開設された「教職大学院」です。実は、この制度にも筆者は後年、深い関わりを持つことになったのですが、この件についてはまた、稿を改めてお話します。
今回は、筆者の紹介と、明治時代以降の教員養成の歴史についてお話しさせていただきました。次回またお会いしましょう。