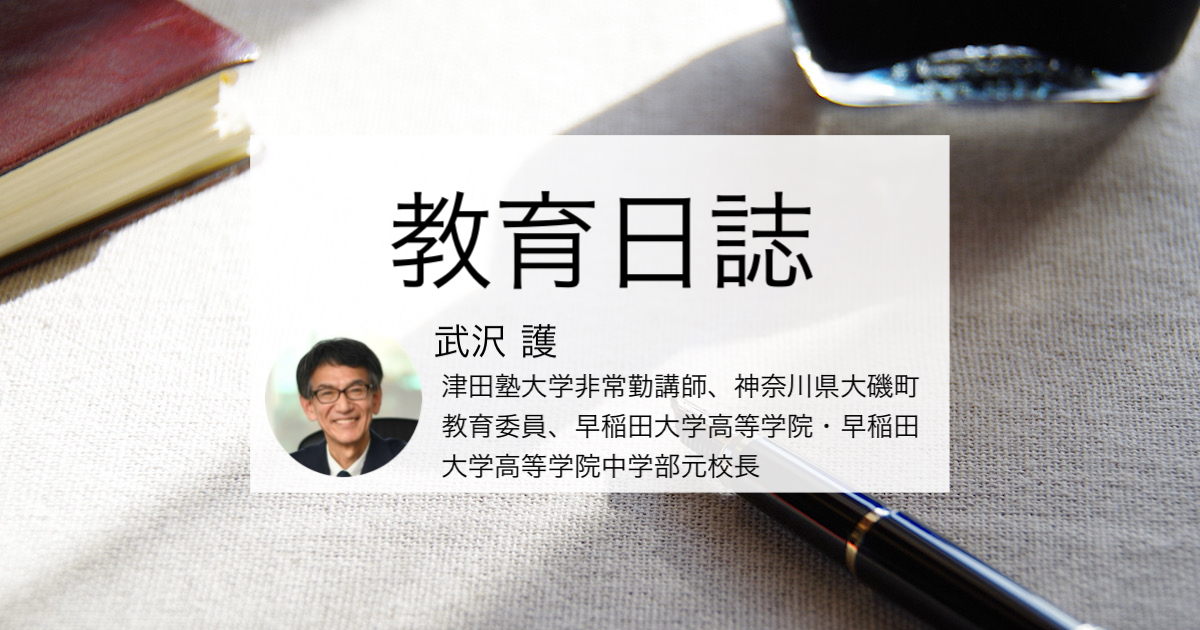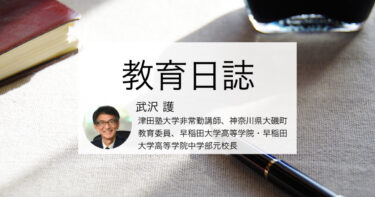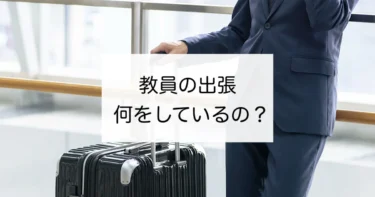第2回は、男女別学・共学についてお話しましょう。
まず、今回は男女別学・共学の歴史を振り返ります。いまから45年前、最初に赴任した高校は湘南地方にある公立の男女共学の進学校でした。この学校は、戦前の高等女学校の流れを汲む高校でしたが、戦後に共学となりました。
わが国の戦後教育の改革として、「高校三原則」というものがあったのをご存知でしたか。これは、旧制中等学校間にあった格差を是正して、小学校・中学校とともに高校をできるだけ地域学校化してその普及を図ろうとする考えによるものです。そして、その3つとは「小学区制」、「総合制」そして「男女共学」の原則です。
まず、「小学区制」について説明します。これは通学区域をできるだけ小さくして区域内の進学希望者はすべて地域の学校に無償で通学できることを目標にした制度でした。しかし、戦後しばらくすると、この学区制は各地方では中学区制、大学区制となり、現在に至っています。
次の「総合制」は、同一学校の中に普通科と専門学科(商業、工業、農業)など多様な課程・学科を併設し、子どもたちの全人的な発達を目的としたものですが、これも普通科と専門学科と単一の学校の流れになっていきます。
三つ目は、「男女共学」です。これは戦前の旧制中学(男子)や高等女学校というように別学を基本としていたものの改革です。
各地域では、旧制第一中学、第二中学という男子校、高等女学校は第一高女、第二高女という女子校で「ナンバースクール」として有名でした。
東京都の例でいうと、府立一中が都立日比谷高校、府立二中が都立立川高校、府立第一高女は都立白鴎高校、府立第二高女が都立竹早高校というような改組が各地方で行われました。
こうして、戦後の公立高校は男女平等の原則に従い、共学に改組されて現在に至っています。各都道府県の伝統校の歴史を紐解くことで男女別学から共学の歴史が読み取ることができますね。
しかし、例外もありました。それは北関東と一部東北地方です。現在、埼玉県立高校では一部の別学校での男女共学化が話題になったことは記憶に新しいところですね。
また、首都圏の私学でも、かつて別学だった学校が共学化されるところも増えてきました。男女別学・共学にはこのような歴史があります。
次回は、男女別学・共学のそれぞれの特色についてお話します。
今回は、男女別学・共学の歴史について振り返りました。次回またお会いしましょう。