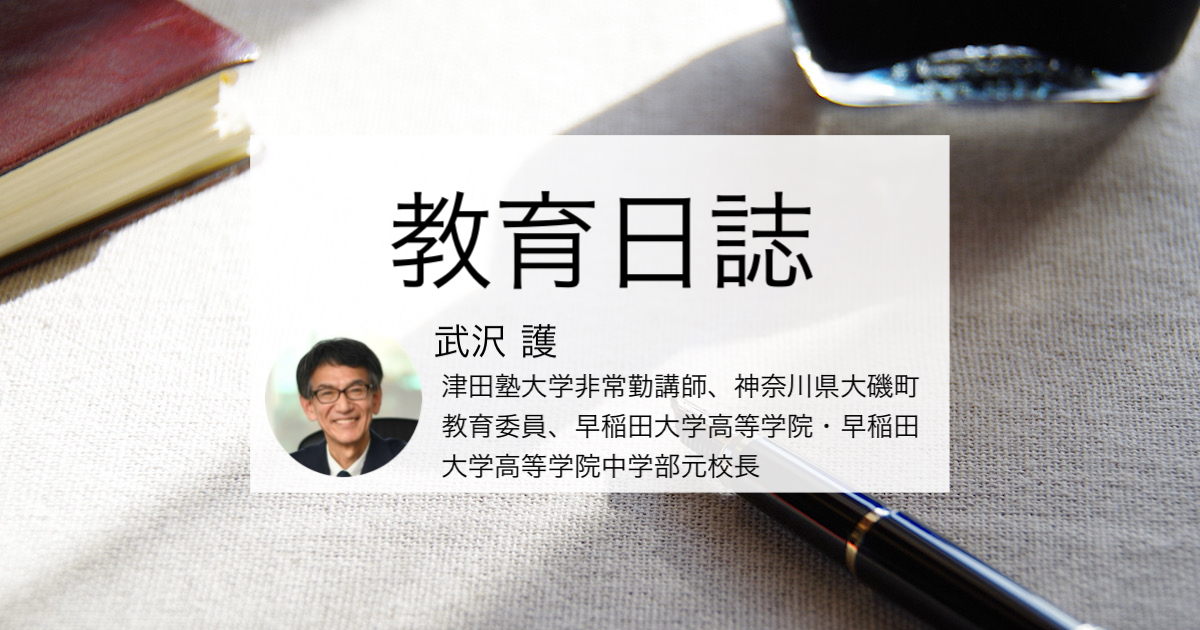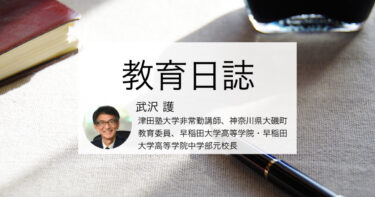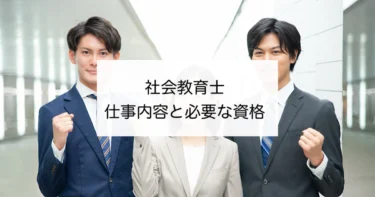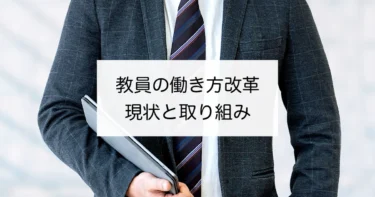今回は部活動についてお話します。
私自身、学生時代は合唱部や吹奏楽部に所属していました。しかし、教員になって最初の勤務校では男女ハンドボール部の顧問として10年間を過ごしました。技術的な指導は専門の先生がいたので、私は副顧問という立場でしたが、活動は多岐にわたりました。平日は放課後の練習、土日は練習試合や大会への引率、さらに夏季休業中には男女の合宿にも引率するなど、文字通り部活動に明け暮れる日々でした。家族にも少なからず迷惑をかけたことと思います。その後の勤務校でもハンドボール部を担当することが多く、最後の勤務校でもハンドボールの顧問で教員生活を終えました。
この3月に定年退職し教員生活にピリオドを打ちましたが、その後、各学校時代のハンドボール部のOB・OGから声がかかり、退職祝いの会を催してくれました。最初の勤務校の教え子は今や60代。かつての思い出話に花が咲き、教え子の成長を見るにつけ、教師冥利を実感しました。
教員の仕事は、生徒たちの在学中のみならず、卒業後も彼ら彼女らとの付き合いが継続できるという、他の業種では決して得られないものだと改めて感じています。
しかし、最近は部活動について、様々な課題が表面化しています。それは主に教員の働き方についてです。部活動は法的には拘束力がないので、ある意味で教員のボランティアに近い形で行われてきました。また、部活動がその教員の専門性に近ければいいのですが、私の場合のように、必ずしもそうではありません。
現在、国や各地方自治体は部活動について様々な工夫をして、教員の負担軽減に取り組んでいます。私が今、教育委員をしている神奈川県大磯町も、「大磯方式」というシステムで外部人材の活用を積極的に行っています。
今後、部活動は欧米のように学校教育から離れて、地域中心の活動になっていくのでしょう。
一方、部活動にも教育的意義があります。
授業やHRだけでは見ることのできない生徒の様子、また卒業してからも続く教員とのつながりは、授業担当やHR担任した生徒以上に濃い人間関係を育むことができます。
教員は、生徒にとって授業をする「先生」であるだけでなく、広い意味で彼ら彼女らの「ロールモデル」です。少子化のため兄弟も少ない、現代の生徒たちにとって、学校という場は人間関係を構築するためにも貴重な場でもあります。授業だけでは得られない、大人としての教員や異学年の生徒との交流ができるからです。
部活動が学校から離れても、学校ではこのような場を確保することがますます重要になってくるのではないでしょうか。
次回は第2回でお話した「総合制」を改めて取り上げます。