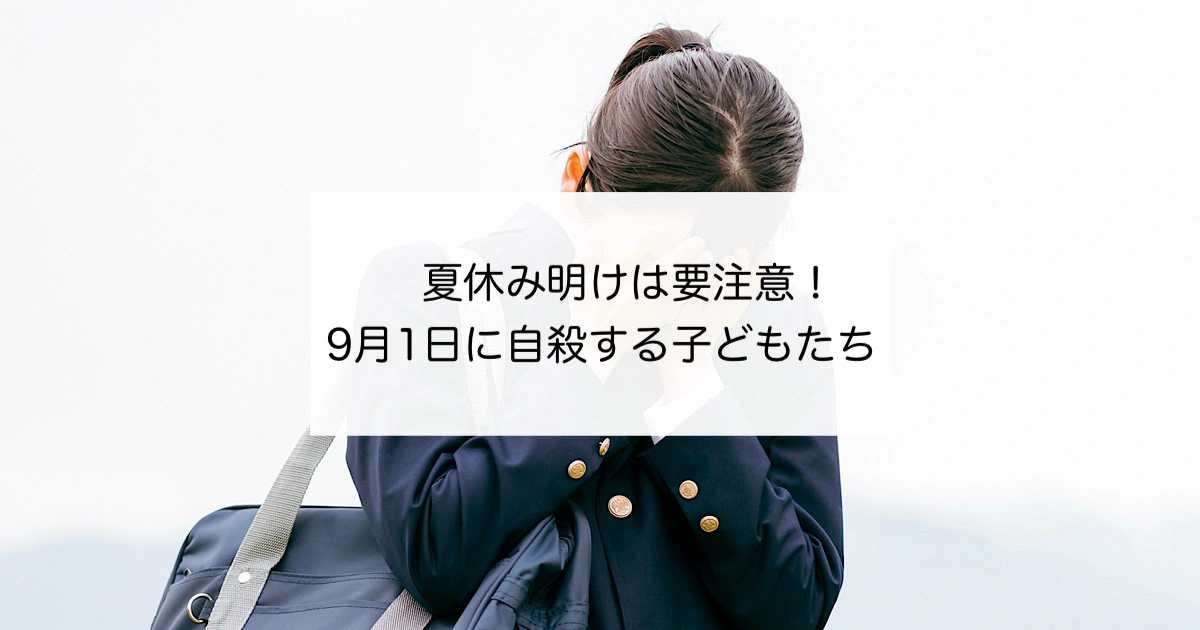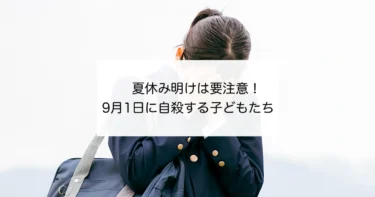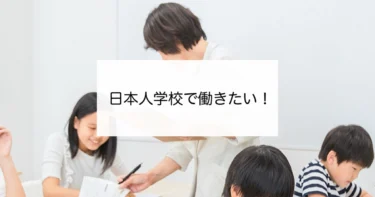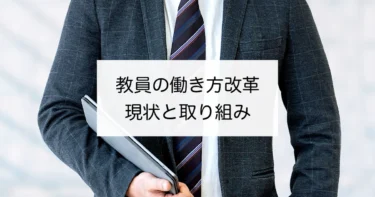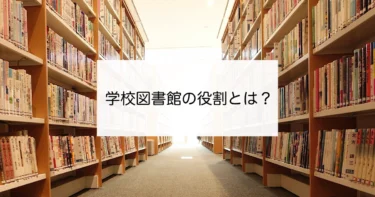9月1日は最も「子どもの自死が多い日」と言われているのをご存知でしたか。
文部科学省の公表している「18歳以下の日別自殺者数」の過去40年間の平均値からもわかるように「9月1日」は極端に多く、新学期よりも多い傾向があります。
教員は子どもたちを守るためにも「9月1日」という日を子どもたちにどう迎えさせるのか考えて行動しなければなりません。既に夏休みに入っている場合も、次の長期休み前や翌年のために、こちらの記事を読んで心構えをしておきましょう。
ライター

emikyon
・元公立学校教員
・教育委員会にて勤務
・eduloライター歴3年
まずは事前準備をしよう
夏休み期間は長いところで40日近くに及び、その間の出校日も1日または2日というところがほとんどではないでしょうか。中学校であれば部活動があるので、もう少し学校に来ている生徒も多いと思いますが、小学校の場合1か月以上も姿を見ないことになります。
これだけ長い休みがあれば、子どもたちは成長する部分がある一方、これまでに作ってきた生活リズムが大きく乱れ、家庭環境の影響により様々な「格差」ができてしまいます。
1学期担任をしてきた教員から見ると「夏休み大丈夫かな」「ちょっと心配だな」と思った児童生徒もいるのではないでしょうか。読者の中には、休み前に声をかけるなどの予防線を張った人も多いでしょう。こうした「事前確認」がとても大切です。
例えば、家庭環境が心配な人は、スクールソーシャルワーカーや児童相談所などと相談している人もいるのではないでしょうか。ここまでできていれば完璧な対応とも言えます。
こういったことができていないという方は、ぜひ来年こそは「事前準備」をしておきましょう。1学期の保護者会は休みをどう過ごすのか、事前情報を仕入れるのにとてもよい時間です。「気になる児童生徒」がいる場合には、休みの前と休みの期間どうするのか、対策を立てておくことが大切になります。
子どもが夏休み明けに登校しにくくなる理由を知ろう
夏休み明けに「自殺」が増えてしまう理由は何なのでしょうか。はじめに、自殺の理由は人それぞれであり、どれが多いという断定的なことは言えません。
ただ、自殺につながる要因としてよく挙がるのが次の例です。
①学校での人間関係の悩み(いじめ・孤立・友人トラブルなど)
②学業不振、進路への不安
③家庭内問題や関係性の悪化
④精神的な不調(生活リズムの変化など)
⑤将来への不安、新しい世界を知るきっかけ
普段の生活でも起きやすそうな理由ばかりですが、夏休み明けは①~⑤の複数の要因が重なりやすい時期でもあります。
特に、普段とは違う生活リズムになるため、④の要因が根底にありつつ、①や②の内容が重なってくると子どもの心が耐え切れなくなってしまうのです。
夏休みは、子どもにとって楽しい時間かもしれませんが、一人一人を見ていくと「楽しい」と思っている人は全てではないと意識する必要があります。
学校に通いやすくするための取り組みをしよう
子どもの自殺事案に対する取り組みは、学校だけでなく自治体でも行われています。
学校独自としては
・夏休みの課題を少なくし、宿題への負担感を小さくする取り組み
・サポートルームや不登校支援教室を活用し、始業式に通常の登校以外を許可する取り組み
などがあります。
自治体や教育委員会では
・自治体独自の子ども相談窓口を設けて、夏休み中の子どもの悩みに対応する取り組み
・支援が必要な家庭へのスクールソーシャルワーカーの派遣をおこなう取り組み
などが行われています。
文部科学省の大臣メッセージや内閣府の「孤独・独立対策推進室」でもオンラインで気軽に相談することができる場所を設置して、子どもたちの心の負担を少しでも減らす取り組みが行われています。
一方で、夏休みは「他者による気づき」が得にくい時期でもあります。学校に来ていれば教員が子どもを見ていますし、周りの友達もたくさんいます。夏休みに入ると自宅での時間が多くなり、人と接する時間が短くなるため、結果的に支援が遅れやすいのが特徴といえます。
何気ない情報に耳を傾けておこう
筆者もこれまで何度も自殺事案にかかわった経験があり、事務局(教育委員会)に勤務していたころには、背景調査を実施したこともあります。そのときに自殺を選んでしまった理由を知った際には「なぜそんなことで」や「学校では対処できない」と思うことが多々ありました。正直なところ「どんなに優秀な先生でもこの背景には気づかない」と思ってしまうような理由が圧倒的に多いです。
しかしながら、どんなに原因究明が難しくても教員である以上は「子どもの命を守る」ということは大切な使命です。
すでに夏休みを迎えてしまっていてもやれることはあります。まずは、次に挙げるようなことが起きていないか、今一度見直してみてください。
・夏休みに入って素行が変わったという話を聞いた
・普段来ていた部活動に姿を見せない状態になった
・保護者の異動(転居や離婚など)の情報が入った
こんな情報が入ってきたら注意しましょう。
少しおせっかいになるかもしれませんが、保護者に電話連絡をして事情を確認したり、子ども本人と話をすることができれば様子を聞き取るのもよいです。何気ない話かもしれませんが、耳を傾けておく高いアンテナが大切になります。
子どもをみんなで守る 学校に無理やり来なくてもよい空気づくり
子どもが自殺をするということは、決してあってはならないことです。しかし、現実には多くの子どもが悩んでいるのも夏休みの特徴です。では、夏休み明け、どうしたら子どもたちが元気な姿を見せてくれるのでしょうか。
一つのポイントとして「空気づくり」を提案します。まずは、学校に来ることを第一に、来ることができなければ会話だけでも、顔だけでも確認する。間違っても「宿題をやってからこい」や「必ず来なければいけない」という雰囲気を出すのではなく、無理に来なくてもよいという空気を作って子どもを迎えましょう。
そして、学校側だけでなく、保護者側も「無理をさせなくて大丈夫」という空気感を作り出すことができるように、事前に情報共有をしておくことも大切になりますよ。
参考文献:18歳以下の日別自殺者数,文部科学省,https://www.mext.go.jp/content/20200824-mext_jidou01-000009294_011.pdf,(参照2025-07-14)
参考文献:文部科学省 文部科学大臣メッセージ「~不安や悩みがあったら話してみよう~」,https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/mext_00003.html,(参照 2025-7-14)