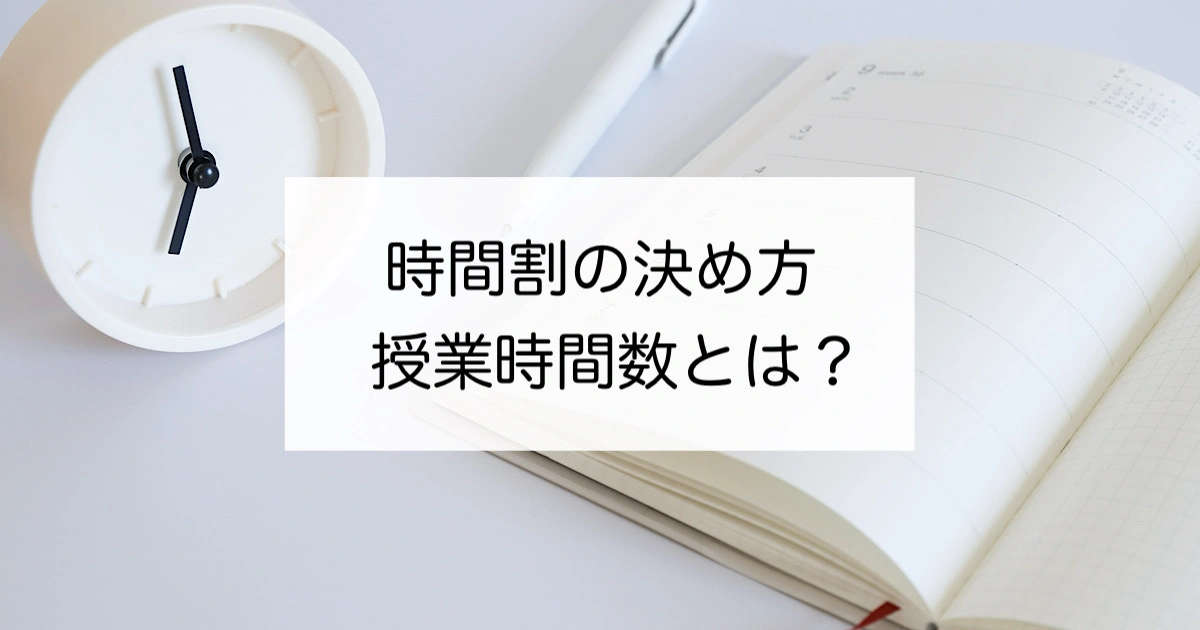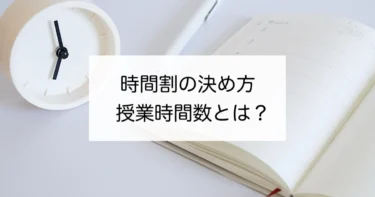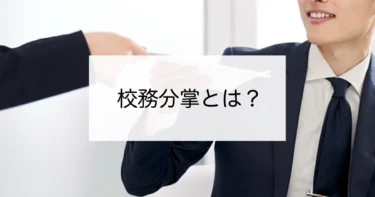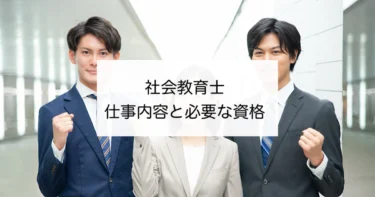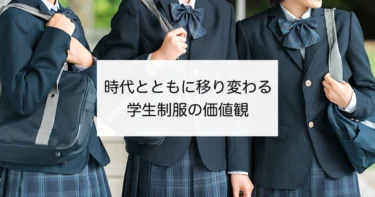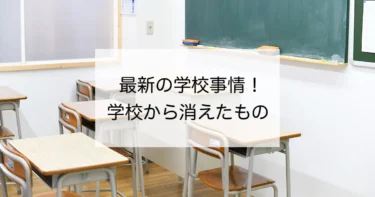教員が4月頃に行う大切な業務の1つに時間割の決定があります。
小学校の場合、時間割はクラス毎に決めることができるため、特別教室や運動場の空き状況などを元に教科をあてはめていくのが一般的です。また、中学校や高等学校では、時間割担当の先生が一元管理し、各教科の教員に伝達します。
では、時間割を決める際にどこにどの教科をあてはめるべきなのでしょうか。ここで重要なのが「授業時間数」です。
今回は、教員志望者や若手の教員に知っていて欲しい授業時間数の基本と各学校の授業時間数を決める根本「標準授業時数」について詳しく解説します。
ライター

emikyon
・元公立学校教員
・教育委員会にて勤務
・eduloライター歴2年
教科ごとに定められている時間数
学校で行う授業は、決められた時間数を実施しなければいけません。この「標準授業時数」は、教科ごとに学校教育法施行規則によって定められているものです。
例えば、小学校1年生の国語なら「年間306時間」、算数なら「年間136時間」(1時間は45分授業)と決まっています。
「時間配分が難しそう」「時間通りに授業ができるのか心配」と感じる方もいるかもしれませんが、心配はいりません。実は、各学年で使う教科書は、この標準授業時間で終わるように作成されており、教科書をもとに作られる教育課程も標準授業時数に当てはまるように作成されます。
小学校の担任教諭や中学校の時間割担当になった教諭は、この標準時数を満たすように授業計画を立てて時間割を作成しましょう。
「標準授業時間数」に達しない場合は?
万が一、「標準授業時間数」を大幅に越えてしまったり、逆に満たすことが出来なかったりする場合には、学期によって時間数の調整が必要です。
例えば、学校行事(運動会や水泳指導)に合わせて、一定期間に特定の教科を集中させ、他の週で調整などを行います。最終的に、学期末の段階で各教科の定めている標準授業時間を超えていることが大切です。
時間数を確認するための週案簿
この時間数の確認をする大切な書類が「週案簿」になります。
いつ、どんな授業を行ったのか記録する帳簿(学校管理運営規則や学校文書管理規定などで週案簿を公文書と明記しているところもあります)で、公文書と明記されていない場所では作成の義務はありませんが、週案簿を記録していないと何時間の授業を行ったのか、標準授業時数を満たしているのか証明するのが難しくなるので、基本的には作成しておいた方がよいです。
授業時数は少し多めに計算しよう!
時間割を設定際には、標準授業時間数とぴったり同じにしないようにしましょう。なぜなら、次のような不測の事態が発生する可能性があるからです
よくある不測の事態
・インフルエンザなどの流行性の病気によって学級閉鎖、学年閉鎖となる
・行事等で授業時間数を取られる
・台風や大雪などによる休校、短縮日程の可能性
このようなことを考慮して、まずは学校で年間の総時数を少し余裕をもって組みます。これは多くは教務主任の仕事になります。
学級担任は学校から示された年間の授業時間数に当てはまるように各教科の時間割を割り振ります。各教科ごとに「少し余裕時間数」を入れておけば、不測の事態が起きたときにも対応することができますよ。
ただし、「標準授業時間数」に関しては「絶対に越えなければ進級」できないというわけではありません。例えば、令和2年の新型コロナウィルス流行に伴う一斉休校や大災害(東日本大震災など)による長期休校が起きた際には、学習課程を一部次年度へ先送りすることによって「修了」したケースもあります。
曖昧な時数が多いため削減に着手する動き
昨今「働き方改革」が進められる中で、注目されているのが「余分時数」です。
前述したように、各学校では、不測の事態に備えて「余分時数」を事前に決め、教育課程に組み込んでいます。しかし、実際には「余分時数」を多めに見込んでいるため、小学校では低学年から6時間授業が増えるなど授業時間が長くなってしまったり、教員の研修時間や授業準備の時間を確保することが難しくなるケースもあります。
そこで、ここ最近では「余分時数」をできる限り削減し、年間の授業時間数そのものを削減しようとする動きもあります。余分時数には、教科ごとの時間数の他に、行事の時間、行事の準備にあてる時間が該当します。曖昧な時間をカットすることにより働き方改革の推進が期待されていますよ。
「授業時数特例校制度」によって学校ごとの特色が出せる
これまで、授業時間数は「学校教育法施行規則」によって全国一律に定められていましたが、「学校や地域の実態に照らし、より効果的な教育を実施するため」として新たに「授業時数特例校制度」が定められました。
各学年の年間の標準授業時数の総授業時数は確保することを条件は下記の通りです。
・各教科の1割を上限として教育課程の編成が可能
・別の授業時数に上乗せすることが可能
・年間授業時間数が35時間未満の下記教科は対象外
(小学校)特別の教科 道徳、外国語活動(第3,4学年)、特別活動
(中学校)音楽(第2,3学年)、美術(第2,3学年)、技術・家庭、特別の教科 道徳、特別活動
例えば、外国語教育を充実させるために、国語の授業時数を減らして外国語の授業時数を増やすことや、学力の基盤となる言語能力や情報活用能力、地域教材の取り扱いなどに教科を割り振ることが可能になります。
学習課程の変更は、私立学校ではよく見られるものの公立学校では法律上認められませんでしたが、特例校制度ができたことにより、公立学校でも学校の独自性を打ち出すことができるようになりました。経験の浅い先生が特例校に赴任になると、他の学校とは学習課程が大きく異なっているので心配になるかもしれませんが、その学校が独自性を出して、子どもの個性を伸ばしていきたいという教育方針のもとやっていることを理解しておきましょう。
1時間の授業時間も標準単位時間に収まれば柔軟に変更可能
実は1回の授業時間も「小学校45分、中学校50分」という形ではないケースが多くあります。
中学校で50分授業だった学校から45分授業や47分授業の学校に赴任するとついつい戸惑ってしまいますが、これらの短い授業時間数であっても「50分授業」に換算しなおすことで授業時間数を確保していることになります。小学校で40分、中学校で45分授業を実施しているような学校では、時間割上の授業時間コマ数は多くなります。ただし、実際に報告をする際には小学校45分、中学校50分に直して計算されているので、他の学校の教員と比較すると授業数が多いなと感じることになります。
このように授業時間は学校毎に調整をすることができ、最近は「カリキュラムマネジメント」という言葉が注目されるようになったことで、職員の働き方改革と併せて、児童生徒の時間を変更する措置も取られています。
授業時間数の最終決定者は校長 学校の独自性を出すことができるポイント
授業時数は、標準とするものが文部科学省から出されているものの、最終的に決定する権限は校長にあります。若い先生や経験の浅い先生は、標準時数として出されてくる時間を見て、そのまま組んでいるかもしれませんが、数少ない「学校の独自性」を出すことができるものの1つです。魅力ある学校づくりが求められていますが、時間割や教科において「魅力ある学校」を作り出すことができるということも知っておきましょう。
参考文献:標準授業時数について,文部科学省,https://www.mext.go.jp/content/20210629-mxt_kyoiku01-000016453_4.pdf,(参照 2025-2-6)