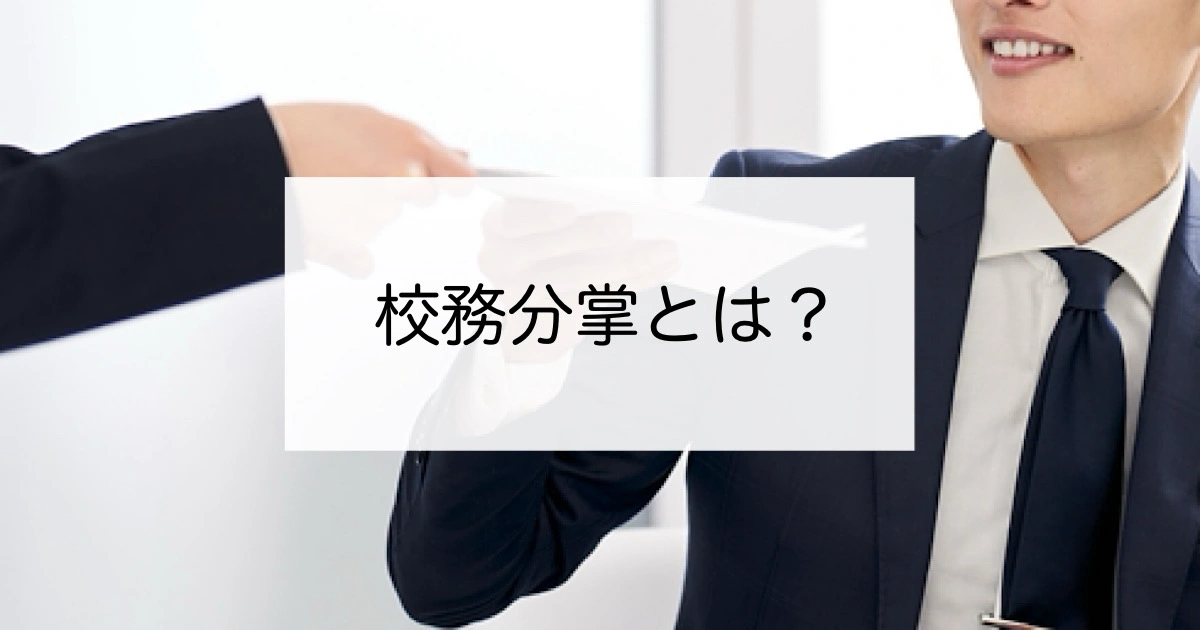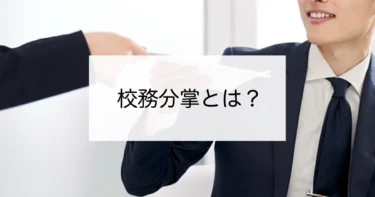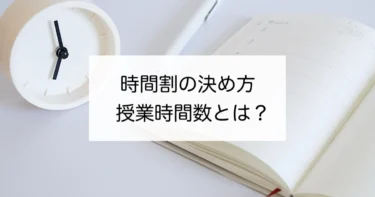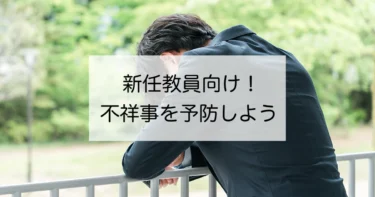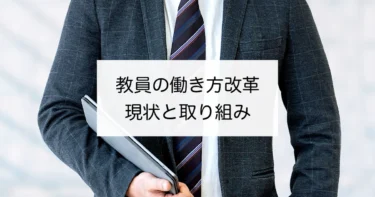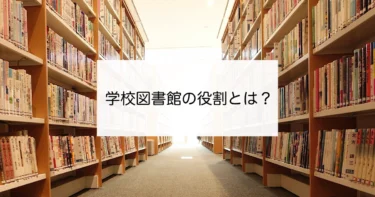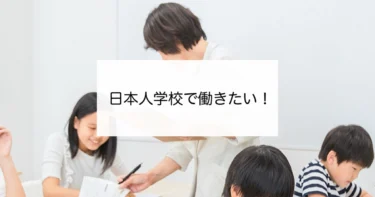新学期を迎える4月は、教員にとってわくわくする気持ちがある一方、忙しく不安を抱える時期でもあるでしょう。
この時期、特に気になるのは「校務分掌」だと思います。経験の浅い先生にとっては「校務分掌」と言われてもピンと来ないかもしれませんが、簡単に言えば、学校内での役割分担のことです。
例えば、下記のような物を指します。
・「主任」・・・教務主任や学年主任、生徒指導主事(主任)、進路指導主事(主任)など
・「教科主任」・・・国語主任や図書館主任、体育主任など
・「活動担当」・・・児童会主任、いじめ対策主任、不登校対策主任など
学校によって呼び方や役割は変わりますが、全ての教員に何らかの校務分掌が割り振られて新年度がスタートします。
若手の教員や異動してきたばかりの教員だけでなく、初めて担当する分掌が割り当てられた方も不安になるのは当然です。
何をするのか分からず不安に感じている教員のために、今回は新しい分掌が決まる4月にやっておきたい5つのことを紹介します。
ライター

emikyon
・元公立学校教員
・教育委員会にて勤務
・eduloライター歴2年
①過去の起案書類、提出書類の時期を確認しよう
分からないことがあるとすぐに前任者に確認をしてしまいがちですが、4月は忙しい時期のため何度も質問や確認を行ってしまうと前任者の仕事を止めてしまいます。
自身も何も知識のない状態で説明を聞いても理解しにくいため、「まずは自分で探してみる」ことを心がけましょう。これは学校現場だけでなく、社会人としても基本になります。
その際に参考になるものが以下の2つです。
・前年度の文書記録フォルダー
・前年度の発出した文章や校内で起案されている文書
なぜこの2つが参考になるかというと、まず、校内で起案される文書は行事予定や日程が大幅に変更されていなければ、起案される時期がおおよそ決まっているからです。いつ何が起案されているか、職員会議で議論されているのかは、前年度の職員会議の目次さえ読めば、おおよそ知ることができます。
次に行政(教育委員会から来る調査)に関しても毎年同じ時期に来るものがほとんどです。つまり、前年度のファイル確認して「いつ作成しているか」「いつ提出しているか」をつかむと先が見通しやすくなりますよ。
資料が日付の付いた順に整頓されていたり、提出日や提出先がファイル名に付いていたりすると分かりやすいのですが、前任者がそこまで配慮しているか分かりません。自分が作成するときには、引継ぎをされた人が分かりやすいようにファイル名を付けておくのもポイントです。
②前任者に確認する
昨年度の資料を見ても理解できなかった場合には、前任者に確認しましょう。
前述した通り、新年度は前任者も含めて非常に忙しい時期のため、特に若手の教員にとっては先輩に話を聞くというのはハードルの高い作業かもしれません。だからこそ、前任者に聞く前に自分でできる限りのことをやっておく、概要でもよいので情報をつかんでおくことが大切なのです。それにより、前任者に聞く際にもどこが分からないのか具体的に話を聞くことができます。具体的な話であれば先輩も短時間で答えることができます。
自分でイメージをつかんでおき、分からない部分をまとめて前任者に質問をする流れにしておくとスムーズに話を聞くことができますよ。
③学校のウェブページや過去の写真を見よう
若手の教員は、初めての校務分掌の仕事が割り振られても、どんなものなのかイメージができず不安になると思います。仮にイメージができたとしても「運動会」や「学習発表」のような大きな行事は、前任校と全く違うやり方だったということもよくある話です。
こんなときに参考になるのが下記の2つです。
・過去(前年)の行事写真
・学校ウェブページの内容
特に、「学校ウェブページ」は行事の内容ややったことも詳しく書かれており、しかも写真も掲載されているのでかなり参考になります。前年の資料を見る前(できれば校務分掌が決まったらすぐにでも)に過去の写真やウェブページに目を通しておきましょう。
④変更や廃止をする場合の流れを知っておこう
行事や役割によっては「前年踏襲」をすることができず、変更したり、廃止したりしなければいけないケースもあります。このとき、担当になったからその権限でいきなり廃止にすると表明したり、職員会議で話を出したりすることはルール違反です。そもそも職員会議は多数決などを取って議決をする場所ではありません。物事を変えていくことは大切ですが、変えるには必要な手順があります。経験のある教員は手順を知っているかもしれませんが若手や経験の少ない教員は、どうすればよいか分からないまま過ぎてしまうこともあります。
基本的な手順は、まず「校内起案」をします。これは、教務主任や校長などに担当者が直接話をして、これからの計画を提案する段階です。提案だけなので、考えを示す程度にしておきましょう。この段階で、実現不可能であったり、修正が必要であったりすると助言をもらうことができます。また、経験豊富な教員に聞くことで、この先のロードマップを示してもらうことができます。修正や廃止の案がある程度固まったら校内の「企画委員会」で提案を行います。企画で提案するときにはしっかりとした案に固めてあり、具体的な日程なども示す必要があります。地域や保護者を巻き込む場合には、地域との連携を話し合う協議会でも提案して賛同を得る必要があるかもしれません。こうやって、周囲を埋めてから「職員会議」での提案になります。
非常に手間がかかるのでめんどくさいと思うかもしれませんが、外堀をしっかりと埋めてから話をすすめないと思わぬところから反発を招く可能性があります。また、時間のかかる作業にもなりますので、計画の変更等を考えている場合には「早めの提案」をすることを意識しましょう。
○ポイント 校内起案→企画→職員会議の流れを理解しておこう
⑤横のつながりを知っておこう
分掌によっては1回の行事が終われば完了するものと長期的なプランを元に進めていかなければいけないものもあります。進路指導や学年主任、いじめ対策、現職教育といったものが長期的なものの代表格になるのではないでしょうか。
例えば、進路指導を例にとると中学校3年生4月の段階で1年後の入試を見据え、逆算的に準備をしていかなければいけません。夏休みまでにやること、冬休み前にすることなど1年間を見通して準備を進めていきましょう。また、子どもの実態や他の学校の状況など前年踏襲が難しい場合もあります。こんなときには、他校の同じ校務分掌との情報交換がとても大切になります。なかなか他校の教員と話をするのはハードルが高いかもしれませんが、それは他の学校の教員も同じです。横のつながりを大切にすることで、最新の情報を知ることができるだけでなく、お互いに手落ちがない確認して仕事を進めることができますよ
自分で動くことや流れを理解することが大切
新しい校務分掌が発表され、引継ぎをするときにはみんな不安です。その不安を解消していくためにも、まずは自分で動いてみましょう。そして、それでも分からなければ聞くというスタンスで行くのがよいです。過去の資料は、書類だけでなく写真や動画、ウェブサイトなど参考にするものがたくさんあります。こうしたものを見てイメージを作っていくことは大切です。また、自分の学校だけでなく周囲の学校の同じ分掌の人とのつながりも重要です。人間関係を広げる意味でも、幅広いつながりを「分掌」を通して作っていくことができるとよいですね。