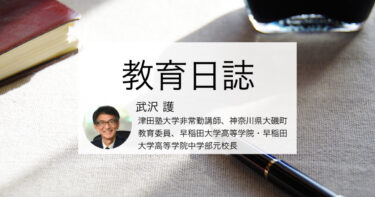こんにちは。千葉県の公立小学校で教員をしている山本裕貴です。前回は音読の手法についてお話ししました。今回は国語授業に焦点を当てていきたいと思います。
私自身、若手の教員から「国語授業は難しい」「どのように展開したらよいか分からない」といった意見を聞くことが多々あります。私も初任者の頃は、国語授業をするのがとても苦手でした。国語授業が難しいと言われている原因は何でしょうか。それは、国語は他の教科に比べて「何を身につけさせたらよいか分からない」からだと思われます。
例えば、6年生の算数「円の面積」では、円の面積の求め方を考え、面積の公式を理解し、面積を求めることを目的に授業を行います。
この目的を達成するために、円を分割した図を示したり、練習問題に取り組ませたりと達成するための手法が明確です。そして、身についたかどうかも問題を解くことでよく分かります。
一方、6年生の国語「あの坂をのぼれば」では、情景描写に着目し、主人公の心情を考えることを目的に授業を展開します。この目的を達成するためには、どのような手法がよいのでしょうか。悩んでしまいますよね。
このように国語は教科の特性上、身につけさせる力や手法、評価の方法が曖昧な側面があります。そのため、経験の浅い若手教員にとっては「国語授業は難しい」と感じるのでしょう。
国語授業では、どのような学力を身につけさせるかを教員が明確にしておくことが大切です。私の師である植草学園大学名誉教授の野口芳宏先生は、国語授業で身につけるべき国語学力を3つに分類しています。それは「読字力」「語彙力」「文脈力」です。
読字力とは「漢字を読むことができる力」のことです。漢字は書きよりも読みが先です。まず読めるようにならなければ、学力は形成できません。ですので、最も優先して教えるのは、漢字の読みです。
語彙力とは「言葉を知り、使うことができる力」のことです。言葉の意味を理解し、自分でも使うことができるようにすることが国語授業の大きな役割です。
文脈力とは「文章を論理的に読み取ることができる力」のことです。文章と文章とのつながりを整合し、正しく読解できることが国語の学力だと言えます。
私は野口先生の考えを踏まえ、国語授業では3つの国語学力を形成すべきだと考えています。それは「語彙力」「読解力」「作文力」です。それぞれの教材を通して、この3つの学力を身につけさせるのが国語授業の意義だと思います。では、この3つを養うためにはどのようなことをすればよいのでしょうか。
次回は引き続き、「語彙力を高める授業」についてお話ししたいと思います。ここまでお読みいただき、ありがとうございました。