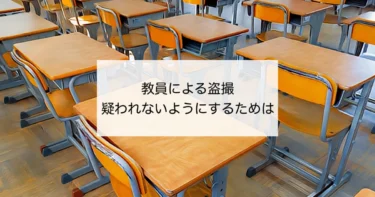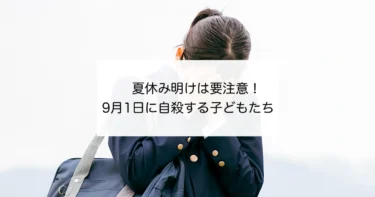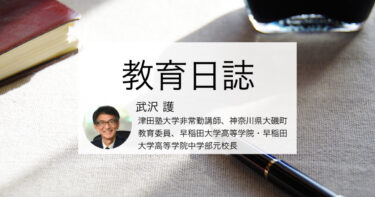こんにちは。千葉県の公立小学校で教員をしている山本裕貴です。
前回は国語授業で形成すべき国語学力についてお話ししました。私が考える国語学力とは「語彙力」「読解力」「作文力」です。
そして、この3つの中で、最も優先すべきものは「語彙力」と考えています。では、どのようにすれば子どもたちに語彙力が身に付くのでしょうか。今回は語彙力を高める国語授業についてご紹介します。
そもそも「語彙」とは何なのでしょうか。手元の辞書を引いてみましょう。そこには「ある人やある国が持っている単語の総体のこと」と書かれています。つまり、言葉ということですね。
さらに語彙力とは「どれだけ言葉を知っていて、どれだけ的確に使えるかどうかを示す能力のこと」とあります。
このことから、語彙力を高めるには「言葉を知っていること」「的確に使えること」が大切だと言えます。
そのため、私は以下の3点を意識して、国語授業を行っています。「①どんどん教える」「②じゃんじゃん調べさせる」「③がんがん使わせる」です。順番に説明していきます。
「①どんどん教える」とは、言葉の通りです。教員が、どんどん言葉を子どもたちに教えていくということです。私の師である野口芳宏先生は「語彙指導は、チャンスを生かすことだ」と仰っています。
例えば、あまんきみこの「白いぼうし」の冒頭に「お客のしんし」という言葉が出てきます。このとき「しんしというのは、礼儀正しい男の人のことです。【紳士】このように書くのですよ」「紳とは立派な人という意味です。また、士というのは男の人ということです」「士はさむらいとも読みます。だから武士という言葉もありますね」というように、子どもが言葉に出会ったチャンスを生かして、どんどん教えることが有効です。
次の「②じゃんじゃん調べさせる」とは、辞書引き活動を多く取り入れるということです。私は子どもたちの机の横に、常に辞書を袋に入れ、かけるように伝えています。すぐ辞書を引くことができるように、辞書カバーを外しておくのがポイントです。また、授業中はいつでも好きなタイミングで辞書を使って良いと言ってあります。
例えば授業中に「教科書には【夏みかん】と書いてありますが、みかんという漢字はあるのでしょうかね。誰か調べてくれますか」と教員が言います。すると、子どもたちはすぐに目を輝かせて辞書を引きます。こうした活動を短く、何度も取り入れることで、子どもたちの語彙力は高まっていきます。
最後の「③がんがん使わせる」も文字通りです。①、②は「言葉を知ること」を目的に行っています。しかし、それだけでは使えるようになりません。水泳も、実際に水に入らなければ、泳げるようにはなりませんよね。ですから、言葉を使う機会をたくさん用意してあげることが大切です。
例えば「紳士という言葉を使って、短作文を書きましょう」「調べた言葉を、友達と伝え合いましょう」などのアウトプットする活動を取り入れます。このような活動を通して、子どもたちは的確に言葉を使えるようになっていきますよ。
今回は「語彙力」についてお話しさせていただきました。次回は、「読解力を高める授業」についてお話ししたいと思います。ここまでお読みいただき、ありがとうございました。