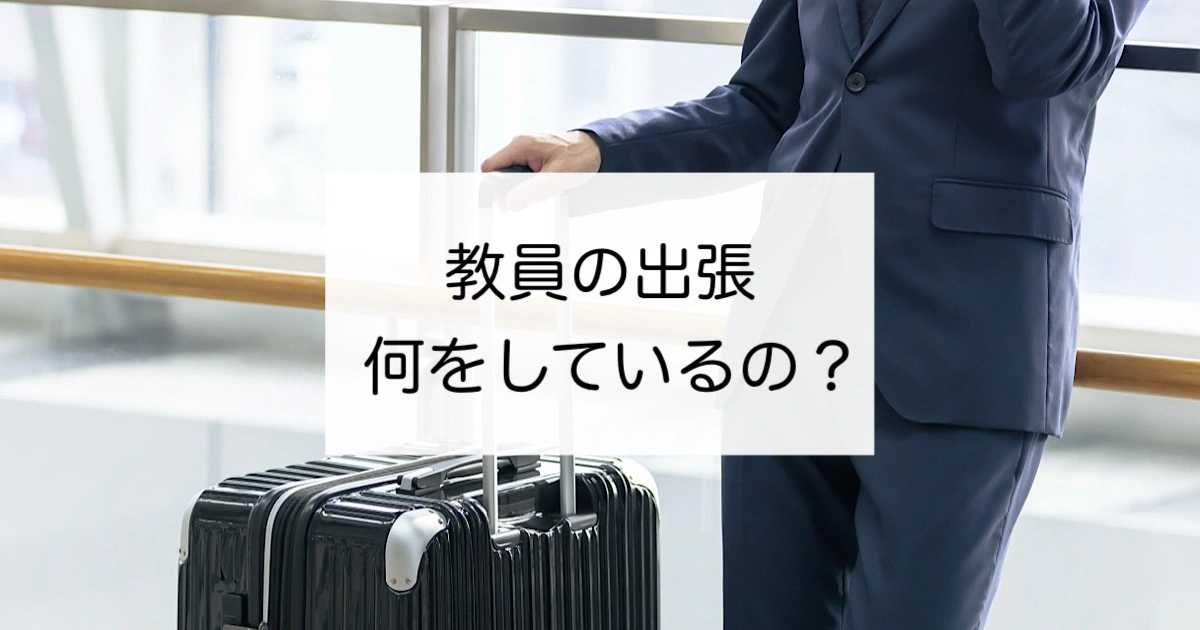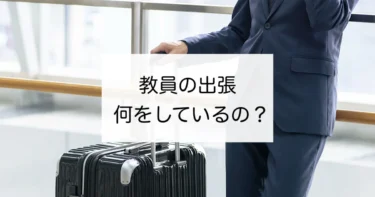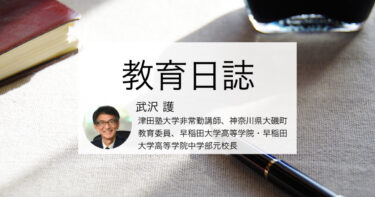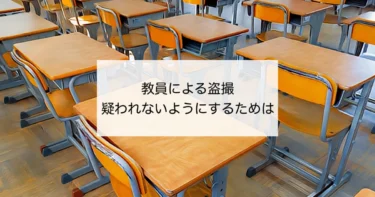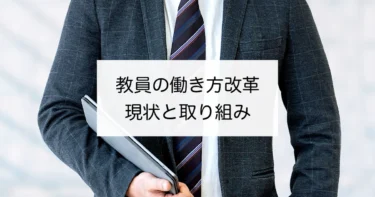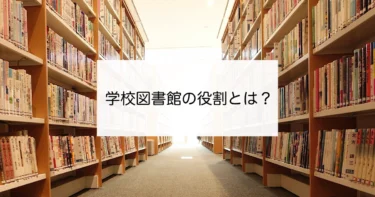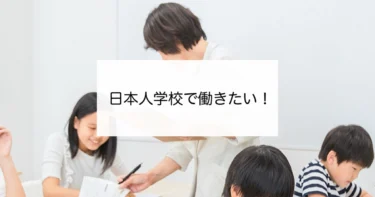教員にも出張があるのを知っていましたか。他の職業に比べ、教員の出張は少ないイメージがありますが、実は学校内で1日1人は出張があるほど教員の出張は多いのです。
日によっては出張が重なることで、担任以外の教員、管理職までが教室に担任代理として入ることもあります。役職や季節によっては、毎日のように出張で出ていくケースも多いのです。今回は、教員の出張事情についてご紹介します。
ライター

emikyon
・元公立学校教員
・教育委員会にて勤務
・eduloライター歴3年
出張の多くは研修
教員の出張の多くは「研修」です。例えば、初任者であれば「初任者研修」、中堅教員であれば「中堅教諭資質向上研修」といった法律で定められた研修を受講するために出張として研修場所に行っています。
他にも教科指導者としての力量向上、特別支援教育や特別支援教育コーディネーターとしてのスキルアップなど、様々な研修が用意されています。
教員の中でも役職によって求められる仕事のスキルが変わります。新しい役職になれば、その職の専門的な知識を学ぶ研修があると覚えておきましょう。
こうした研修の多くは、学ぶのに時間が必要です。担任の先生は、なかなか時間をとることが難しいので、担任が受けるとよい研修は夏休み期間に実施される傾向があります。「学校の先生は夏休みは暇」と思われがちですが、強制的に受けなければいけない研修も数多くあり、夏休みの期間の多くを勉強にあてています。
同じ役職同士での情報交換会
校長や教頭、教務主任など学校には「一人職」と呼ばれる役職があります。養護教諭や栄養教諭も同様のものになります。こうした立場の方は、一人職として専門的な見識から指導やアドバイスをしますが、困ったときに相談相手が校内にいないという悩みもあります。
そこで、他の学校の教員と横のつながりを作ることを目的として、同じ役職同士が集まって話し合いをしたり、その職に必要なことを学んだりする研修会が実施されています。同じ職の人同士だからこそ、困りごとを相談して解決することができますし、教育委員会の指導的な立場から見ると、文部科学省からの重要な通知や自治体としてお知らせしなければいけないことを一気に伝えることができるというメリットがあります。
校長や教頭といった重要なポストの人に対しては毎月のように「会議」が設定されており、教育委員会と現場が統一して物事を進めることができるようになっています。仕事の内容によっては横のつながりがないと進められないことも多く、同じ役職同士で集まるのは重要な場となっています。
地域の学校間での情報交換会
最近、学校で増えている出張が「地域向けの出張」です。コミュニティスクール(学校運営協議会制度)が推進され、同じ地域の学校、同じ中学校区内の学校などの単位で定期的に集まることが増えています。
会議の内容は、校区内で統一する項目(学習マナーや学校イベントの調整など)の検討、地域連携で実施する行事の打ち合わせなどをしています。
こうした会議に参加するのは管理職が一番多く、保護者の代表としてPTA会長が呼ばれるケースもあります。一般教諭からするとあまり関係ない会議のように見えますが、学校の現状を話し地域のサポートを得るためには大切な会議になります。
教員の代表としてカリキュラムや教科書、補助教材の作成
経験の少ない教員は、まだこの立場にはならないと思いますが、10年目を過ぎたような中堅教員の立場になってくると自治体全体の指導的な立場を担う仕事を任されることもあります。
例えば、学習カリキュラムは地域の実情に合わせて使用している教科書、補助教材を用いて、学習指導要領の内容を網羅できるように変更できます。文部科学省の示す学習指導要領に沿いながら独自のカリキュラム作成を担うのが、その地域で指導している教員の代表です。経験豊富、または教科指導に長けている人物を各校から選抜して独自のカリキュラムを作る編成会議のようなことが行われます。
他にも、地域教材の作成、ICT機器で利用できる補助教材も各校で作っていると負担が大きいので、代表者で作成し、各校に配付して利用できるようになっています。
少し変わったところでは、教科書の作成にも教員が関わっています。教科書の最終ページの編集者を見ると何人か現職教員の名前が入っていることが分かりますよ。
彼らも教科書会社から依頼を受けて選抜され、教科書の作成に関わります。この場合には、教科書会社から謝金が発生するため「副業申請」をきちんと行い、許可を得たうえで仕事をして報酬を得ています。
行事の下見や準備のために打ち合わせ
若手の教員でもよく経験する出張は「下見」です。教員は、校外学習やキャンプ、修学旅行を実施する前に、道中が安全か、現地では何ができるのかといったことを確認しています。また、必要に応じて現地の人との打ち合わせもしなければいけません。
修学旅行などの校外学習では、事前に所属する教育委員会に申請書を提出する必要があり、その際には、緊急避難先や現地での緊急医療機関なども記載した上で提出しなければいけません。行きなれた場所であれば、事前に下調べをすることも少ないですが、新しい場所に行くときには調べることがたくさんあります。大げさに聞こえるかもしれませんが、道中どこで休憩するのかも大切で、多人数の学年であれば停車するサービスエリアを変えないとトイレ休憩の時間が非常に長くなる可能性もあります。修学旅行の集合場所も、そのときにどれだけの学校がやってくるのか、いつやってくるのかといった細かいところまで計算して下見をしないと、当日人が多すぎてパニック状態になってしまうこともあります。最悪の事態を想定しながら下見をしてくることはとても大切です。
大切スキルアップや情報交換の場
教員の出張は、一般企業の出張と異なり、他の仕事の人と一緒に活動したり、何かをプレゼンテーションして売り込んだりすることはありません。その代わり、学校では接することができない他校の教員とのコミュニケーションや、自分のスキルアップのために学びに行くということが多いです。
近年はオンラインでの出張も増え、自校にいながら他の学校の教員とつながる機会も多くなりましが、教員の出張は円滑な学校運営をしていくうえでとても大切なことです。役職に応じてさまざまな立場として学校外に出ていくことになるので教員の出張について知っておきましょう。
参考文献:コミュニティ・スクール(学校運営協議会制度),文部科学省,https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/community/index.htm(2025-6-19)