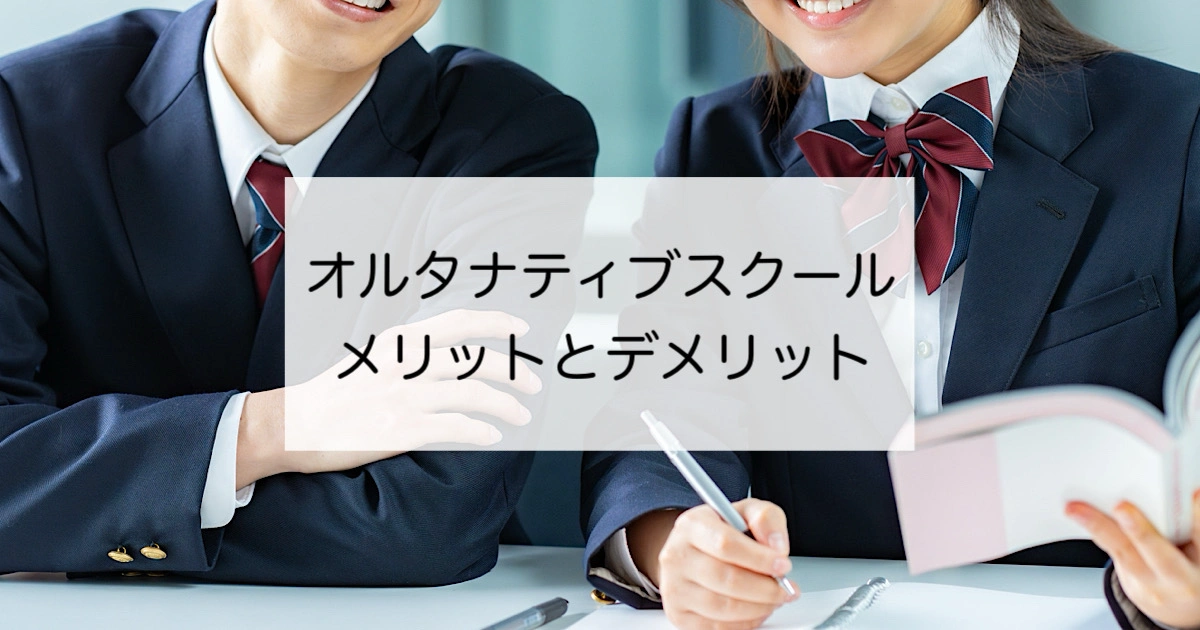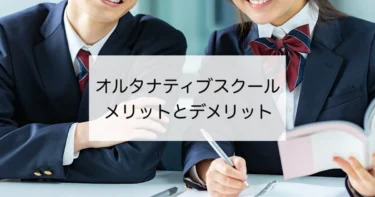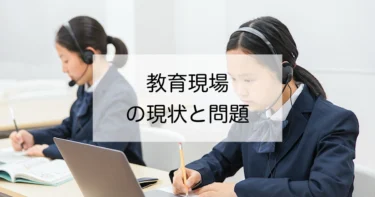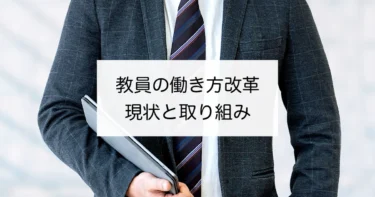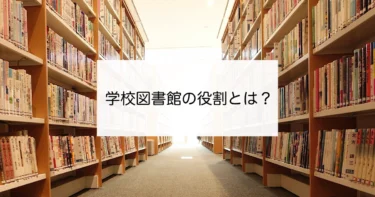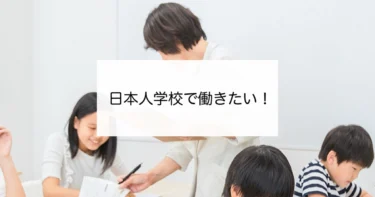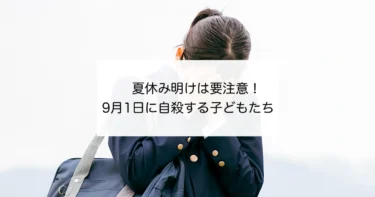「オルタナティブスクール」という言葉を聞いたことはありますか。近年話題となり、「第3の学校」と評されるオルタナティブスクールには、多くの魅了があるものの安易に勧められない事情もあります。今回は、多様化する子どもたちのために知っておいてほしい「オルタナティブスクール」について詳しく解説していきます。
ライター

emikyon
・元公立学校教員
・教育委員会にて勤務
・eduloライター歴2年
オルタナティブスクールとは?
オルタナティブスクールは、アメリカやヨーロッパの哲学的思想をベースに発展した「オルタナティブ教育」を取り入れている学校のことを指します。
「オルタナティブ(alternative)」という言葉には「主流に変わる新しいもの」という意味合いがあり、「学校」や「フリースクール」と違うは異なる「新しい選択肢の学校」として注目されています。
なぜオルタナティブスクールが必要なの?
近年、オルタナティブスクールが注目されるようになったきっかけには、「不登校の増加」が関係していると言われています。小中学校の不登校児童生徒数は、11年連続で増加し、34万人を超えました。不登校の理由は人間関係に起因するものだけでなく、学習環境になじめない、一斉指導についていくことができないといった理由もあります。
そういった理由から学校に通うことができない子どもが主体的に学ぶことができる場として、フリースクールや学習支援センターやオルタナティブスクールの需要が高まっています。
オルタナティブスクールの特徴と種類
オルタナティブスクールは、指導要領や運営体制が規定されている公教育とは異なり、そのスクールの方針や教育理念を元に運営されています。
シュタイナー教育やモンテッソーリ教育、サドベリーバレー教育などアメリカやヨーロッパの哲学的思想を元にした教育理念や自由進度学習を取り入れており、公教育と比べると特化型の教育に視点を置いていることが、一般的な学校との大きな違いです。
オルタナティブスクールのメリット
オルタナティブスクールの魅力は、子どもの個性が尊重され、主体的に学べることです。公教育では、一定の学力水準を均等に満たすことができるように指導されるため、どうしても「教え込み」や「一斉授業」といった方法になりがちです。これは高校入試や大学入試といった「入試」に対応するためでもあり、個性を尊重する授業や学びをしなければいけないことを教員も分かっていながらなかなかできない現実があります。
一方、オルタナティブスクールでは、学びの方向を自分や保護者と一緒に決めて進むことができるため、一斉指導を聞くことが苦手、集団で学ぶことが苦手という発達特性をもつ子どもにとっては学びやすい環境と言われています。
また、個性を尊重するような学びができるため、子どもにとって安心感があり、その子どもにあった心の成長ができるというメリットがあります。
さらに、一般的な学校ではできない特別な体験活動や留学、スポーツに特化した学び方など、保護者と子どもがやりたいという勉強を自由にすることができます。
オルタナティブスクールの課題
ここまでオルタナティブスクールの魅力をお伝えしてきました。「発達特性がある子や受け持っている不登校の子どもに紹介するとよいのでは?」とすぐに思ったあなたはとても優秀な教員です。こんな学校があれば、何かの役に立ちそうだと思うのは教員の性ですよね。しかし、焦りは禁物です。子どもたちや保護者にすすめる前に現在のオルタナティブスクールが抱えている課題や問題点を把握しておきましょう。
出欠の判断
オルタナティブスクールの抱える問題の1つ目は、「出席扱いにできるのかは在籍校の学校長判断になる」という点です。オルタナティブスクールは、学校教育法で定められた「認可校」が少なく、認可校以外では通っていても不登校と同じ扱いになります。
認可校以外には転校手続きができず、あくまで現籍校に籍を置いたまま通うことになるため、義務教育段階では、オルタナティブスクールに通った日数を「出席」と認めるかどうかは、在籍校の校長が判断することになります。「出欠の判断」について、通うことを検討している子ども、保護者、そして学校長と事前に確認しておく必要があります。
学費以外にも費用がかかる
2つ目が費用面の問題です。公立で運営されているオルタナティブスクールの数は非常に少なく、多くが私立で運営されています。また、学校数も少ないので、学費の他に通学に関わる費用もかかります。いろいろな面で保護者負担が増えることを保護者自身に納得してもらったうえで選択してもらう必要があります。
行政がどこまで認可していくのかが今後のポイント
不登校児童生徒が増加する中で知名度が高まっているオルタナティブスクールですが、今後も需要は増加すると見込まれています。課題は行政の支援で今はまだ半分ボランティアで運営されていたり、NPO団体が運営していたりと資金面や人材確保の問題があります。行政も不登校支援策として「教育支援センター」や「サポートルーム」といった対策を打ち出しており、これらとオルタナティブスクールを同時に展開していくにはお金も人も足りない状態です。
また、学校教育法との適合も課題になります。現状のルールではオルタナティブスクールは「学校」として認められておらず通っても「不登校」の扱いをされてしまいます。義務教育であれば、出席日数が0であっても卒業することは可能ですが、高等教育では卒業要件を満たすことができません。また、義務教育を卒業することができても出席日数の数字で高校入試が不利になってしまいます。こうした課題を1つ1つ乗り越えていく方策を打ち出すことが行政には求められるようになります。
オルタナティブスクールよって救われる子どもはたくさんいる
オルタナティブスクールがこれだけ注目されるようになってきたのは、現行の公教育制度に合わない子どもたちも学びたいという気持ちを受け入れてくれる学校だからです。自宅にいてはなかなか経験することができない学校生活をさまざまな形で実現することができるオルタナティブスクールを使うことによって助かる子どもたちがたくさんいます。
保護者の方々や子どもたちにオルタナティブスクールをすすめる場合には、具体的なアドバイスができるようにするためにもオルタナティブスクールの特徴やメリット・デメリットを知っておきましょう。
参考文献:令和5年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果及びこれを踏まえた対応の充実について(通知),文部科学省,https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1422178_00005.htm#:~:text=%E4%BB%8A%E5%9B%9E%E3%81%AE%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%84%E3%81%A6%E3%80%81%E4%BB%A4,%E6%98%8E%E3%82%89%E3%81%8B%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82 ,(参照 2025-1-8)
参考文献:オルタナティブ・スクール あいち惟の森,https://www.yuinomori.org/,(参照 2025-1-8)
参考文献:箕面こどもの森学園,https://cokreono-mori.com/kodomonomori/index.html,(参照 2025-1-8)