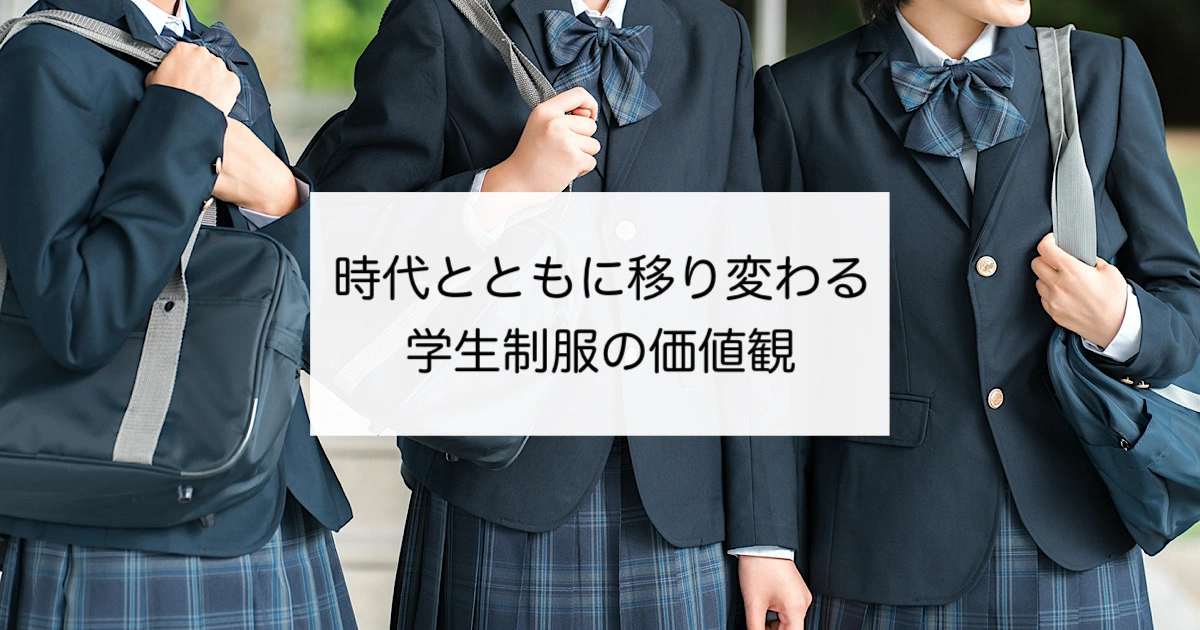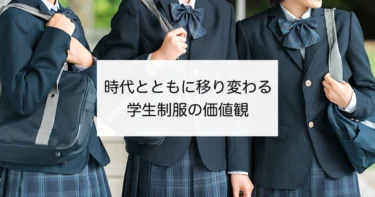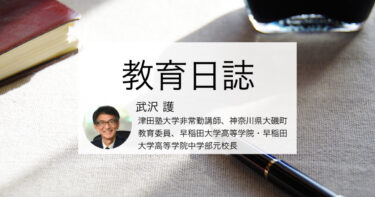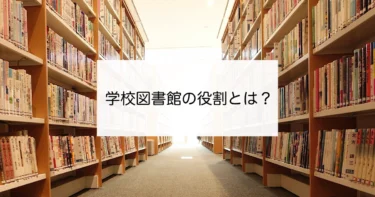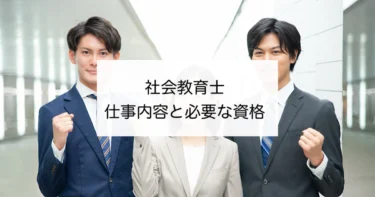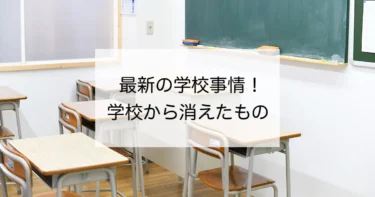中学・高校の制服と聞くと、みなさんはどのようなイメージを持ちますか。3、40代の方であれば、どこの学校でも似たようなデザインが多く制服のデザインを理由に進学先を決めたり、あえて校則から少し外れたような制服の着方をしていた方もいるのではないでしょうか。
近年、そんな制服のイメージも大きく変わりつつあります。学校制服に大きな影響を与えているの制服のジェンダーレス化です。これまでの「みんなが一緒」「性別によって着るものが決まる」という古い考え方は変わり、一人ひとりの個性が重視される時代となりました。今回は、ジェンダーレス制服や学校制服を取り囲む事情を紹介します。
ライター

emikyon
・元公立学校教員
・教育委員会にて勤務
・eduloライター歴3年
ジェンダーレスを意識した制服づくり
最近の「制服デザイン」の中心的な考え方は「ジェンダーレス」です。「LGBTQ+」が注目されるようになり、それまでの男子・女子という制服の分け方から、性別に関係なく自由に着ることができる制服が登場しました。女子がスラックスを履くなどといった、男女の区別がない制服が登場しています。
その他にもジェンダーレスを意識した制服には下記のような種類があります
・前合わせを左右自在に変えることができるジャケット
・シルエットが強調されないスラックス
・スカート、スラックス、ネクタイ、リボンを自由に組み合わせる
など
ジェンダーレスの制服は、主に高等学校での導入が進んでおり、公立高校でもおよそ3割が導入しています。導入を検討している学校も多く、高校だけでなく中学校にもその流れは広がっています。生徒の多様な個性を尊重し、より快適な学校生活を送るために日々進化しています。
町をあげての新しい制服・学校プロジェクト
学校制服の変化は、教員だけでなく、子どもたちや保護者にとっても大きなことです。特に歴史や伝統と紐づいている学校や地域では、制服のデザインを簡単に変えることが難しいと言われています。
そこで、制服の変更を1つの巨大プロジェクトとして自治体や企業、保護者、子どもを巻き込んで行っているところもあります。例えば、愛知県一宮市では「みんなの制服プロジェクト委員会」を立ち上げ、保護者や生徒の意見を聞くだけでなく、地場産業の協力も得ながら新しい制服を作り上げました。このような取り組みは、一宮市以外にも行われており、新しい制服を地域の魅力として打ち出しているところもあります。
これまで、私立学校では独自の戦略を打ち出しやすいことから「制服を魅力」とした学校づくりをすることがありましたが、公立学校でもだんだんと広がりを見せています。
校則を見直して今の時代に合った制服や登校の姿づくり
制服の見直しと同時に「ジェンダーレス」の視点から学校の設備や校則を見直す動きもあります。
例えば
・頭髪に関する規定の見直し
「男子の髪型の指定」や「女子の髪の長さが一定を超えたらまとめなければいけない」といった性別によって髪型に対する規定をしていたものを見直す動き
・下着や防寒着の規定の見直し
下着の色指定や防寒着についても男女で使うものを指定するのではなく、生徒の健康の快適性を重視したものに見直す動き
・生徒の呼称や名簿の統一
児童や生徒の呼び方も「~くん」「~さん」のように男女で区別するのではなく「~さ ん」で統一したり、出席名簿も男女で分かるのではなく、男女混合で五十音順にする
こうした取り組みにより子どもたちを取り巻く環境も大きく変化しています。
一方、合唱などでは男女で分けないと能力上、混声合唱をすることができません。卒業式などの式典で名前を呼ばれるときは、男女混合で番号順に呼ばれ、並びも男女混合です。このままでは合唱をすることができないので、式典の最中に席替えをするケースもあります。「男女の差がなく」という方針が増えたことで、これまで教員が考えなくても当たり前の光景が「不可能」となり、新しい対応策を立てないといけないケースもあります。
高等学校では制服を廃止・持ち物の規制も緩和
近年、中学校、高等学校において、制服制度の見直しをする動きも広がっています。例えば、「制服を廃止」し、私服での登校に切り替えている学校があります。服装は自由になり、制服を購入する費用も掛からないメリットがある一方、私服での登校のほうがお金がかかるという保護者の意見もあります。
また、学校に持っていく持ち物についても自由化する動きが広がっています。
例えば
・日傘を利用して登校してもよい
・日焼け止めやハンディクーラーの使用や化粧の許可
・スマートフォンの校内への持ち込み可
など
かつては、学校に不要なもの、学習に関係のないものは持ってこないという校則が多くの学校で一般的でした。しかし最近は、気候や環境に合わせ、子どもの安全や安心を最優先に考えてるように変化しています。
メリットとデメリットがある服装の自由化
中学校や高等学校において「服装の自由化」を求める声はよくあがります。
① 自分の好きな服を着ることによる個性の尊重と自己表現の促進
② 個性や自己表現が促進されることによる自己肯定感の高まり
③ 体調や気候に合わせて服を選ぶことができることによる快適性の向上
④ 自分で服装を考えることができるということによる主体性の育成
など、服装の自由化を求める人は、このようなメリットを主張しています。
その一方で
① 私服になると家庭の経済状況が顕著化することによる格差の発生
② 自由化してもある程度の制約(企業ロゴの禁止や露出の多い服装の制限など)を設けることに対する教員への負担
③ 自由な服を着ることによる学校の一体感の希薄化
④ 学校にふさわしくない服装をする生徒が増えることによる風紀の乱れへの懸念
など、こうしたことをデメリットとしてあげる人もいます。
このようなどちらがよいとも取りにくい議論となってしまうため、制服の自由化はなかなか進んでいません。教職員も「指導のしやすさ」を考えて、制服のほうが楽であるという意見が多くなっています。
「統一」よりも「個性」を重視
かつて、制服は学生の象徴的な意味合いがあり、見た目のカッコよさや可愛さにあこがれて進路選択をした人も多くいました。しかし、近年では見た目や統一性よりも機能性が重視されるようになり、制服の姿も変わってきました。また、制服を決める際にも、教員が中心となってデザインを決めるのではなく、学校に通う生徒や保護者、地域の人たちなど様々な人たちの意見を取り入れて「オリジナル性があり、かつみんなから支持される制服づくり」を行うところが増えています。
参考文献:愛知県一宮市「みんなの制服プロジェクト」委員会 実施報告書,https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/060/162/hokoku1.pdf,一宮市教育委員会,(2025-7-7)