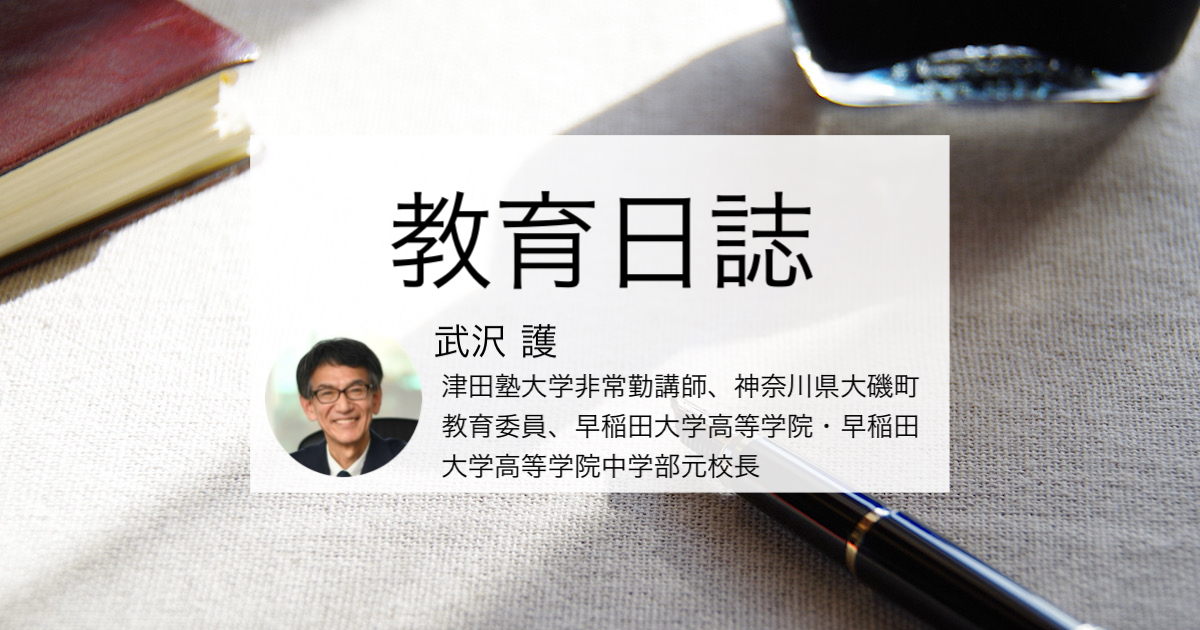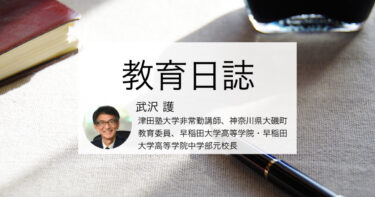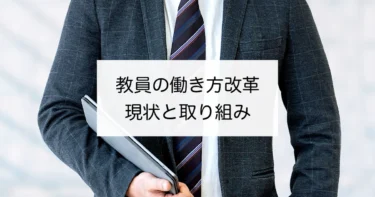今回から2回にわたって、私のかつての勤務校での経験を踏まえながら、戦後の高校教育について考えていきます。
現在、高校教育に関わる話題としては、「高校授業料無償化」や、2030年度から始まる次期学習指導要領における「教育課程の多様化」などが挙げられます。第2回でもお話ししたように、戦後の高校教育は「小学区制」「総合制」「男女共学」という高校三原則からスタートしました。
今回はその中の「総合制」に焦点を当ててお話しします。
この「総合制」は同一学校の中に普通科と専門学科(商業、工業、農業など)という多様な課程・学科を併設し、生徒の全人的な発達を目的としたものでした。
ところが、この制度も後年、形を変えます。普通科と専門学科とで別々の学校へと実質的に再編されていったのです。かつて各都道府県の公立学校には普通科と専門学科(商業科、工業科、農業科)が併設されていましたが、ある時期から専門学科を廃止し、普通科のみになる学校が大幅に増えました。このことは、さまざまな学校のWebサイトなどでその歴史を確認できます。
その後、1960年代は60%だった高校進学率が、1970年代になると90%を超えるようになり、高校教育は事実上、準義務教育となっていきます。私が最初に勤務した神奈川県では、都市部を中心とした学齢人口の増加に対応するため、「百校計画」なるものが1973年から1987年まで実施され、実際に100校が増設されました。しかも100校の内訳は99校が全日制普通科で、工業高校は1校のみでした。こうして、多くの高校生が普通科教育を受けることになったのです。しかし、その一方で課題集中校の問題や学習意欲を持たない生徒の増加など、高校教育の課題は噴出しました。
このような状況を踏まえ、高校教育の改革として文部科学省は1994年度から「総合学科」(多くの学校は単位制)という課程を導入しました。これは「普通科」と「専門学科」の中間的な位置づけとした課程で、「産業社会と人間」という科目を必修とし、大学進学だけでない生徒の多様な進路に対応できるコースを設けていきます。神奈川県でもいくつか「総合学科」を持つ高校が設置されましたが、なかなか運用が大変なようでした。
そして21世紀になってから少子化を迎え、学齢人口の減少から、全国の多くの公立高校は再編・統合化へと進んでいきます。さらに、大都市圏では受験生の私学志向が増加し、公教育としての高校教育は「公立」と「私学」がどのように役割を分担するかも大きな課題となってきました。
次回はもう少し具体的に高校教育の改革について考えます。