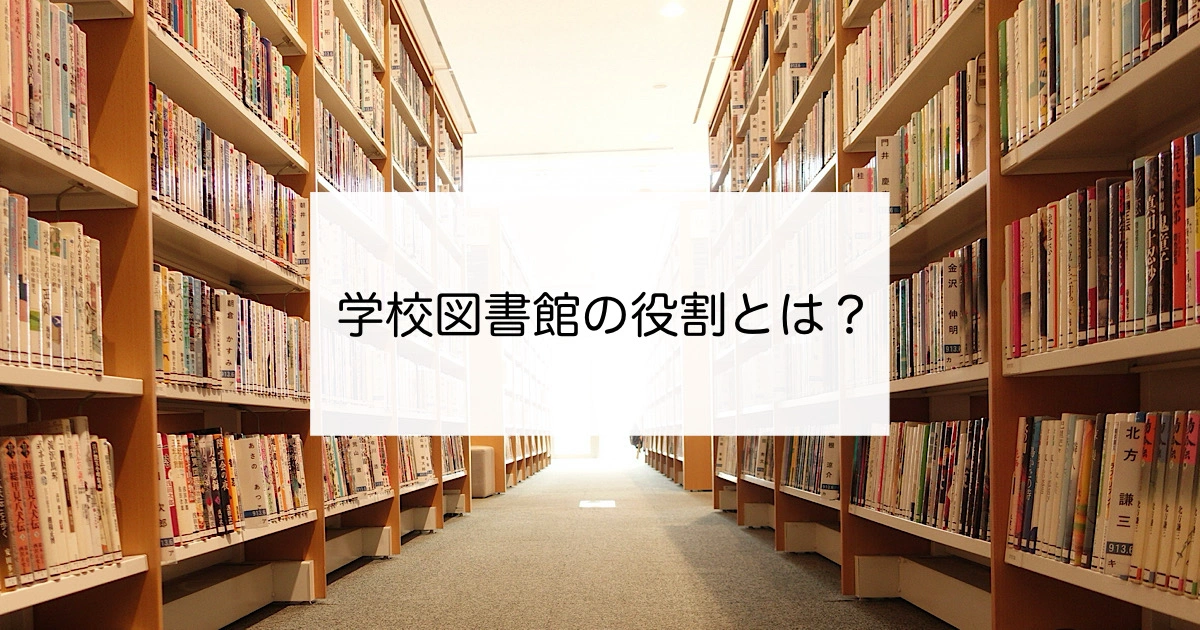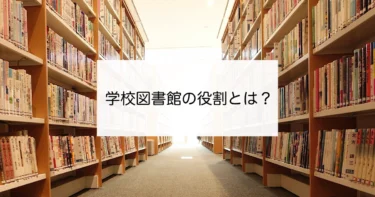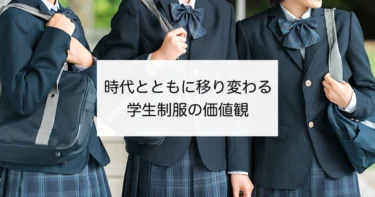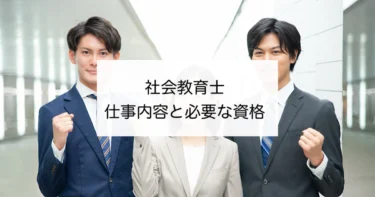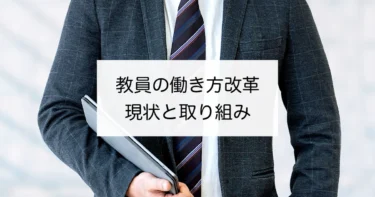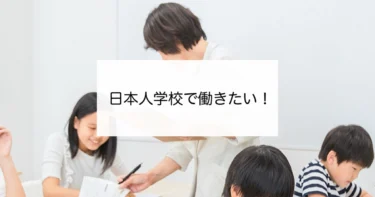学校にある図書館の目的や役割について考えたことはありますか。単に「本を借りる場所」だと思っていませんでしたか。
学校図書館は、「学校図書館法」という法律に基づいて設置されており、すべての学校(小・中・高等学校、中等教育学校、特別支援学校)に置かなければならないものとされています。このことからもとても重要な役割を担っていることが分かりますね。
司書教諭の免許を持っている教員でなくても、図書館担当になることもあります。学級運営をしていく中でも図書館の活用は重要なポイントになります。
今回は、新任の図書館担当教員や図書館の役割を詳しく知りたいという教員に向けて、学校図書館の役割を解説します。
ライター

emikyon
・元公立学校教員
・教育委員会にて勤務
・eduloライター歴3年
学校図書館の目的とは?
学校図書館法において、設置の目的として以下の2つが挙げられています。
教育課程への寄与
授業内容を深く学び、調べ学習を行うための資料や情報を提供することで、日々の学習活動を支える
児童・生徒の健全な教養を育成
読書を通じて、豊かな心や想像力、多様な価値観を育む
その他にも学校図書館法では「司書教諭の配置(12学級以上の学校では司書教諭を置かなければならない)」や「学校司書の配置(努力目標として)」などが定められています。
学校図書館の役割について
学校図書館の役割は、単に本を貸し出す場所ではなく、学校教育全体を支えるための重要な教育施設です。その役割は、主に以下の3つのセンター機能に集約されます。
①読書センターとしての役割
学校図書館の最も基本的な役割です。読書の楽しさを伝えるために、多様なジャンルの本を揃え、読書イベントなどを通して、子どもたちが自発的に本を手に取るきっかけを作ります。また、豊かな心を育むために、物語や伝記など、様々な本との出会いを通じて、子どもたちの想像力や共感力を養います。そのために次のようなことをよくします。
1.自由な読書活動の推進
児童・生徒が自分の興味や関心に応じて自由に本を選べるよう、多様なジャンルやレベルの図書資料を整備します。
2.読書指導
読み聞かせやブックトーク、お薦めの本の紹介など、様々な手法を用いて、読書への関心を喚起します。
3.心の居場所の提供
休み時間などに静かに過ごせる場所、一人で落ち着いて考え事をしたり、友人と本につ いて語り合ったりできる「心の居場所」としての機能も担います。
読書(読む)習慣は、すべての学習の基礎となります。休み時間や朝の読書などを通して、日常的に本に触れる機会を提供するのが学校図書館の1つ目の役割です。
②学習センターとしての役割
学校図書館は、授業の学びをサポートし、探究学習の基盤を担う役割もあります。総合的な学習や社会などの調べ学習において図書館を利用する授業がこれに該当します。
1.授業の支援
教科書の内容をより深く理解するための関連資料や、テーマ学習、総合的な学習の時間で使う情報を提供します。学校図書館は、それぞれの分野を詳しく解説している書籍を用意しなければいけないだけでなく、常に最新の情報を子どもたちに提供することができるように資料類の本については定期的な入れ替えが必要になります。
2.情報活用能力の育成
必要な情報を効率的に探し、適切に利用する方法を指導します。現在ではインターネットが普及し、生成AIが登場するなど、ICT端末を利用すれば簡単に情報を手に入れることができるようになりました。一方で、インターネット上の情報と図書館の蔵書を比較検討するなど、複数の情報から正しい情報を見つけていくという情報リテラシーを育む場としても活用されています。
3.探究学習の拠点
課題解決学習や探究活動を行う際、様々な資料や文献を探すための中心的な場所となります。もちろんインターネット上の情報も使うことができますが、できるだけ多くの情報から興味関心のある所を見つけることができます。また、ネット上の情報は、非常に細かく書かれている一方で、言葉が難しく、使われている漢字も大人でなければ読めない字を使っていることも多いです。図書館の本は、子どもの発達段階に応じた表現や言葉が使われているので、低学年の児童にとっては、インターネットで情報を探すよりも本を利用したほうが、情報を探しやすい傾向があります。
③情報センターとしての役割
あまり知られていませんが、学校内外の情報をつなぐハブとしての機能も学校図書館にはあります。最近はオンラインのメリットを生かして、学校図書館にはない本を地域の図書館にあるかどうか探すシステムや学校図書館と公立図書館の貸し出しカードを統一化することにより、簡単に本を借りることができるシステムを導入しているところもあります。
1.最新情報の提供
図書だけでなく、新聞、雑誌、オンラインデータベースなど、多様なメディアを通じて最新の情報に触れる機会を提供します。学校図書館のデメリットとしてスペースが限られているため、最新の蔵書を手に入れにくかったり、雑誌類などを置いていなかったりします。そこで最新の情報については、地域の図書館にあることを示し、情報だけは学校から検索することができるようにしています。
2.図書館ネットワークの活用
最新の情報と重なる部分がありますが、公立図書館や大学図書館と連携し、学校にない資料を取り寄せられるようにします。これは、どちらかというと子ども向けというよりも教職員向けになります。教材として使う資料や教員向けの専門書などを取り寄せることができる場所もあります。
3.情報の整理と提供
信頼性の高い情報を体系的に整理し、利用者が目的の情報にスムーズにたどり着けるようサポートします。学校図書館や地域の図書館には膨大な数の蔵書があります。この蔵書の中から自分の必要な本を探したり、複数の関係する文献から自分の必要なものを見つけ出したりするのはとても大切な学習です。
図書館では蔵書が統一の指標に従って系統的に分類されており、だれもが本を探しやすい状態になっています。この統計的に整理や整理すること、整理されたものから情報を見つけることは、生きる力を育むうえで大切な知識になります。
ICT化が進んだ後の学校図書館
ICT化が進み始めたときに、今後の学校図書館の在り方が問われました。一部の人からは廃止すべきという意見もあがりましたが、ICTよりも簡単に情報を手に入れることができる、速報性はないものの確実性が高いといった理由で今でも学校の重要な設備になっています。
また、先ほど紹介した「情報センター」としての役割が近年重視されるようになり、より本を身近に、手軽に貸し借り、検索ができるようなシステムが導入されました。
現在、学校図書館の運営にかかわっている教員の皆さんがこの記事を読まれていたら、ぜひ、先ほど挙げた「3つの役割」を意識して、図書館づくりを進めてみてください。
参考文献:学校図書館法,https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000185/,(参照 2025-8-8)
参考文献:「学校図書館図書標準」の設定について,国立国会図書館ホームページ,https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11402417/www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/t19930329001/t19930329001.html,(参照 2025-8-8)