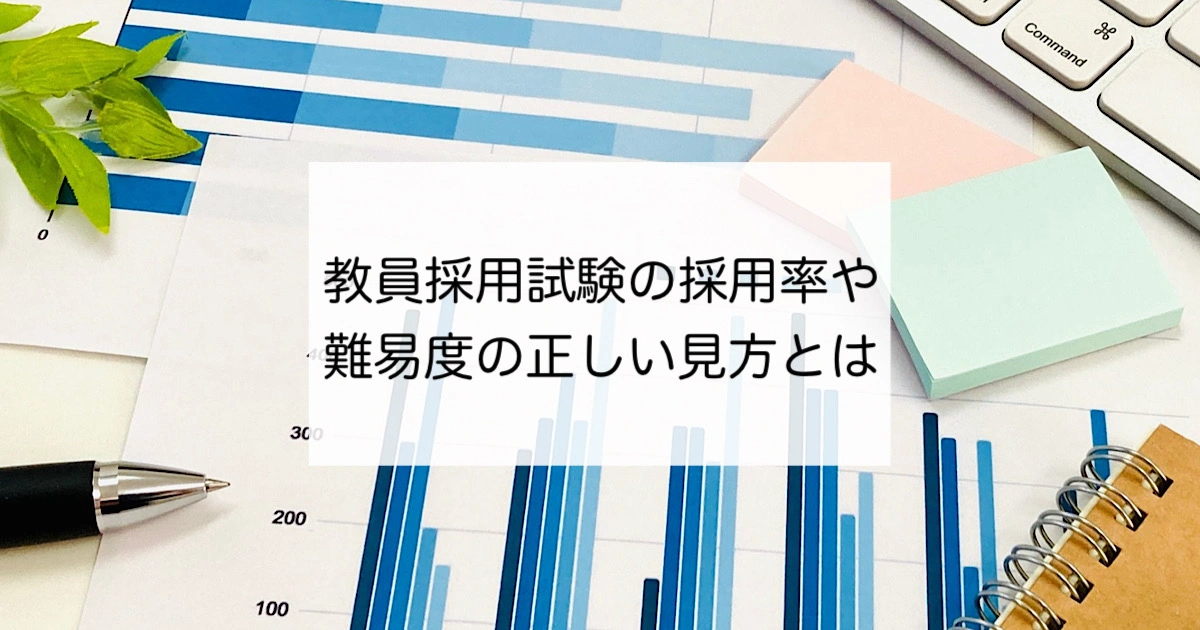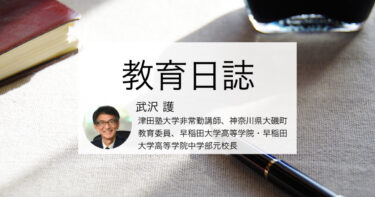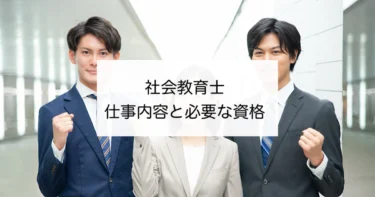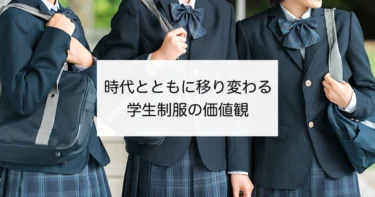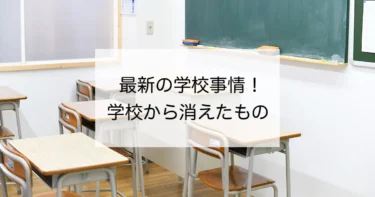教員採用試験の日程が全国的に前倒しをした影響もあり、既に試験が実施され、受験した人や受験直前という方も多くいるのではないでしょうか。
全国的に見ると採用の平均倍率は下がり、昔に比べて合格しやすくなっているように見えます。
読者の中には来年度以降に教員採用試験を受けようと考えている人も多いと思いますが、採用試験の倍率の数字を正しく理解しないととんでもない間違いをすることになります。特に教員採用試験の日程が前倒しになった昨年以降、倍率の数字の意味を正しく理解して受験する自治体を決めることが大切です。
ライター

emikyon
・元公立学校教員
・教育委員会にて勤務
・eduloライター歴3年
教員採用試験は重複での受験が可能なため県によっては高い数字になる
教員採用試験の倍率をみると全校種の平均で最も高いのが沖縄県の8.48倍、低いのは新潟県の1.27倍となります。一見すると沖縄は非常に受かりにくそうに見えますが、実は倍率を押し上げているのは、沖縄県の高等学校の採用倍率で14.9倍という数字が大きく押し上げています。沖縄県の小学校の採用倍率は2.8倍、中学校は5.3倍で、全国的に見れば高いものの小学校や中学校は大きく倍率は下がります。このように受験する校種によって倍率が変わるため注意が必要です。
もう1つ注意しておきたいのが、教員採用試験は重複受験が可能という点です。教員採用試験は自治体ごとに行われており、試験日程が統一されているわけではありません。また、受験できる自治体は全国どこでもよいため、重複して受験することができます。もちろん両方受かった場合、どちらかの自治体は辞退するため、繰り上げの採用者が多く生まれます。
2024年に高知県の教員採用試験(小学校)において採用予定数130名のところ547人が受験しました。これだけ見れば4倍程度の倍率になりますが、高知県では辞退者を想定して293人の合格を出しています。つまり、実質の倍率は2倍以下という数字です。このように多くの合格を出しているのは辞退者を想定してのことですが、試験前に公表される倍率と実際の試験の倍率が異なる自治体が多い実態があります。特に重複受験者の多い自治体ほど、数字を見るときには注意をしましょう。
採用試験の日程前倒し・一次免除のルールで倍率がばらける
このように新聞などで公表されている倍率と実際の倍率が大きくずれる現象は、今年度さらに増えると見込まれています。
その要因は
・採用試験日程のさらなる前倒し
・一次免除制度を利用できる人数の増加
この2点です。
まず、文部科学省は「令和8年度教員採用選考試験の実施に関する留意点等について(通知)」において、『令和7年5 月 11 日を一つの目安(標準日)とする』要請を出しています。令和7年度採用教員採用試験で6月実施への要請をしていましたが、今年度はさらに早めています。
令和7年度教員採用試験において日程を早めた結果、自治体によって試験日程のばらつきが多くなり、重複受験をする人が増加しました。その結果、高知県での採用試験のような大量採用に、大量辞退者が発生することになりました。本年度さらに日程がばらけたことにより重複受験がしやすくなり、正しい倍率が分かりにくい状況となっています。
2つ目に「一次免除制度」の影響です。令和7年度に実施された教員採用試験から「大学3年生から一次試験を受けることができる」ルールを採用したところがあります。元々、一次試験免除の制度は「講師経験者」や「かつて他の自治体で教員採用試験合格者」といった人を対象に行われていましたが、ここに現役大学生の前年度合格者が加わることになります。一次試験の倍率は公表される通りですが、一次試験の倍率に比べて二次試験の倍率が大幅にあがることが予想されます。
このように採用試験日程の変更が、倍率の数字にも大きく影響を与える可能性があるため数字を見るときには注意が必要です。
辞退者が多くなり実質の倍率がわかりにくくなる
昨年度、高知県だけでなく他の自治体でも辞退者が相次ぎました。そのため、神奈川県や兵庫県をはじめとした12の自治体で追加募集を行う事態にもなっています。
神奈川県や兵庫県といった受験者数も多く、人気がある自治体でも辞退者が相次いでいる背景として
・ほかの県との重複受験が可能であり、両方受かった結果辞退した
・辞退者の想定が甘く採用者数に穴が開いた
このような状況が予想されています。
では、令和8年度に実施される教員採用試験はどうなるのかというと、昨年度よりも辞退者を想定してより多めに採用することが見込まれます。この「多めの採用者数」は公表されないことが多いので、今年の倍率は実際にどのくらいなのか分かりにくい状況になっています。
このような状態は、昨年度辞退者が多くなった自治体だけでなく、ほかの自治体でも起きる可能性は高いです。元々、採用試験の倍率が低い「小学校採用」は実質倍率が大きく下がり、受かりやすい状況になることが見込まれます。
重複での受験は良いが教育現場を混乱させる一員に
教員採用試験の日程がずれたため、受験者によってみるといくつかの自治体を掛け持ちすることができ、採用試験に受かりやすい状況となりました。もちろんルール上、認められている制度なので問題はありませんが、採用する自治体の現場でも大きな混乱が起きています。
まず、採用試験の追加を行うのは12月頃になります。この頃、現場では管理職の人事配置の大枠が決まり、教職員の異動に関する調査が始まっています。当然、新任の教員を指導するには指導教官となる人が必要になるので、新卒採用者のいる学校には、指導することができる教員が充てられます。しかし、この段階で新任が決まっていなければ、その部分は「欠員状態」となり、二次募集の結果を待つことになります。二次募集で採用の枠が埋まり、次に欠員が出ている学校に対して「講師の補充」が行われます。この講師は「教員採用試験の不合格者」から充てることが多く、採用試験の日程が遅くなれば遅くなるほど、いろいろな人事が決まるのが遅れていきます。二次募集次第では4月から欠員がいる状態で学校を始めなければいけない状況にもなります。
現場の感覚から言えば、大量辞退者によって二次募集が実施されることで、4月からの学校スタートにも大きな不安と欠員発生時の負担がのしかかります。
自分の希望する自治体の試験をよく確認して受けよう
令和8年度の教員採用試験は実質の倍率が非常に分かりにくい中で実施されます。ただし、昨今の事情を考えれば採用はされやすい状況であると考えられます。
採用試験を受ける人は、しっかりと正しい倍率をみて受験すること、また、夏の試験に不合格であっても二次募集の可能性があります。採用試験に関する情報をしっかりと調べて受験するようにしましょう。
参考文献:令和8年度教員採用選考試験の実施に関する留意点等について(通知),文部科学省,https://www.mext.go.jp/content/20240426-mxt_kyoikujinzai01-000011998_4.pdf,(参照2025-5-10)