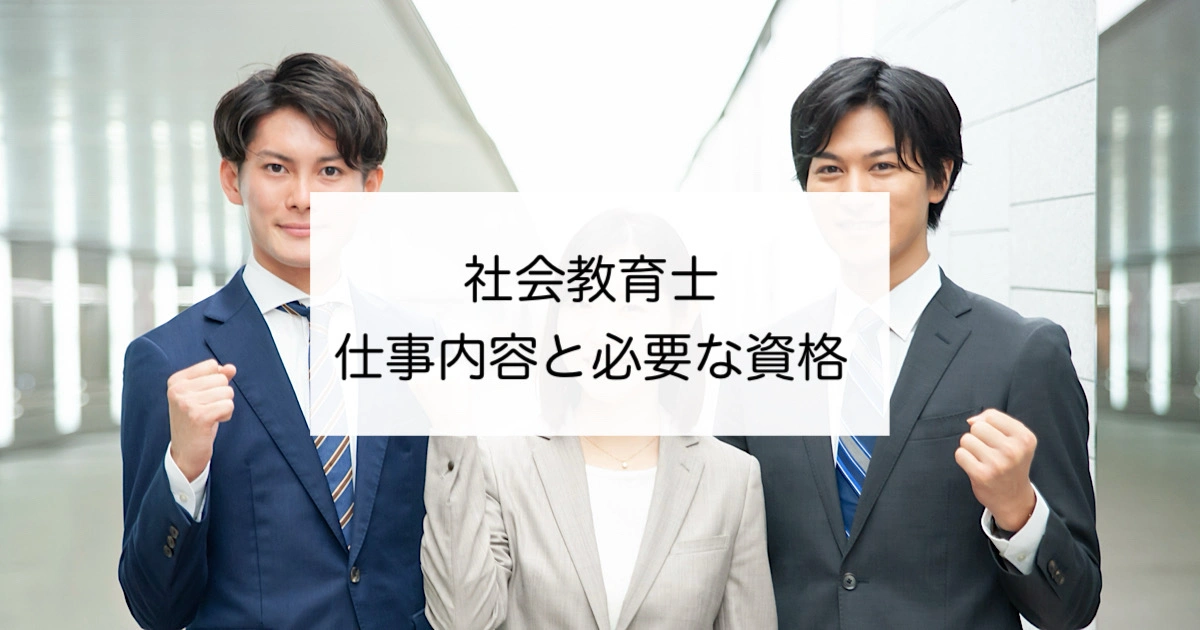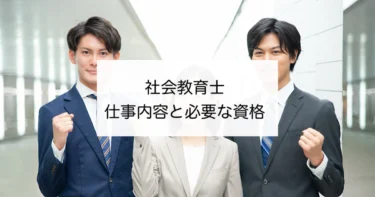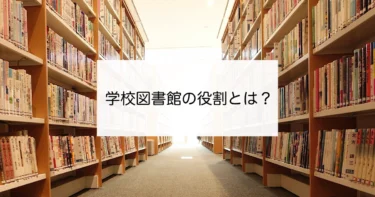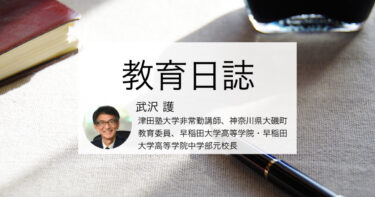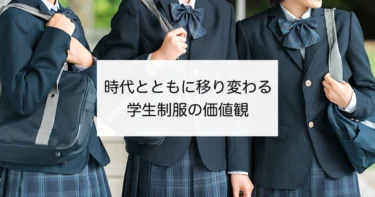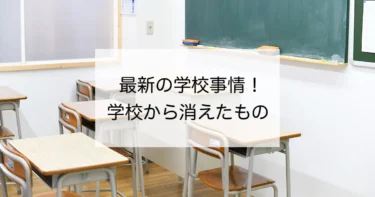教員の中でも、「社会教育士」についてよく知らない方も多いのではないでしょうか。社会教育士は、地域の学びや人々の交流を支える重要な役割を担っています。今回は、その仕事内容や必要な資格について解説します。
社会教育士とは?
はじめに、「社会教育士」という資格は、2020年に誕生しました。それまでは「社会教育主事」という名前でした。
地域社会のさまざまな課題を解決するために、人々の学習活動を支援し、豊かな地域づくりを推進する専門家として、行政、NPO、企業、学校など、さまざまな分野で活躍しています。現代社会における「学びの重要性を幅広い世代に指導していく」ことが仕事になります。
社会教育士の役割と仕事内容
社会教育士は、具体的にどのような仕事をしているのでしょうか。詳しい役割と仕事内容について紹介していきます
社会教育士は、人々の「学びたい」という意欲を掘り起こし、その学びを地域全体の力を変えるためにコーディネートをしています。したがって、学びを受けたいという人の対象は全世代であり、子どもたちだけでなく、子育て世代や高齢者の「学びたいニーズ」に対応します。
そのため、仕事の内容は大きく3つの柱から構成されています。
①コーディネート(人やものをつなぐ)
例えば、地域に専門的な知識を持っている人材がいる、資源(観光産業や地場産業など)があるといったことに目をつけ、地域の人同士を結び付けて学びにつなげたり、広報活動を通して他の地域に向けて発信する仕事です。
こうした仕事をするためには、行政や企業、NPO法人などと連携して進めなければいけません。この「連携」にあたる部分を担当するのが社会教育士になります。
②ファシリテーション(人や地域のニーズを引き出す)
2つ目の柱が「ファシリテーション」です。その地域にどんな学びのニーズがあるのか、地域として必要とされている課題は何かを見つけ出し、解決に向けた準備をします。
例えば、地域に若い人が多く、新興住宅地やマンションなどが増えている地域であれば、子育て家族の支援制度が必要になります。また、育児の悩み相談を受け付ける場所も必要になるでしょう。こうした、住民のニーズを聞き取り、関心に応じた支援策や教育プログラム、ワークショップの準備を担う仕事も1つです。地域が必要としているニーズは場所によって大きく異なります。また、時代の流れによっても変化するため「今」何が求められているかを読み取り、実行する力が必要になります。
③地域や人のコンサルティング
3つ目の柱が、コンサルティングです。ニーズを知り、人を集めるだけで活動ができるわけではありません。場所や運営資金の手配、持続的に行うものであれば運営組織の構築が必要になります。また、提供した「学び」が地域の力として役立ったのかを検証する必要もあります。こうした組織作り、運営について専門的なアドバイスをします。
社会教育士の仕事は、司会進行をしたり、講師として指導をしたりするなど表舞台に立って行うことは少ないですが、地域のために縁の下の力持ちとして準備運営に関わっています。
具体的な仕事の事例
続いて、「社会教育士」の仕事について、実際の事例を元に紹介していきます。
1.地域住民と小学生が協働するキャリア教育
本事例の学校は、過疎地域の小さな学校ということもあり、キャリア教育をしたくてもなかなか今の若者に人気の仕事が地域にはありません。そこで社会教育士に相談し、2つの方法で授業を実施しました。
まず、子どもたちに人気の職業人との話は、ICT機器を用いたオンラインでの講演、質問タイムを設けて、遠く離れていても実際に働いている人の生の声に接することができました。2つ目に、地域を知ってもらう観点から地域の職人や農業従事者、また、農業を管理している農協の職員などを講師に招いて、実際に活動しながら自分たちの町にはどんな産業があるのかを学ぶ授業をコーディネートしました。
2.外国人住民の生活支援と多文化共生
ある自治体では、外国人住民の増加に伴い、生活上の困りごとや地域との交流不足という課題がありました。また、周囲の日本人との溝も大きな問題で「共生」をどのようにするかも問題でした。そこで、社会教育士の資格を持つ行政職員が、外国人住民に対して、ボランティアによる日本語教室を開設しました。単に日本語を教えるだけでなく、日本の生活習慣や子育てに関する情報交換の場としても機能させました。参加する外国人親子と地域の日本人住民が交流する機会を設けることで、相互理解を深め、誰もが暮らしやすい多文化共生社会の実現を目指す取り組みをしています。
このように、教員や一般の行政職員ではなかなかできない、横につなぐ役割を持つのが「社会教育士」になります。
3. 「社会教育士」と「社会教育主事」の違い
新しくできた「社会教育士」と従来からある「社会教育主事」を混同する人が多いので違いを知っておきましょう。
「社会教育士」は、社会教育主事講習や大学の養成課程を卒業することで名乗ることができます。「社会教育主事」は地方公務員として教育委員会に所属し、教育委員会から発令されることによってその職務につくことができます。つまり、社会教育主事は、教育に関することに活動が制限され、生涯学習や図書館教育の運営に関する指導助言をします。一方で社会教育士は、教育行政の場に限定せず、NPOスタッフや地域ボランティア、企業職員として様々な立場から活動できる特徴があります。
社会教育士になるための資格とは?
社会教育士を目指す場合には大きく2つのルートがあります。
1.大学で必要な科目を履修する
大学や短期大学で、文部科学省令で定められた社会教育に関する科目を履修し、所定の単位を修得する方法です。
現在、大学や短期大学に在学している人または、すでに大学を卒業しているが、社会教育士の資格取得を目指したい人(科目等履修生として必要な科目のみを履修する制度がある)が受講可能です。必要な科目は、社会教育の専門的な知識やスキルを体系的に学ぶための科目が含まれます。具体的には、「生涯学習支援論」「社会教育経営論」「社会教育実習」などです。これらの科目をすべて修得し、大学を卒業すると「社会教育士(養成課程)」と称することができます。
2.社会教育主事講習を受講する
文部科学大臣が指定する「社会教育主事講習を修了」する方法です。この講習は、社会教育の現場での経験がある人や、教員免許を持っている人などを主な対象としています。
したがって対象者は
・大学・短期大学を卒業している人
・教育職員の普通免許状を持っている人
・社会教育に関係する職務に2年以上従事している人
・学校の教職員に4年以上勤務している人
・その他、文部科学大臣が同等以上の資格があると認めた人
と少し条件が厳しくなります。
講習は、社会教育の専門的知識やスキルを短期間で集中的に学ぶことができ、講習を修了し、所定の単位を修得すると「社会教育士(講習)」となります。
幅広い意味で「地域の教育」を支える仕事
現在の日本社会は、少子高齢化、地域コミュニティの希薄化、多文化共生、格差、孤立など、多くの課題を抱えています。これらの課題は、学校や行政の力だけでは解決が難しく、住民一人ひとりの「当事者意識」や「自発的な活動」が求められます。社会教育士は、まさにこうした課題に対して、人々の学びを促し、つながりを生み出し、主体的な活動を支援するプロフェッショナルとなります。
参考文献:社会教育士note,文部科学省,https://mext-shakaikyoiku-gov.note.jp/,(参照 2025-8-4)
参考文献:社会教育士って何,文部科学省,https://www.mext.go.jp/a_menu/01_l/08052911/what.html,(参照 2025-8-4)