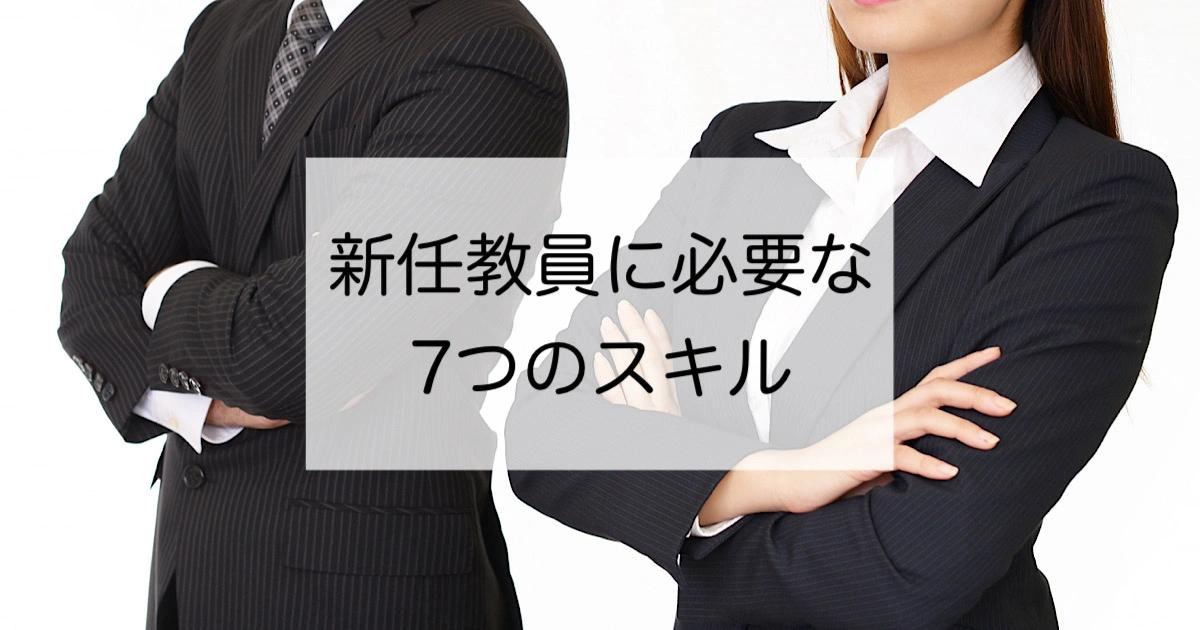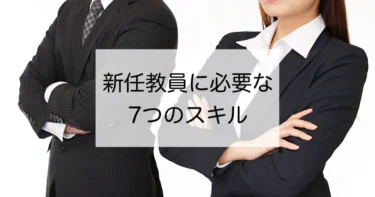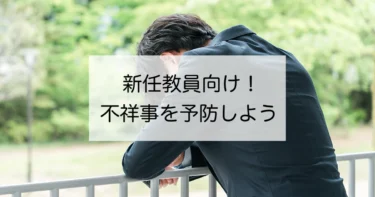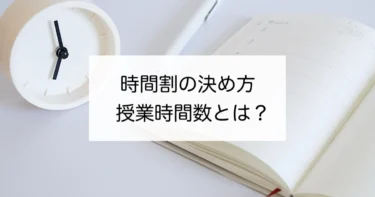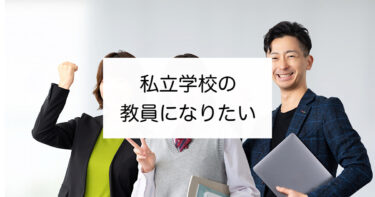新任教員や若手教員の皆さんの中には、慣れない環境での精神的疲労や仕事への充実感、うまくいかない焦りなど様々な思いが出てきた頃ではないでしょうか。新学期から1、2ヶ月経つと子ども達も少し落ち着いてくる時期です。よりよい学級づくり・授業づくりをしていくためにも、この時期に新任教員として身につけておくべきことを確認しておきましょう。
ライター

emikyon
・元公立学校教員
・教育委員会にて勤務
・eduloライター歴2年
①元気に挨拶をする
教員は子ども達に対して「あいさつをしましょう」と教える立場ですが、自分自身は実行できていますか。朝職員室に入るとき、同僚を見かけたとき、子どもを見かけたとき、自分からあいさつすることができているでしょうか。学校周りで保護者や地域の人を見かけたときには、自分からあいさつをするぐらいの気持ちが欲しいものです。
ただ、教員も人間です。疲れがたまっているとき、ストレスがたまっているときなど、なかなか自分からあいさつができないときもあります。そこまで追い詰められた状態になっているのであれば、少し休むことも大切です。まだまだ数日で回復できる状態ですが、ここで無理をすると長期的に休まないと治らない状態になりますよ。
②子どもの話を聞こう
あなたの子どもたちに対する接し方はどうでしょうか。授業や日常生活の中で指示をすることが多い教員ですが、指示ばかりにならず、子ども達の話をしっかりと聞けていますか。
新任教員に限らず子どもとの関係作りに溝が生まれてくるのが5月、6月です。その原因の1つが、子どもの状況を教員がしっかり把握できていないケースがあります。子どもとの関係に慣れてきて、子どもの話をしっかりと聞かない状態になっていないでしょうか。また、特定の子どもとばかり話しをしていないでしょうか。いま一度確認してみましょう。
③メモをとろう
大切な情報を逃さないようにするために、メモをとる癖をつけましょう。記憶力の良い人であれば覚えておくこともできるかもしれませんが、教員に入ってくる情報は膨大です。ちょっとした情報伝達ミスから学校と保護者との大きなトラブルにつながることもあります。子どもの変化を見逃すことになるかもしれません。
メモ用のノートの作成や、付箋を持ち歩くことがおすすめです。付箋の場合は落としてしまう可能性もあるため個人情報以外を書かないようにしましょう。
学生の頃からたくさんの情報を整理して順序付けするテクニックを磨いておくと教員になってからも役立ちます。すでに現場で活躍している人は、情報の整理法を身につけるとぐっと仕事の効率が上がりますよ。
④気づきの感性を磨く
子どもの変化を慎重に見ていないと小さな変化に気が付かず見逃してしまいます。そこで、経験の浅い先生にはぜひ「気づきの感性」を磨いてほしいと思います。ではどこを見ておくとよいかというと次の3点に注目してみてください。
・言葉遣いに変化はないか
・人間関係が変わっていないか
・服装は毎日変わっているか
最初の2つは友達関係を見抜くことができます。最後は家庭環境の変化に気づくことができます。このようにちょっとした変化を見逃さないように、常に前日や前週、また週に1回しか入らないような教科担任や部活動顧問のアドバイスをしっかりと聞いておくとよいです。
⑤1人で抱え込まない
クラスや学年のトラブルに遭遇したり、ベテランの教員と自分を比べてしまってはいませんか。そんなときは一人で抱え込まないようにしてください。一人で抱え込むと仕事も止まってしまいます。周りに対して「助けて」と言うことも大切なスキルです。でも、実際にはなかなか弱音が言えずに、どうにもならない状態になってしまう人もいます。管理職や学年主任も経験の浅い教員を何とかサポートしたいと思っていますが、瞬時に様子がわかるわけではありません。一人で仕事があふれてしまいそうになった時には早めに「助けてほしい」と言うようにしましょう。そのほうがサポートをする側もしやすいのです。
⑥チャレンジ精神を持とう
経験が浅い、若いからと言って遠慮をする必要はありません。若い教員だからこそできることもあります。例えば、最近導入されているタブレットやデジタル端末の使い方は若い教員のほうが慣れているのではないでしょうか。
デジタル教材を活用した授業やアプリケーションを使った主体的な学びを活用することができるのであれば、積極的にチャレンジして授業に導入していきましょう。チャレンジをする際には学年や管理職に相談してから始めてみましょう。
⑦コミュニケーション能力を培おう
教員になるとコミュニケーション能力の大切さを実感するようになります。教員が接するのは子どもだけでなく、保護者や地域の人、同僚など様々な人々がいます。子どもを除けば多くの人が自分より年上であり、これまでの学生生活と同じような感覚で接しているとよいように思われないこともあります。
保護者対応でも堅苦しくない雰囲気で話せる場面とそうではない場面があります。礼儀や手順といった昔ながらの手続きを踏んでいかないといけない地域の重鎮と接することもあるでしょう。その人とどのように接すればよいのか考えて、対応できる力をつけておくと、今後のコミュニケーション作りに大いに役立ちますよ。
この時期に7つのスキルを身につけよう!
5月は大型連休があるものの4月からの忙しさを抜けて、気が緩む時期でもあります。それだけ教員も子どもも疲れが見えてくる時期といってもよいでしょう。だからこそ、お互いにイライラしやすくなり、上手くコミュニケーションをとることができなくなることもあります。そんなときこそ、教員に必要なスキルを確認し、身につけておきましょう。今後は、成績処理も入ってきて忙しくなります。しっかりと子ども達を観察し、クラスが乱れてきていると気づくことができると早めに修正することができ、安心して1学期を乗り越えることができますよ。