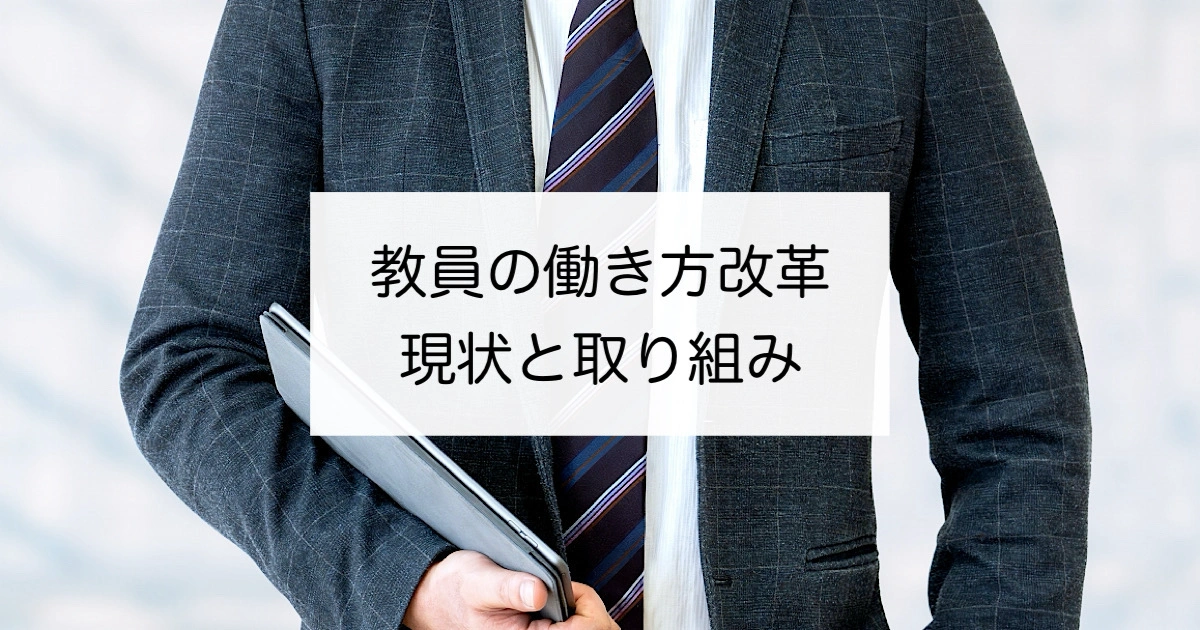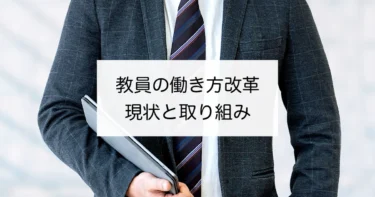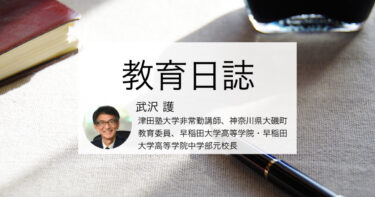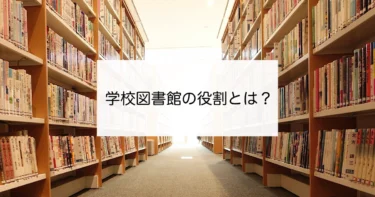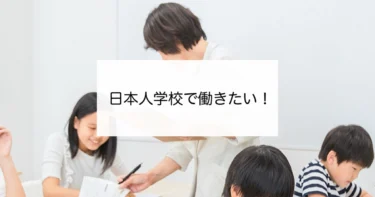長時間労働といった「教員の働き方」が問題になってから早数年が経過しました。日々忙しい現場にいると「改革は進んでいるものの目標には到底及んでいない」と感じている教員も多いのではないでしょうか。管理職の方々も、教育委員会と教員の板挟みとなりプレッシャーを感じていることでしょう。
では、実際に学校現場ではどこまで働き方改革が進んでいるのでしょうか。働き方改革の進行状況は、学校事情によっても差があります。自身の学校で取り入れているものもあれば、聞いたことのないものまであると思います。既に現場で働いている教員は、ぜひ自分の視野を広げるためにも、各地の取り組みを参考にしてください。
業務の削減・効率化
教員は授業だけなく、生徒指導や部活動の指導など業務量が多い職業です。学習指導要領の中身も満載で、カリキュラムを消化するだけでも精一杯という方も多いのではないでしょうか。
そのため、現在は、業務の効率化や削減などへの取り組みが行われています。
なお、取り組みの判断基準になっているものが文部科学省の示す『学校・教師が担う業務に係る3分類』です。ここから学校事情に合わせた選択が行われています。
ICT・校務支援ツールの活用
全国的に取り組んでいる事例で多いのが校務のICT化です。例えば校内の仕事として多いものにお知らせやテストなどの印刷物があります。印刷、振り分けといったことにも時間がとられます。このようなものを一気に片付けてしまうのがICTです。
例えば、保護者への連絡ツールやアプリを利用して、電子データで送付する。webページへのアップのみにする。保護者からの欠席、遅刻連絡は電話ではなくメールがアプリのコメント機能で受け付けるといった手法です。
その他にも
・週案(毎週教員がつける授業記録)の電子化
・通知表の印刷配付
などが挙げられます。
生成AIが入ってきたことで、文書作成をAI活用している人も出てきました。さまざまな校務支援ICTを活用して効率化している人がいる一方で、どうしても「ICT機器の活用差」による「教員の業務能力の差」が生じています。
事務作業の外部委託・教員以外のスタッフの配置
先ほど挙げたプリントの印刷や連絡ツールの使用は、教員でなければできないものではありません。学校には、清掃や電話応対など教員以外が担うことができる仕事もたくさんあり、部活動もその1つです。これらの仕事を行うにあたって「教員免許」は必要ありません。
そこで、学校内における事務作業を外部委託、または地域の人を有償ボランティアとして雇う学校もあります。任用するのは学校であったり、自治体であったり差があります。また、呼び方も「学校補助員」や「スクールサポートスタッフ」などの呼び方がありますが、事務作業をサポートしてくれる人として教員以外のスタッフを雇う学校が増えています。
会議・書類の見直し
次に会議や書類、出張の見直しです。学校でいえば職員会議に進路指導会議、書類も必ず作成しなければいけない「指導要録」や「個別の指導計画」、教育委員会や文部科学省から依頼される調査などがあります。これらも見直しが行われ、職員会議については電子化して印刷の手間や会議時間の削減が行われています。
出張に関しても各学校に配備されたタブレット端末を利用して、オンライン会議に変更し、移動する時間の削減をしています。教員の研修についても、研修の内容を精査し、集合でやらなければいけないものは集合で行いますが、オンラインやeラーニングシステムを使ったオンデマンド研修に切り替えているところも増えました。こうした見直しを取り入れて、教員への負担を削減しています。
部活動改革
どの自治体も頭を抱えている働き方改革が部活動のあり方ではないでしょうか。小学校の教員はなかなかピンと来ないかもしれませんが、中学・高等学校の教員にとっては大きな問題です。生徒の受け入れ団体や連絡調整、どれも簡単にできることではありません。国もガイドラインは示しているものの、やり方は自治体任せになっているのが現実です。
休養日の設定
とりあえずという「改革」で行われているのが休養日の設定ではないでしょうか。土日のどちらかを休みにする、平日も決まった日を部活動なしにするなど、強制的に休みを設定するようにしています。
地域移行
部活動改革で目玉になるのが「地域移行」です。これまで教員が担ってきた部活動を地域のクラブチームに移行する方法です。メリットとしては
・専門の指導者に指導をしてもらうことができる
・いくつかの学校が合体することで集団スポーツ(野球やサッカーなど)の維持ができる
などがあります。
一方でデメリットとして
・学校での活動に比べれば保護者の費用負担が大きくなる
・平日の授業後に活動することが難しい
などがあります。また、実際に地域移行が始まった現場では課題として
・学校と地域以降のクラブ、子どもたちとの連絡が上手くいかない
・受け入れる地域クラブの数、指導者数の不足
などの問題が浮かび上がっています。
生徒の部活動に対する意識調査も地域移行のクラブチームで「やりたい人」と「やりたくない人」の差がはっきりとしており、かつてのように半強制的に部活動に全員が参加するような状況ではありません。思ったように人が集まらなかったり、団体だけではチームを維持することができなかったりして、上手く活動できていないところも多いです。
勤務時間の適正化
教員は「勤務時間」に関する意識が薄いと言われてきました。確かに、今この記事を読んでいる人も勤務時間の開始と終了、休憩時間は何時から何時までと即答できる人は少ないのではないでしょうか。
このようになってしまった理由として
・勤務開始よりも前に子どもが登校してくるのは当たり前
・勤務終了時以降も会議や部活を平気でやっている
・休憩時間は子どもの管理で教室にいるのが当たり前
こんな日常が「当たり前」という常識になってしまったところにあります。
勤務時間管理の徹底
そこで近年は、勤務時間の徹底が図られるようになりました。
具体的には
・勤務時間の開始と登下校の時間を合わせる
・休憩時間を「休み時間」と設定する
・電話応対や来客対応は勤務時間中のみとする(留守番電話機能の設定など)
このような改革をして教員が勤務時間を意識しやすいようにしています。管理職からも時間を意識した働き方をするように指導が入ります。
働き方の意識改革
2つ目は、働き方の意識改革です。教員の仕事は、やり始めるときりがない部分があります。個人(担任)の裁量に任されている部分があり、教室掲示や教材研究などこだわればいくらでも時間をつぎ込めてしまう仕事です。「子どものために」「保護者のために」と親身になればなるほど「良い先生」と評価される部分もあり、一生懸命な教員ほど勤務時間が長くなる傾向があります。
こうした働き方は、これまでの伝統的な働き方からきている部分であり、ある意味「悪しき伝統」とも言えるでしょう。特に「ゴール目標」なく仕事をしていることが仕事を増やし、改善につながらないのです。
そこで最近の働き方改革の研修では、ゴール目標の設定をすることをよく言われます。教員の力量向上、日々の業務、教材研究でも、事前にどこまでやるのかという計画を立てて仕事をします。ゴール目標を達成したら、ゴールにたどり着くまでにかかった時間と効果について検証し、改善する時間を設けるように指導を受けることが多いです。
やるなら今しかないという意識を全職員が持って取り組もう!
近年、教育現場の働き方改革に向けてかなりの追い風が吹いています。マスコミの報道、地域の声を聴いていても「働き方改革をサポートしよう」という声が多いのです。このような機会に変えていかなければ次はいつ変えることができるようになるか分かりません。教員も管理職も今しかできないという意識をもって、学校組織として取り組むことができるようにしましょう。
参考文献:学校における働き方改革について,文部科学,https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/hatarakikata/index.htm,(参照 2025-8-16)
参考文献:「学校・教師が担う業務に係る3分類」更なる役割分担・適正化の推進に向けた取組について,文部科学省,https://www.mext.go.jp/content/20230725-mext_zaimu-000031116_3.pdf,(参照 2025-8-16)