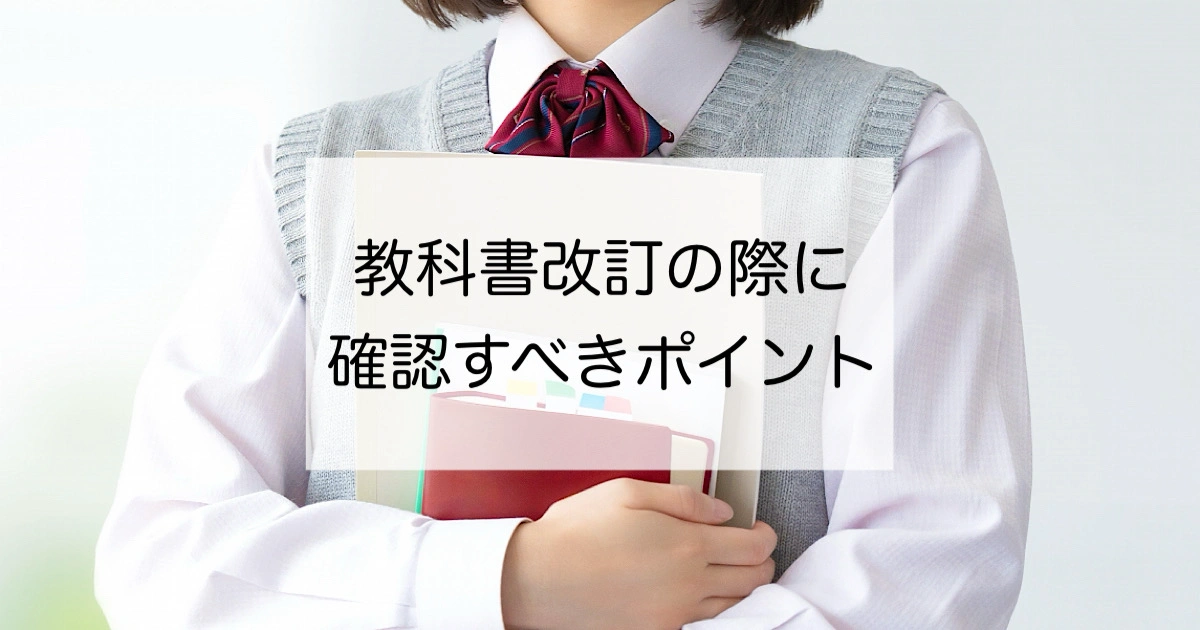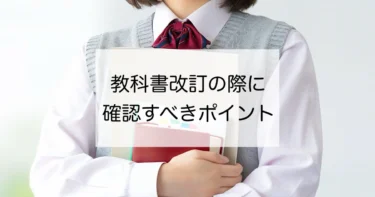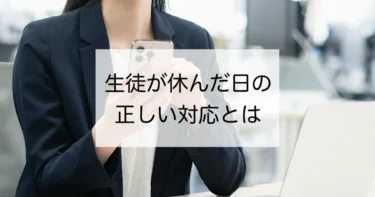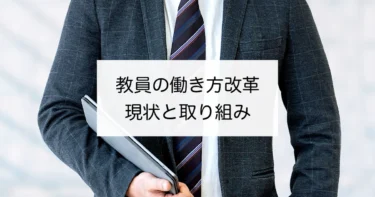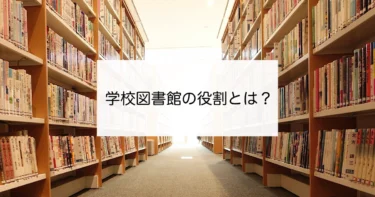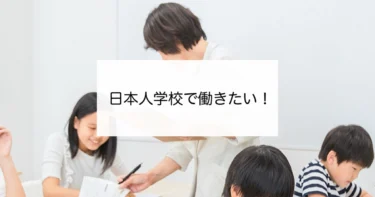中学校では、2025年度からの教科書改訂に伴い、新教科書が使われるようになりました。4年前の全面改定と比較すると大きな改訂とは言えませんが、実際に教科書を見てみると「イメージと違う」という印象を抱いた教員も多くいるのではないでしょうか。
今回の教科書改訂で、特にポイントとなるのが「デジタル対応」です。4年前に発行された教科書は「タブレット端末の一人一台付与」が行われる前に作成されましたが、今回からは、タブレット端末が子どもたちの手元にあることを前提として、紙の教科書でありながら「二次元コード」などを活用して、デジタルの学びをすぐに使うことができるように工夫された点が大きな変更になります。また、「個別最適化」「協働的な学び」が重視されるようになり、「子どもが主体的に学ぶことができる」ように教科書の内容や説明も変わりました。
ライター

emikyon
・元公立学校教員
・教育委員会にて勤務
・eduloライター歴3年
まず確認するポイント
すでに教員の皆さんの手元には新しい教科書が届き、時間をかけて教材研究をされたのではないでしょうか。今回は、教科書改訂の際に「確認すべきポイント」を2025年度に改訂された中学校教科書を元に説明させていただきます。
①単元の配列と時間数などカリキュラムの変更
はじめにこれまでと同じ教科書会社であっても改定によって
・単元の配列
・単元の授業時間数
この2点は変更になる可能性があります。
地域によっては前年の段階で新しい教科書に対応した「カリキュラム(指導課程)」を市や教員の代表で作成するケースもありますが、まずは単元の配列と授業時間数を確認しましょう。これまで8時間完了だった単元が6時間完了になっていたり、単元の配列が変わっていると学習計画やテスト計画に大きな支障が出てしまいます。
また、教科書の内容を見るだけでなく、教科書のはじめにある「目次」の部分を新旧で比較したり、単元の総ページ数が変わっていないかなど、時間に関係する視点で確認することも大切です。
②補助教材、実験教具
教科書改訂において、教員が一番苦労することになるのが教科書会社の変更です。教科書はすべて同じ教材を使っているわけではなく、教科書会社毎によって「特徴」を出しています。
例えば、国語の教材1つとっても教科書会社ごとに取り扱っている作品が違うため、教科書会社が変わるということは、一から教材研究をやり直しすることになります。理科や技術・家庭科であれば、取り扱いをしている教材も変わっている可能性もあります。
教材が変更になる場合には、事前に準備をしておかないと授業に間に合わないケースもあるので、1年間の授業プランを立てる際に必要なものが学校(実験室など)に整っているのか確認しましょう。
中学校の教科書改訂は高校受験にも直結します。補助教材として、学習者用のドリル教材や問題集を購入している場合、教科書が変わるとドリルの販売元から見直さなければいけないこともあるので要注意です。
③単元内で取り扱っていた教材
教科書会社が変更になった場合には、教材の中身を再確認するので、何が変わったのか注意深く確認すると思いますが、教科書会社が変わらなくても内容に変更が多いケースもあるので注意が必要です。
特に今回の教科書改訂では「デジタル対応」がポイントになっていることを前述しました。
デジタル教材が重視される一方で、何かを減らさないと総授業時間の縛りに収めることはできません。
そこで教科書内の教材の軽重を確認しましょう。数学や理科であれば、演習問題が削減されていたり、必修だった実験が応用や発展扱いになっているかもしれません。そのまま授業をしてもよいですが、子どもたちの実態や入試にあわせて教材の取り扱いを変えるのも1つの方法です。
生徒の実態として読解力が弱いのであれば「読み取りの時間を増やす」、計算力が弱いのであれば「問題演習の時間を増やす」このように特性や実態に合わせてマネジメントするのも1つの方法です。
もう1つ、いろいろな教科書を見ていると今回の改訂で「振り返り」が重視されていることが分かります。各単元末に「振り返り問題」「新たな課題の発見」というシンキングサイクルを意識した構成となっています。振り返りを意図的に評価していくことで「第3観点:主体的に学習に取り組む態度」の評価をすることができるようになりました。第3観点の評価に苦労していている教員は、単元末のページが参考になります。
③教科書が変わる学年と変わらない学年
教科書改訂と言っても注意しなければいけないことがあります。それは、一斉に教科書が変わる学校と段階的に変わるという学校、教科があります。
例えば、技術や家庭科は3年間同じ教科書を使いますが、その場合、1冊の教科書の中に3年間分の指導が入っているため、
教科書が変わるときには
①全ての学年の教科書を一気に変える
②新1年生のみ新しい教科書、2,3年生は旧教科書と分ける
という2つのパターンになります。
3年間同じ教科書を使う教科でなくても、学校事情によって段階的に切り替えていくというケースもあるので確認が必要です。
④デジタル教材の活用法を検討する
4つ目が、改定の目玉である「デジタル教材」の活用方法です。二次元バーコードが付いたことにより、動画解説や実験、英語のリスニングなどを簡単に使うことができるようになりました。
バーコードを活用するには、一人一人に配布されているタブレット端末の利用は必須となり、子どもたちがすぐに端末を使うことができる環境も必要になります。
動画教材をクラス全員で一斉に使おうとするとネットワーク回線容量を一気に使うので、古い回線を使っている場合にはネットワークの増強も必要になります。
実際には、教科書を使い始めてから不具合が分かることかもしれませんが、少なくとも
・子どもたちがタブレット端末をすぐに使うことができる
・クラス全員がデジタル教材を使っても耐えられる回線容量がある
この2点の条件を満たしているかどうかは確認してよいと思います。
⑤経験の浅い教員は教材研究を早めに
最後に新教科書になったことで、教材研究を早めに進めておくことをおすすめします。教材が変わらない場合でも指導する内容や視点は変化していることもあります。教師用の指導書の新旧を比較するとその違いがよく見えてきますよ。
今まで通りの教材研究で授業をやっても子どもに力を付けさせることはできるかもしれませんが、それは新しい学びにあわせた指導ではありません。「主体的・対話的で深い学び」と言われていた前の教科書の頃から「個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実」という新しい考えに基づいた指導に変わっています。
これから長い教員生活をしていく人には、ぜひ、教科書改訂の時期に新学習指導要領の総則に習った考えを従来の考えと比較しながら教員自身のスキルアップを図ってほしいと思います。
今回の教科書改訂は「主体的に学ぶ」がポイント
今回の教科書改訂では「デジタル教材」「振り返り」など、従来の教科書改訂と同じぐらい変化があると考えておくべきでしょう。小改訂というとベテラン教員の中には大したことないや変わらないという人もいるかもしれませんが、そのような気持ちではいないほうがよいです。
デジタルが教育に入ってきたことで数年単位で学ぶ視点が変わったり、新しいものが入ってきているのが今の教育です。ぜひ、若手の教員には何が変わっているのかしっかりとつかんで、余裕をもって授業に臨むことができるとよい授業ができると思いますよ。
参考文献:令和7年度 中学校教科書のご案内,一般社団法人 教科書協会,https://www.textbook.or.jp/textbook/07j_textbook.html,(参照 2025-3-3)
参考文献:学習評価の在り方 ハンドブック,国立教育政策研究所 教育課程研究センター,https://www.nier.go.jp/kaihatsu/pdf/gakushuhyouka_R010613-01.pdf,(参照 2025-3-6)