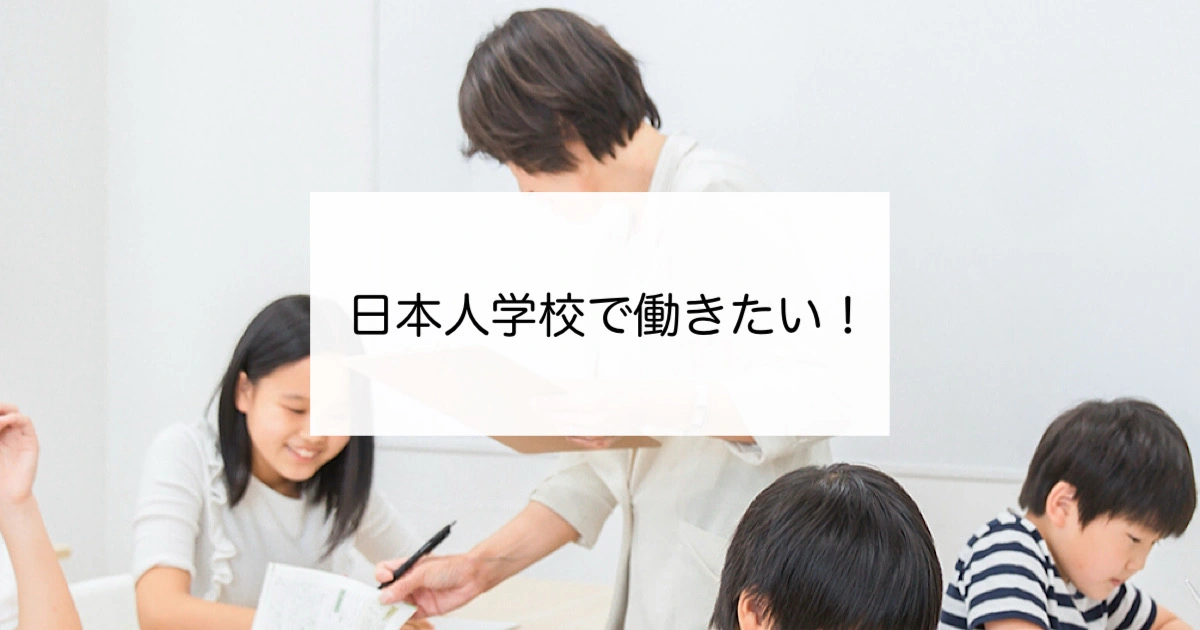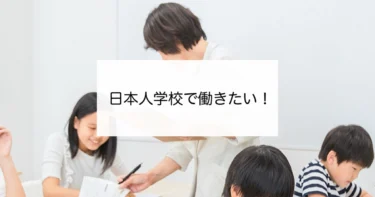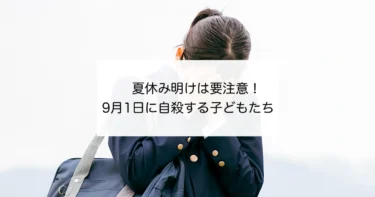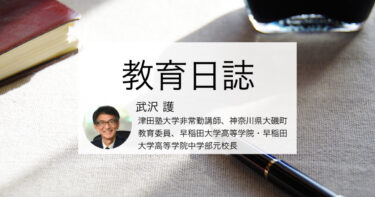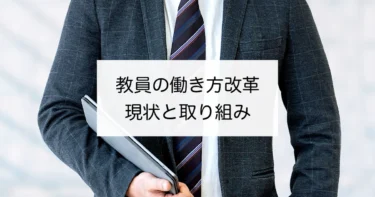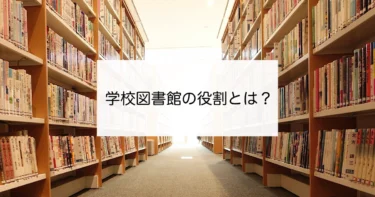筆者は数年前、文部科学省の派遣教員として実際にアジア地域の日本人学校で勤務をしていました。今回は、その経験をこれから在外教育施設(日本人学校)で働いてみたい方に向けて詳しく紹介します。
日本人学校に関する詳しい説明は、「在外教育施設とは? 日本人学校での勤務経験のある教員が解説!」をご覧ください。
ライター

emikyon
・元公立学校教員
・教育委員会にて勤務
・eduloライター歴3年
日本人学校で働く大変さとは?
在外教育施設で働く教員は、文部科学省の試験に合格した教員が日本全国から派遣されています。1回の派遣で滞在する期間は約2~4年なので、教員数の多い学校は10人以上が入れ替わることも珍しくありません。
教科書やルールの違いに戸惑う
全国から教員が集まってくるため、授業のあいさつのやり方や指導案の書き方などのそれぞれの赴任前の学校のルールの違いにより戸惑うこともあります。
また、在外教育施設では「全国で最も使われている教科書」を授業で使うため、これまで使ってきた教科書と違うこともよくあります。
仕事の役割について
在外教育施設では、「教員としての経験年数」ではなく、「赴任して何年目か」によって仕事の役割が決まります。筆者の場合は、1年目は担任、2年目には小学部長、3年目に教務主任となりました。当然3年目に新規で赴任してきた教員の中には自分よりも経験年数も、日本での役職も上の方がいましたが、在外教育施設の中では話が別です。
いよいよ赴任先へ 準備が大切!
在外教育施設への赴任は4月4~6日前後になることが多く、到着すると翌々日ぐらいには入学式が予定されていることもあります。
この間、ホテル暮らしをするケースと先輩方が用意した住居に仮入居するケースがありますが、ただでさえクラスの立ち上げで忙しいところに自分の生活の立ち上げもしなければいけません。学校や生活のスタートを2年目、3年目を迎える先輩方がサポートしてくれますが、それでも慌ただしくスタートしたのを覚えています。
この忙しさを回避するためには、赴任前に日本でしっかりと準備をすることが大切です。行先の学校とコンタクトができるようになったら、使用している教科書やドリルを確認し、日本から持っていった方が良い資料があれば持参することもおすすめします。
また、人事がある程度決まっているのであれば、担当学年や校務分掌などを聞いておきましょう。
教員とは全く違う世界を経験できる
在外教育施設は、日本の教育をする場所ですが生活は現地の人にあわせておこないます。日本のように安全な生活ができる場所ではないため、学校の閉まる時間が決められていたり、土日の出勤を禁止されることもよくあるそうです。そのため、自分のペースで仕事をすることはできず、赴任国の働き方に合わせた働き方が求められます。
また、「学校外でのつながり」も大切になります。管理職になれば、大使館のイベントに参加することもありますし、一般職員でも在外公館職員や各国にある「日本人会」、現地で展開している日本企業との関係行事に参加することもあります。
日本人学校は「私立学校」に近いもので、運営に関しては現地の日本人関係者から多くの支援を受けています。
私が赴任している際にも日本国首相や皇族が赴任国を訪れることがあり、日本人学校の訪問をされました。首相夫人と一緒に授業をするという、日本の学校ではまず経験できないことができたのは、一生の思い出になりました。日本では経験できないたくさんの出来事があなたを待っていますよ。
保護者との関わり方
在外教育施設に通っている子たちの保護者の中には高い教育レベルを求めている方も多くいます。海外赴任をするような企業は「大企業」が多く、海外赴任をしている保護者の方も「将来が嘱望されている人材」です。
そのため、高学歴、高収入の保護者が多く、勤務している会社もみんなが知っている大手企業ばかりのため当然、教育に関する関心も高く、子どもの教育に力を入れようと考えている方が多いです。
こうした保護者の中には、教育関連の法律に詳しい方や、学校のカリキュラムに関心を持っている方が多く、中学校1年生の段階から高校入試に向けての情報収集を依頼されたりするなど、求めるレベルの高い保護者を相手して指導をしなければいけません。
もう1つ、保護者との関係で注意しておきたいのが距離感です。派遣教員の中には自分自身のお子さんを帯同させるケースがあります。こうした子どもも同じ学校に通うことになり、教員であると同時に保護者にもなります。
住んでいるところの隣に保護者がいる、週末にスーパーやレストランに行けば保護者がいるなどすぐ近くに保護者がいます。ちょっとした仕事の話をすれば漏れ聞こえますし、保護者との関係が近くなれば「えこひいき」ととられることもあります。保護者と教員の付き合い方は、日本以上に近いだけに注意が必要です。
日本人学校との違い
日本人学校の勤務をすると日本の学校とは違うところがたくさんあります。1つ目は登下校です。日本では登下校の際に、徒歩や公共交通機関を使うのが一般的ですが、海外では安全面を考えて送迎バスまたは保護者の送り迎えとなります。
児童生徒数が1000人を超えるような大規模校では送迎に伴う渋滞は当たり前で「1年生担任の一番大変な仕事は、たくさんいるバスに子どもを確実に乗せること」という表現も大げさではありません。100台を超えるバスが学校から出ていくのを見送るだけでも相当な時間がかかります。
2つ目は給食です。日本人学校ではカフェテリアのような軽食を販売する施設は併設されていても給食はほとんどありません。子どもたちも教職員も弁当持参でやってきます。お菓子やジュースの購入、持ち込みが許可されていて、休み時間にみんな食べているという外国らしい光景が日本人学校内でもあります。
担任生活をしていて気を遣ったのが「教材の準備」です。日本であれば、ノートが欲しい、教材を購入したいというときに業者に電話をすればすぐに持ってきてもらうことができますし、ネット通販で購入することもできます。
しかし、海外の場合、簡単には行きません。大学ノートのようなものは手に入りますが、国語の授業で使う縦書きノート、漢字ノートは日本から送ってもらったり、職員が一時帰国した際に運んだりします。
直前になって物が欲しくても簡単には手に入らない環境なので、数か月前から計画し、必要なものがあれば輸送する時間も考えて日本に頼む先を見通す力を養うことができました
驚きの多い3年間 でも日本では経験できない世界を見ることができる
日本人学校の勤務は3年間でしたが、驚きの連続であると同時に自分自身が大きくスキルアップできた時間でした。中でも、全国から集まってきた教員と一緒に仕事をすると、自分が今まで非常に狭い世界で仕事をしてきたことを痛感しました。保護者も海外を転々と移動している人も多く、企業人との話は教員の世界でしか生きてこなかった自分に新しい世界を見せてくれました。仕事は日本以上に大変なところはありますが、興味のある方はぜひ経験してみてください。