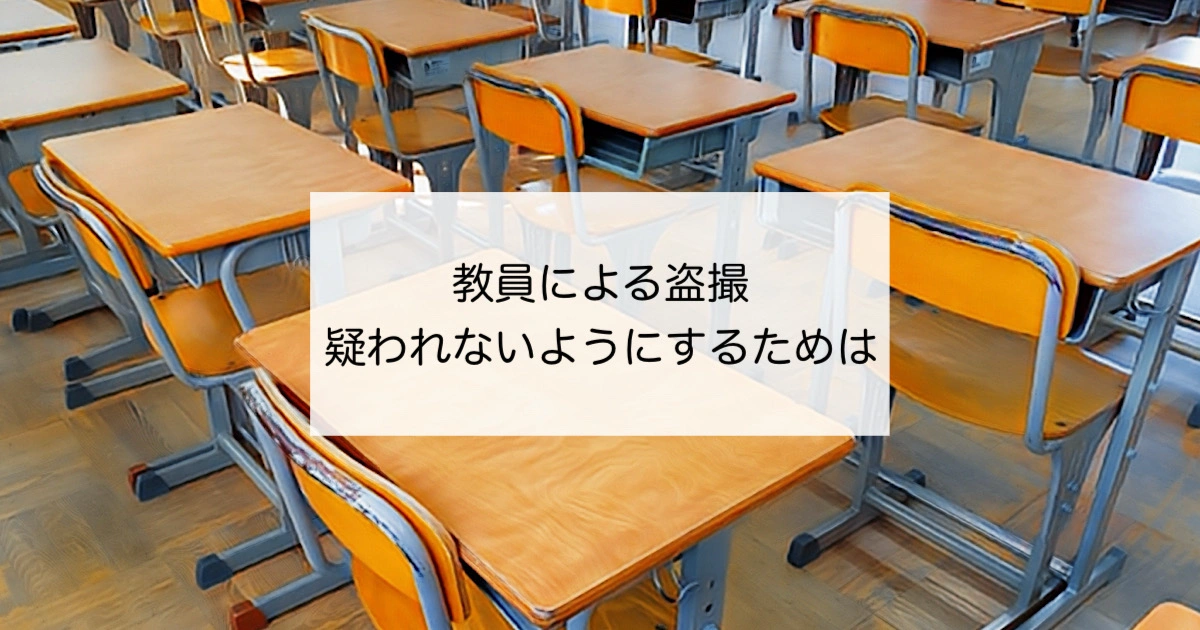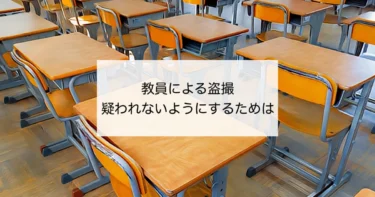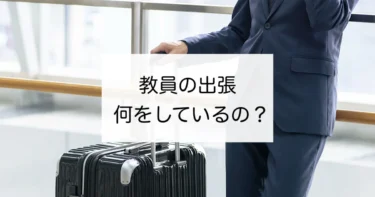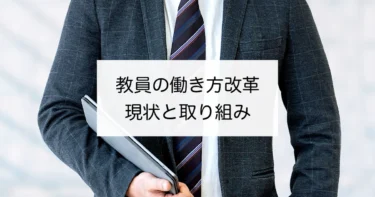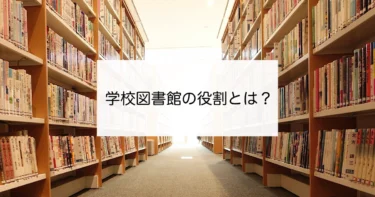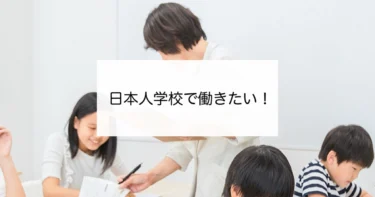25年6月に「教員による盗撮事件」が話題となりました。この記事を執筆している段階では、SNSのグループに入っている教員は特定されておらず、保護者の間には不安が駆け回っている状態です。
ICT機器が学校に導入され、カメラ等で子どもの様子を記録することが当たり前になった昨今、いつ自分が疑われてもおかしくないことは教員一人一人が意識しなければいけません。
今回は、盗撮事案を受けて、自分の身を自分で守っていくために意識するポイントを紹介します。
誰にでも起こりうる周囲からの「疑いの目」
今回の現職教員による盗撮事案が大きなニュースとなった背景には、盗撮しただけでなく、その教員仲間で共有していた点です。また、許されないことに撮影機材は学校で使っているデジカメを用いていたことも報道されています。
教員は、ホームページや学年だより、学校の記録を作成するために普段からカメラ等を用いて写真を撮ることが多くあります。今後は、今回の事件のせいで、子どもたちのために真剣に指導している真面目な教員にも疑いの目が向けられる可能性が高くなるでしょう。悲しいことではありますが、「盗撮を疑われる可能性がある」ことを認識して行動しなければなりません。
疑われないための意識を高く持っておこう
盗撮が疑われても、今やタブレット端末やデジタルカメラは授業や業務をするうえで欠かせない道具となっており、全く使用しないのは得策ではありません。ただ、今回のような事案が起きてしまったからには、教員には、ルールに則った使い方が求められます。
学校で指定された端末を利用する
今のルールとして多くの学校や自治体で、「個人所有のスマートフォンやデジタルカメラを利用しない」というルールになっていると思います。まず、このルールをしっかりと守ることが大切です。「忙しいから」「手間がかかるから」という理由で個人のスマートフォンを利用してしまっている人もいるかも知れませんが、学校や自治体のルールを破って教職員が使うのは大問題です。
その結果盗撮が疑われてしまっても、学校や自治体は「認めていないものを使っていた」という理由で助けてもくれません。今、保護者たちは子どもたちを心配するが故に非常に過敏になっています。学校の教員みんなが使っているものであれば、違和感はありませんが、個人のカメラやスマートフォンを出せば当たり前に疑いの目を向けられてしまいます。何かが起きたときに周囲に守ってもらうことができるように学校で指定された端末を利用するようにしましょう。
個人の機器は使わない・出さない
スマートフォン以外にも、タブレット端末など学校内にはたくさんのデジタル機器があります。タブレット端末もカメラが付いているのが当たり前であり、使い方を間違えると疑いの目を向けられることになります。
タブレット端末を含めて「個人の機器は使わない」「生徒の前では出さない」とルールを決めているところもあります。このルールもしっかりと守りましょう。先程のスマートフォンと同じで学校や自治体のルールを守ることができない場合には、トラブルが起きたときに助けることができません。学校や教育委員会に守ってもらうためにも、教職員が決められたルールに従って仕事をすることが大切になります。
データの管理は校内のネットワーク内または指定されたクラウドに
3つ目のポイントは、データの管理方法です。デジカメなどで撮影したデータをそのままカメラに保存したままにしておいたり、個人のパソコンやハードディスクに記録していたりしないでしょうか。これもデータの管理方法としてはよくありません。
個人のパソコンやドライブに保存するのは広い意味で言えば情報の流出に該当します。また、撮影した個人情報をずっと放置しておくのも情報管理上よくありません。
デジカメなどで撮影した場合には、学校で指定されているフォルダーまたはドライブにデータをアップロードし、端末からはデータを削除しましょう。学校で指定されているフォルダーやドライブは、セキュリティーがかかっており、外部からの侵入ができないようになっています。仮に、セキュリティー空間からデータが流出した場合には、学校管理者やデータの管理会社が責任を負います。しかし、個人が管理しているデジカメや端末、パソコンからデータが流出した場合には、個人が責任を負う可能性があることを理解しておきましょう。
異性との接触は様々な視点から考えて行動する
盗撮事案でも問題になりましたが、生徒指導上、異性との接触に関しては「様々な視点から考えて行動する」ことが強く求められます。
「小学校の低学年だから大丈夫」「自分(教員)に対して心を開いているから大丈夫」そんな楽観的な考えは非常に危険です。自分の相手にとっては良いと思っても、第三者から見ればふさわしくないと思うこともあります。常に多くの子どもたちと接している教員と教員以外では見方が大きく違います。常に周りからどう見られているのか考えて行動し、道具の使い方に関しても注意をしなければいけません。
生徒指導をする際には
・一対一の状況で指導をしない
・相手の身体には触らない
・話すときには適切な距離感をとって話す
など、自分を守るためにも疑わしき行動をしないことから注意しましょう。特に生徒指導対応の鉄則である「複数対応」は忘れないようにしましょう。
盗撮していなくても疑われてしまう事案は多い
今回大きな報道もあって盗撮が話題となっていますが、実際に現場で働いていると「盗撮をしているのでは」と疑われる事案や保護者からの噂話を聞く機会も多くあります。こうした話が出てきた場合には、管理職に相談するのはもちろん、疑われている人には気が付かれないように行動することも大切です。証拠隠滅の方向に動かれてしまうと、全ての対応が後手に回ります。潔白であっても、犯罪であっても、詳しく調査をすることができるのは警察の仕事です。判断に困ったような状況になれば、速やかに警察に学校から相談して指示を仰ぐのが良いでしょう。
だれでも疑われるもの 防ぐのは普段の自分の行動
盗撮はだれもが疑われると思っておきましょう。もちろん、学校内で盗撮をするというのは教育者としてある前に、人として大問題の行動であり、厳正に処罰される必要があります。盗撮行為をするような人は、二度と教壇には立ってほしくありません。
一方で、現在は「盗撮をしているのではないか」と簡単に疑われやすい状況になっているのも事実です。ルールを守って、高い倫理意識を持った行動をすることが身を守ることにつながることを覚えておきましょう。