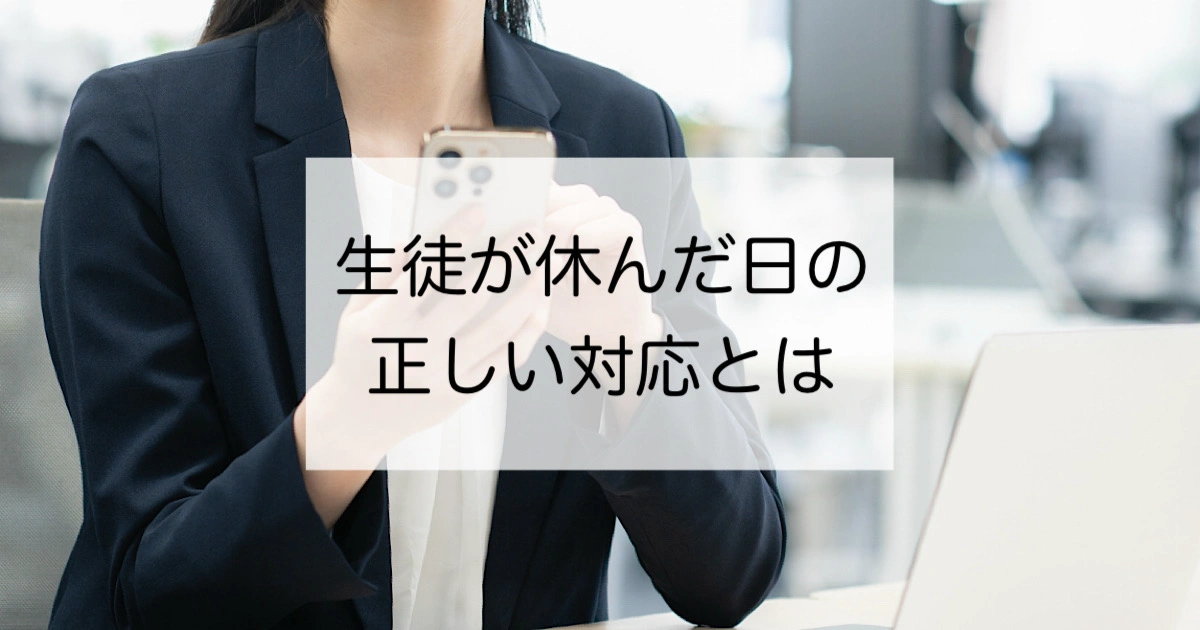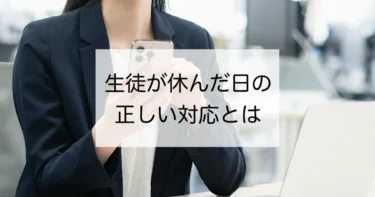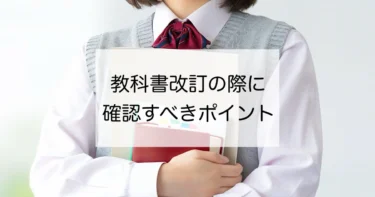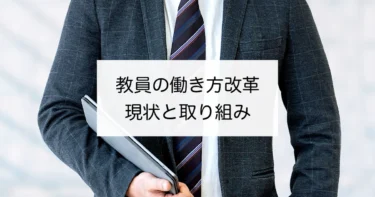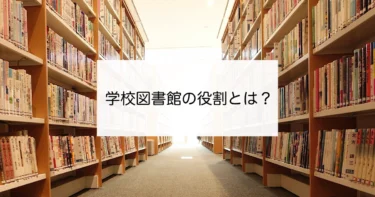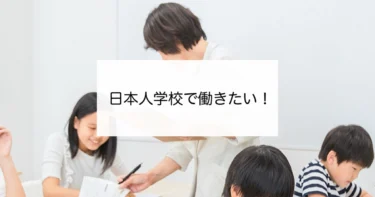新任教員や若手の教員の中には、受け持っている児童・生徒が欠席をした際の対応に悩んだことがある方も多いのではないでしょうか。
心配だから電話したいという気持ちはあるものの「そんなことで電話してよいのか」「電話のタイミングは誤っていないか」などの躊躇する気持ちが生まれてしまう人もいると思います。
筆者は、これまで多くの教員を見てきました。その中で「よい教員」と呼ばれている人に共通する特徴のひとつに「欠席者への対応が上手である」ことが挙げられます。上手に子どもに対応することにより、保護者からも信頼され、周囲からも評価される教員になるのではないでしょうか。
では、欠席者への正しい対応について詳しく解説していきます。明日からの欠席者対応でぜひ活用してみてください。
ライター

emikyon
・元公立学校教員
・教育委員会にて勤務
・eduloライター歴2年
電話で連絡をするときに意識したいこと
はじめに、一番利用する「電話連絡」についてお話しします。電話連絡をする目的は何だと思いますか。まずは、その目的から確認していきましょう。
なぜ「電話連絡」が主流なのか
電話を使う一番のメリットは「相互確認」を即座にできることです。特に子ども健康の状態が明確にわからない場合には、電話で保護者に様子や症状を確認が必要となります。
(例)欠席・早退の理由が「体調不良」「発熱」「風邪」といったケース
(明確な例)インフルエンザや家族旅行など
①直接話せる「電話連絡」が不登校の未然防止にもつながる
最初は体調不良であったものが実は「行き渋り」であったり、単なる風邪だと思われていたものが、実は「インフルエンザ」であったりというように時間が経つことによって判明するケースもあるため確認が必要です。
保護者への電話連絡での聞き取りにより、感染症の拡大防止や、不登校を未然防止することができます。
②即座に状況確認ができる「電話連絡」で事故を防ごう
学校に欠席の連絡が届いていない場合(無断欠席)には、必ず電話での確認が必要です。保護者が欠席連絡を忘れているだけであればよいですが、登校中に事故やトラブルにあっている可能性もあります。
過去にも教員と保護者が子どもの居場所を確認していれば防ぐことができた悲しい事故もあります。(例 牧之原幼稚園バス3歳 熱中症死亡事件など)
すぐに子どもの状態を確認したい、子どもの状況がどうなっているのかわからないので詳しく知りたいときには電話連絡で保護者と相互に確認しましょう。
「電話連絡」のメリット
手紙やメールは、やりとりする情報量が限られますが、電話であれば多くの情報を一度に伝えることができます。
学習のフォローができる
近年はタブレット端末が普及したことによって欠席であっても授業の様子を後から確認したり、課題を受け取ることも可能です。欠席者が情報を見て自分で進めることもできますが、教員が欠席者に対して、何をすればよいのかフォローを入れてあげると子どもも安心します。
欠席した子どもや保護者にとって学校の様子は気になるものです。特に1日休む予定だったのに、2、3日と長引いてしまった場合、不安感が増していきます。このようなときに学校が1本連絡があるのか、ないのかは子どもだけでなく保護者にとっても大きな安心感につながります。初日は手紙やメールで連絡をしていても2日、3日となったときに連絡手段を切り替えるという柔軟な対応が大切になります。
クラスの子どもたちの気持ちを伝えることができる
クラスの子どもたちが欠席者に対してどう思っているのかを伝えることです。病気のことを心配している子どもがいたということや欠席したことで寂しがっている子どもがいるなど、欠席者に対してクラスの子どもたちがどう思っているのかについて少し触れることもポイントです。
電話でなくて手紙を使ってクラスのお知らせを欠席者に伝える場合には、どこかに先生や児童生徒からのメッセージを一言入れておくのも心温まるものになります。病気で休んでいる子どもは、本当は学校に行きたかったのに(行き渋りの子どもではないことが前提)行けない状況です。そんな心に寄り添うようなメッセージがあると、次の登校がしやすくなります。
保護者との信頼関係を築くことができる
保護者との関係が良好な教員は、欠席の連絡の際の「ついで」をうまく活用します。
もちろん、電話の目的は子どもの様子を聞くことですが、そこから普段どのようなことをしているのか、保護者として困っていることはないかなど、家庭での様子を聞き出します。
何もないときに保護者に電話をするのは難しいですが、病気などの確認で電話をしなければいけないのは、ちょっとしたチャンスにもなります。
話をすることでお互いことがわかり、信頼関係を築くきっかけにもなると意識しておきましょう。
手紙やメールで連絡するメリット
子どもや保護者への連絡方法としてもう1つのやり方が「手紙」や「メール」を使う方法です。電話と比べて情報量が少ない手紙やメールですが、電話と違って「情報として残すこと」ができます。 電話の場合は、相手が出ないと用件を伝えることができません。
保護者の中には夜遅くまで勤務していたり、不規則な勤務をしていたりしてなかなか電話に出てもらえないというケースも多いと思います。また、学校の勤務時間の関係上、一定時間を過ぎると留守番電話になってしまい、折り返しをもらっても出ることができないというケースもあります。
このような保護者であるとわかっている場合には、無理に電話するのではなく手紙やメールを使っておくのも良い方法です。着信の履歴も残しておいて、連絡を取りたかったけれども無理であったということが相手にわかれば、学校側から動いてくれようとしていることが相手にも伝わります。
欠席理由が明確であれば「手紙」でもよいが、確認することがあれば電話がよい
子どもの欠席理由には様々なものがあります。「インフルエンザ」や「家族旅行(家事都合)」といったような明確な理由の場合は、保護者に連絡する内容も次の登校日の予定や学習の進捗状況をお知らせするだけでよいです。
しかし、「風邪」や「発熱」といった理由の場合は、いつぐらいまで休むのか、今どんな状態なのかはっきりしていないことを認識しましょう。特に「体調不良」は都合の良い言葉でどうにもとらえることができます。
こうした理由から休みがちになり「不登校」につながっていくというのもよくあることです。子どもが休んだときには、どんな理由で休んでいるのか、本当にそうなのかという気持ちをもって対応に当たることが大切です。担任として何か気になることがあれば、お休みの理由や状況を確認するときに保護者と近況について情報交換することも大切です。
双方のコミュニケーションを取ることで信頼関係を構築
担任と保護者の間でトラブルが起きるときは、小さなボタンのかけ間違いから始まることが多いです。その1つの起点として「教員と保護者の連絡ミス」がよくあります。電話で確認をしておけばよかったことが、確認をしていなかったために子どもが行方不明になった、トラブルに巻き込まれたということもあります。
手紙やメールというのは簡単に使うことができる連絡手段ですが、どうしても一方方向の連絡になってしまいます。電話やチャットといった双方向のやり取りができるシステムもあるので、状況に応じて適切な方法を選択していくことが教員には求められます。