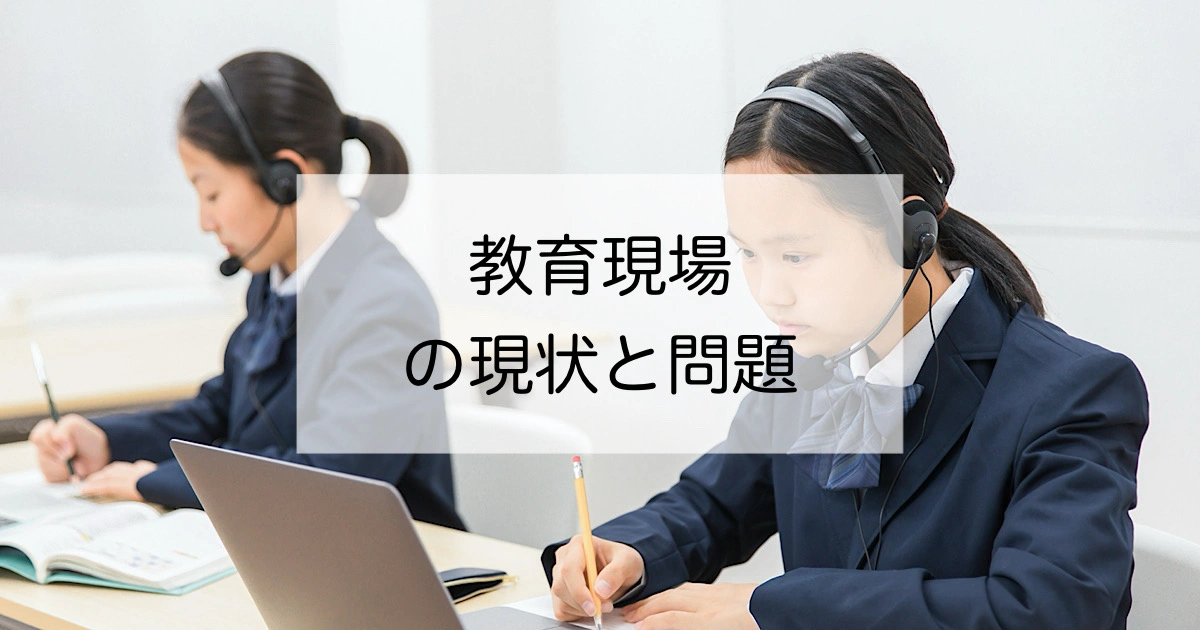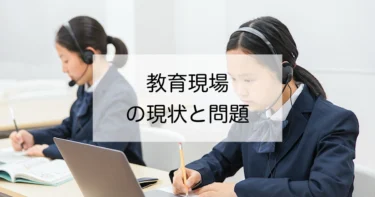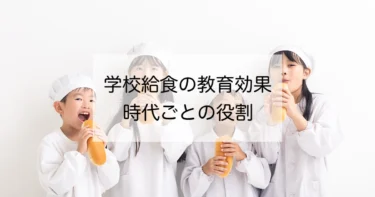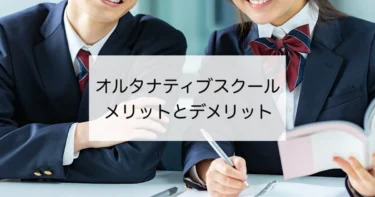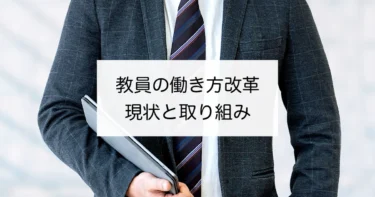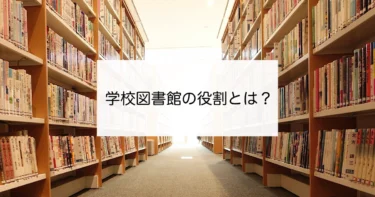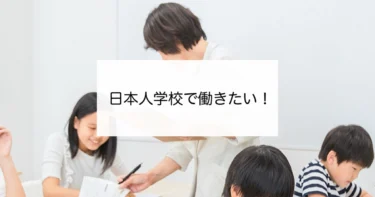急速に変化する現代社会において、学校現場でも、さまざまな教育問題にぶつかっています。人手不足、生成AIの登場など学校が抱えている問題を教育行政勤務者の視点から解説していきます。
指導要領改訂に向けた文部科学省の諮問についても詳しく説明しているので教員・教員志望者の方はぜひ参考にしてください。
教員不足の現状と解決策は、『教員不足が深刻化!現状と解決策は?』をご覧ください
学校における生成AIの活用は、『ChatGPTを教育現場でどのように活用する?文部科学省の見解を解説!』をご覧ください
ライター

emikyon
・元公立学校教員
・教育委員会にて勤務
・eduloライター歴2年
人手不足に悩む教育現場
令和7年度の教育現場は、深刻な人手不足に悩まされています。
「令和6年度公立学校教員採用選考試験の実施状況」によると、公立校教員の採用倍率は3.2倍と過去最低を更新し、学校種別も小学校が2.2倍、中学校が4.0倍、高校が4.3倍といずれも過去最低という結果となりました。
10年ほど前から教員の採用数が増やされましたが、その頃に採用された教員の多くが産休や育休、育児短時間勤務となって教育現場から離れています。そのため、本来は学校教育の中心となる教務主任や管理職までもが担任をしなければいけない状況になっている学校も多くあります。
特に現場で不足しているのが講師の数です。一人の教員が産休に入ると、その部分を講師が埋める必要があります。講師も「常勤講師」と「非常勤講師」がありますが、産休に入る年齢の教員は担任をしていることも多く、代替教員に担任を持たせようと思うと「常勤講師」または「非常勤講師の2名配置」が必要となります。
産休期間に入ってから復帰までという労働期間は、明確ではないうえに、講師不足もあり、多くの学校が代替教員を確保できない状態にあります。管理職も教員が妊娠報告に来ると「おめでとう!」といってあげたいところですが、心の底では「どうしよう」と悩んでいるのは、もはやあるある話です。
参考文献:令和6年度(令和5年度実施)公立学校教員採用選考試験の実施状況について,文部科学省,https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/senkou/1416039_00012.html,(参照 2025-1-8)
働き方改革への期待と懸念
令和7年度は、学校にとって大きなプレッシャーを受ける年になります。その理由が「働き方改革」です。文部科学省は、現行の教員調整額(4%)について段階的な引き上げを明言していますが、一方で、引き上げるための条件として財務省から「働き方改革の進捗を確認」という条件が出されています。これは行政的な視点で見ると、教育の世界で働き方改革が進むのかということを監視するという意味でもあります。
当然、文部科学省から教育委員会を通して調査が入るでしょうし、報告を求めることも多くなります。最終的に何が何でも「働き方改革が推進されて勤務時間が減った」という報告を出させる必要があると、教員に対してプレッシャーがかけられるのではないかと懸念されています。
教育委員会や学校の管理職が上手にマネジメントをして働き方改革が推進されればよいですが、上手くいかないと隠蔽や過少申告といった別の波紋を引き起こす可能性もあるのではないでしょうか。
参考文献:「学校・教師が担う業務に係る3分類」更なる役割分担・適正化の推進に向けた取組について,文部科学省,https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/content/20230721-mext_zaimu-000031074_3.pdf,(参照 2025-1-9)
AIの進展と教育の変化
近年、教育現場での生成AIの活用が積極的におこなわれてきました。子どもたちの調べ学習、画像の生成、教職員の校務支援に生成AIを取り入れて行く流れは2025年度さらに加速することが見込まれています。
校務支援の面でも、文章作成やテストの採点、出欠管理、アプリでの一元管理などに利用され、業務の効率化が進んでいます。
また、授業におけるAIの活用も始まり、これまでのような「一問一答式の発問をして、答えを評価する」ような授業のやり方ができなくなりました。これからは、どう学んだのか、何を使って学んだのかという学習のプロセスを評価することが重要になってきます。2025年は教員にとって、授業も校務も「どのようにAIを活用するのか」がポイントになりますね。
少子化の進行と学校の再編
全国で少子化に伴う学校の再編が始まっています。学校規模の標準は、小・中学校ともに「12学級以上18学級以下」が原則ですが、この数字を下回る学校が増えていることが理由です。また、プールをはじめとした学校施設の老朽化も問題となっています。
そこで、この2つの問題を一気に解決する策として「学校再編」が注目されています。例えば「2小学校1中学校」の校区を「1小学校1中学校」にしたり、「1小学校1中学校」の校区を「1つの義務教育学校」に再編する流れです。こうすることにより、新築する校舎を少なくし建設費用を圧縮することや、小中一貫教育における業務の効率化が可能となります。一方で、登校手段の確保や学校再編による校区の見直しなど、学校だけでなく地域を巻き込んだ検討も必要です。
教育制度・政策に関する問題
文部科学省では、令和7年度から本格的に次回の学習指導要領改訂に向けた準備が始まります。令和6年12月末には、次の学習指導要領改訂に向けた文部科学省の諮問も出されました。ここでは、諮問内容から今年度の動きを予想していきます。今回の諮問内容で特徴的なのが、「負担」という言葉がいろいろなところに入っている点です。
例えば、「教育課程の実施に伴う負担への指摘に真摯に向き合うことを含む、学習指導要領の趣旨の着実な実現のための方策」において
〇教育課程の実施に伴う過度な負担や負担感が生じにくい在り方(学習指導要領や解説、教科書、入学者選抜、教師用指導書を含む)
〇現在以上に増加させないことを前提とした年間の標準総授業時数の在り方、教育課程の実施に伴う負担に留意した上での、現代的な諸課題を踏まえた様々な教育の充実の在り方
のように表現されています。
この「負担」という言葉は教員に対するものなのか児童生徒に対するものなのかによって解釈が変わりますが、どちらにしても今よりも時間数を増やさないことが前提となりそうです。
その上で、現在の授業時間が子どもたちの力を伸ばすことに正しく使われているのか、多様な教育が実施されているのかについて2025年以降は調査が行われると予想されます。
特別支援教育の充実
小中学校には特別支援教育のクラスが配備されているものの、特別支援教育の専門家、または、特別支援教育の免許を持っている教員が指導をしている例は少なく、人材確保も難航しています。さらに、通級指導教育や障がい種別ごとに教員を配置していくこともままならない状態で、クラス数のみが増えていくという状況も起きています。
今回の諮問においても「特別支援学級や通級指導に係る特別の教育課程、自立活動の充実等を含む、障害のある子供の教育的ニーズに応じた特別支援教育の在り方」を見直して考えることが話題に上っています。
参考文献:初等中等教育における教育課程の基準等の在り方について(令和6年12月25日中央教育審議会諮問)【概要】,文部科学省chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mext.go.jp/content/20241226-mxt_kyoiku01-000039494_02.pdf,(参照 2025-1-9)
令和7年は教員にとって大きな変化の前触れに
2025年の教育業界は次の学習指導要領改訂に向けた小さな変化や調査が多くある年になることが予測されています。一人一台のICT端末配備を行ったGIGAスクール構想から5年が経過し、各子どもたちがもっている端末も更新を迎える時期となりました。GIGAスクール構想が始まったころに比べれば端末の利用頻度も増え、インターネット回線も現行の回線では対応できないような大容量のデータ交換も行われています。今後10年の教育がどんなものを目指していくのか。新しい問題が少しずつ出てくる年になりそうですね。