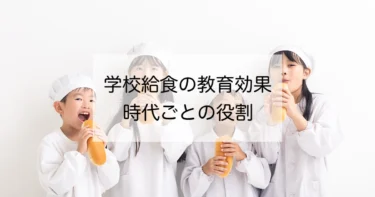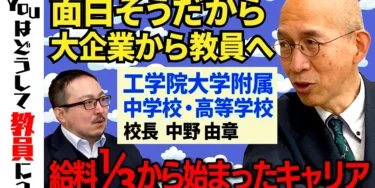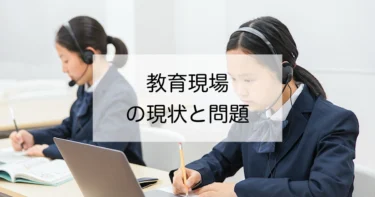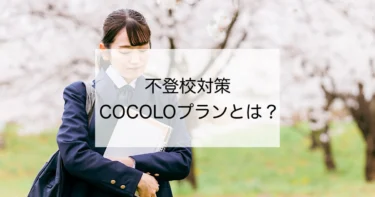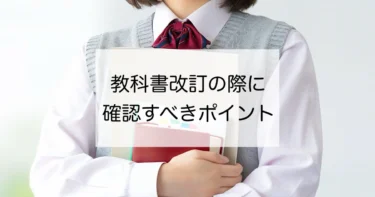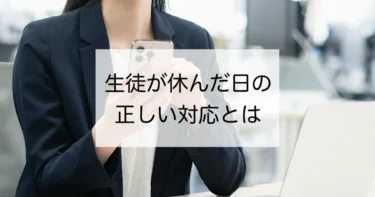子どもたちが楽しみにしている学校生活の1つが学校給食です。日本の小学校では99%、中学校でも91.5%の学校が給食を実施しています。
そんな学校では欠かせない学校給食の目的をあなたは知っていましたか。実は、給食の目的は子どものお腹を満たすだけではありません。
・食生活への意識を高めること
・自己の健康面について考えること
・食文化への理解を深めること
などさまざまな目標が定められています。
そのため、教員にとっての給食時間は、ただ食事をする時間ではなく、「給食指導」という勤務時間になっています。教員以外の方は、食事中に仕事をすることに違和感を感じるかもしれませんが、給食の時間も子どもたちにとっては、学ぶ機会となる大切な時間なのです。
学校給食のアレルギー対策は、『学校給食における食物アレルギーについて教員が知っておくべきこととは?』をご覧ください
学校給食の目的と狙いは、『学校給食の役割!教員が知っておくべきその目的やねらいとは?』をご覧ください
ライター

emikyon
・元公立学校教員
・教育委員会にて勤務
・eduloライター歴2年
時代によって変わってきた給食の目的
学校給食の歴史は古く、明治時代がスタートと言われています。その後、時代の波に呑まれながら給食の目的が変化してきました。まず初めに、給食の始まりから現在に至るまでの学校給食の歴史をお教えします。
給食の歴史
学校給食は、明治22年に山形県鶴岡市で開始しました。当時は食糧事情が悪く、子どもが満足に食事をすることもできない状態でした。そこで栄養状態を改善するために「給食制度」が始まり、全国に広がっていきました。
第二次世界大戦後の食糧難の時期には、アメリカからの援助物資を活用したパンと脱脂粉乳による給食が、全国で開始されました。
そして、昭和29年に「学校給食法」が制定され、学校給食の制度が法的に整備され、その中で「学校給食の目的」が以下の4つに明文化されました。
1.栄養の改善・・・成長期に必要な栄養をバランス良く摂取し、健康な体を作ることを目指す。
2.食習慣の育成・・・望ましい食習慣を身につけ、生涯にわたる健康な食生活の基礎を築く。
3.食文化の継承・・・地域や家庭の食文化を理解し、尊重する心を育む。
4.社会性の育成・・・給食を通して、食事のマナーや公共心を学び、社会性を身につける。
このように給食はただ「お腹を満たすためのもの」ではなく、食習慣や食文化など食に関する学びの場として明文化されました。
参考文献:令和3年度学校給食実施状況等調査の結果をお知らせ,文部科学省
,https://www.mext.go.jp/content/20230125-mxt-kenshoku-100012603-1.pdf,(参照2025-2-1)
子どもたちの居場所づくりとなった給食
平成21年には、昭和から平成と日本の子どもたちの健康を支えてきた給食制度の根幹である「学校給食法」が54年振りに大改正されました。
この法律の第2条で「学校給食の目標」が以下の「7つの目標」に変更になりました。
1.適切な栄養の摂取による健康の保持増進を図ること
2.日常生活における食事について正しい理解を深め、健全な食生活を営むことができる判断力を培い、及び望ましい食習慣を養うこと
3.学校生活を豊かにし、明るい社交性及び協同の精神を養うこと
4.食生活が自然の恩恵の上に成り立つものであるということについての理解を深め、生命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと
5.食生活が食にかかわる人々の様々な活動に支えられていることについての理解を深め、勤労を重んずる態度を養うこと
6.我が国や各地域の優れた伝統的な食文化についての理解を深めること
7.食料の生産、流通及び消費について、正しい理解に導くこと
この改正において新しい目標になったのが「食と社交性や協同」「食と勤労」という『人とのかかわり』が入ってきたことです。給食の時間を通して勤労の精神を磨いたり、友達と一緒に食事をすることの楽しさを学んだりすることが大切であると明記されました。
また近年は、不登校児童生徒数が増加傾向にあります。普段の授業は、教室に入ることが難しくても、給食の時間帯には入ることができる子どもや家庭環境が悪く適切な栄養を取ることができない子どもが給食をライフラインにしていることもあります。そのため、私たち教員が給食時に意識しなければいけないことは「給食を通して子どもたちが学べる時間を作る」ことです。
参考文献:学校給食の目標,一般社団法人全国学校給食推進連合会,https://www.zenkyuren.jp/pdf/leaf_mokuhyou.pdf,(参照2025-2-1)
参考文献:令和5年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果及びこれを踏まえた対応の充実について(通知),文部科学省,https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1422178_00005.htm,(参照2025-2-1)
食文化の継承としての給食
最近の給食では、食文化の継承という新しい取り組みも各地で行われています。栄養教諭や栄養職員を招いた食育の授業や栄養指導、地産地消に対する取り組みもその一例です。
農林水産省では「地産地消コーディネーター」の派遣も行っています。地産地消コーディネーターを派遣することによって、地域食材の生産者と給食を作る人を結ぶようなこともできます。
山口県のある地域では伝統的に食べられてきた「鯨肉」を使った給食を提供したり、名古屋市では姉妹都市であるメキシコの料理が給食で提供されたりと、郷土学習や国際交流の1つとして給食を通した学びも行われています。
転換期を迎えている給食制度
日本の子どもたちを支えてきた給食制度ですが、年々財政状況は厳しさを増し、少子化による影響も出始めています。一方で、支援策を活発化させる自治体もあり、転換期を迎えています。
無償化の進展
1つ目の転換期を迎えているのが「給食費の無償化」です。義務教育において、授業料は無料ですが、給食費については一部保護者負担となっています。そのため、保護者は1食につき300円程度の負担をしています。これは、学校給食法に定められている決まりで、「調理に必要な施設の維持管理費や光熱費、人件費等の経費はすべて市が負担し、食材の購入費は学校給食費として保護者が負担すること」(学校給食法第11条)と明記されています。しかし、家庭の経済状況によっては給食費を保護者が負担することができないこともあるため、生活困窮世帯に限り自治体が負担しているところもあります。
そこで日本政府は、2023年3月に「小中学校給食の無償化」の検討をするとして議論が始まりました。給食費の自治体負担は莫大な財源が必要になります。すでにいくつかの自治体で給食費の無償化を実現しているところもありますが、一方で個々の自治体の財源による差がついているのも事実です。世界的に見ても、義務教育段階の全児童生徒の給食費無償化を実現している国は限られており、今後の国の動向が注目されます。
給食の製造方法
2つ目が給食の製造方法です。給食の製造は各学校で製造する「自校方式」と給食センターなどで作って各校に配送する「センター方式」があります。
自校方式は各学校で調理室、調理員を配置する必要があり、コストがかかります。センター方式も自治体がセンターを建設し、配送しなければいけません。そこで最近、第三の方法として注目されるようになってきたのが「外部委託」です。外部事業者に給食の製造を委託し配送する手法をとる学校も増えてきました。施設の老朽化や児童生徒の減少に伴って給食製造を自前で担うことが困難になってきた自治体も増えており、外部委託型が増えてきています。
アレルギーに対する対応
3つ目がアレルギー対応です。文部科学省からアレルギー対応が出され、各学校においてもアレルギーを持つ児童生徒への対応も厳しくなりました。
原則「完全除去」が明文化されているので、アレルギーに対応する給食を各学校や給食センターで判断して作るのが難しくなっています。また、献立を作る段階でアレルギーに配慮した献立作り(例えば、米粉パンや乳製品を使わないケーキなど)をするなど、子どもたちが少しでも喜んでもらうことができるような努力をしています。ただし、年々多様化していくアレルギー対応のために現場が混乱しているのも事実です。
参考文献:学校給食における食物アレルギー対応指針,文部科学省,https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2015/03/26/1355518_1.pdf,(参照 2025‐2‐2)
学校給食は教育の一環
教員として「学校給食制度」は、いろいろなものを担っていることを知っておく必要があります。給食を楽しみにしている子ども、給食がライフラインの子ども、給食を通して協同を学んでいる子どももいます。
教員は給食が教育の一環であるということ、給食という活動全体を通して、子どもたちに何かを学ばせていく、何かを知ってもらうという意識を持っておくことが大切です。